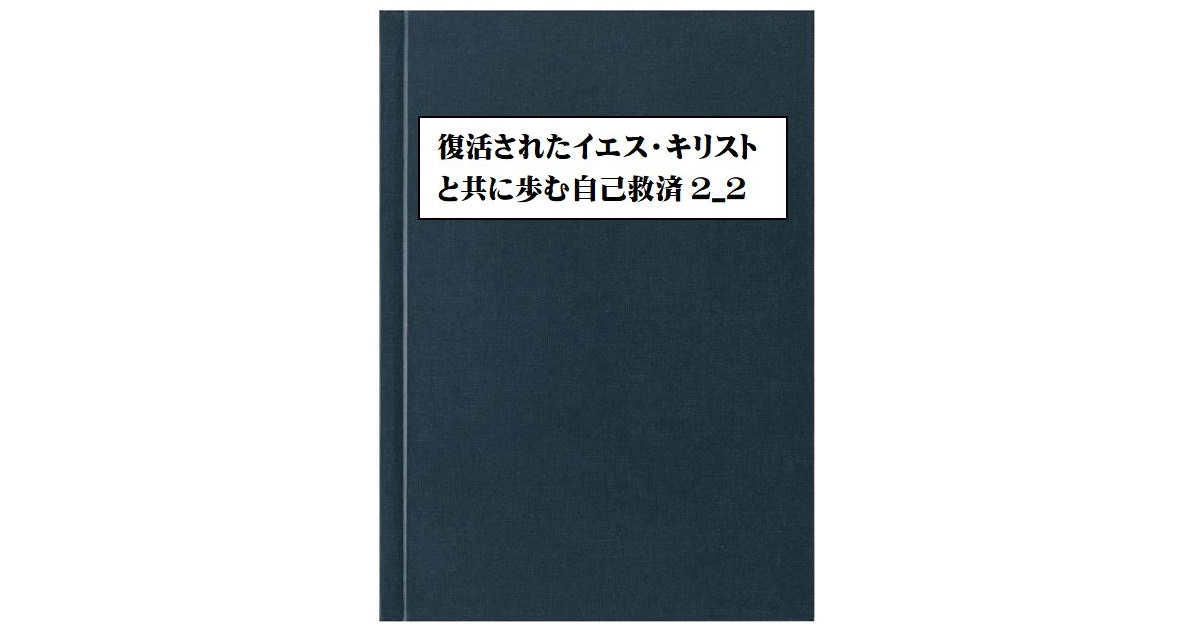第一章 天皇と東大(立花隆・文藝春秋)
この本は、上・下巻で1500ページにも及ぶもので、私(清水)が重要であると思える部分を抜き出して要約、編集して記載させていただきました。明治以降の日本の成り立ちが書いてあり、近代史を教育の中心地である東京大学の変遷という観点から、また、その特異な時代の潮流というものが理解できます。皇室や天皇制についても、偏らない立場で分析されています。この時代のことは、現代における天皇の存在を考える上でぜひ必要な内容です。私は日常的にこのようなことを考える生活をしておりませんので、立花隆の著作を引用させていただきました。
立花隆について
両親は無教会主義のキリスト教徒。両親はキリスト教徒でした。父は早稲田の学生時代に洗礼を受けていますが、母は結婚後、活水(かっすい)女学校のチャペルで受洗しています。無教会主義のキリスト教者と知られる内村鑑三の影響を受けて無教会派になった湊川孟弼という先生が活水女学校にいたのです。その人の影響を強く受けて、両親はのちに無教会派になります。無教会派には洗礼はないので、洗礼を受けたのは無教会派になる前です。念のために言っておくと、僕(立花隆)はキリスト教の影響を強く受けてはいますが、無教会派でも、クリスチャンでもありません。
明治維新から終戦(第二次世界大戦)までの概略
明治維新から終戦(第二次世界大戦)までいろいろな事件がありました。概略だけを簡単に説明するために年号と事件名や日本国内で起こった出来事をまとめてみました。起きた出来事を年号順に記しました。その中には重要な事柄もあるのですが、それは個別に論じるとして、これらのことは、すでにご存知のことが多いと思いますが、出来事の前後関係を確認するためにあらためて記しておきました。
最初の東京大学、つまり帝国大学以前の東京大学が設立されたのは、 1877年(明治10年)です。東大は、明治新政府は日本を近代国家として一刻も早くたち行くようにするために、西洋文明の摂取と人材育成のために作られた大学でした。そして、近代後期(明治時代後半)から現代前期(1945年まで)にかけての時代は、日本が「大日本帝国」を名乗っていた「帝国の時代」といっていいのですが、この間、東大は「帝国大学」(明治30年からは「東京帝国大学」)を名乗り、帝国日本の人材育成の中心的役割を担ってきました。戦前期(初期東大時代、帝国大学時代を含めて)、日本の高級官僚は、行政官も外交官も東大法学部はほとんど一手に供給してきました。
明治22年(1889)2月11日に大日本帝国憲法が発布されました。明治維新の中心的イデオロギーは、尊皇思想でした。国家の基本的な構造を幕府中心の武家政治から、古代さながらの天皇親政に戻してしまおうというのがその基本的発想でした。それを宮中革命(クーデタ)として一瞬のうちに実現してしまったのが、 1868年の王政復古の大号令でありました。
日清戦争は、1894年(明治27年)7月25日から1895年(明治28年)4月17日にかけて日本と清国の間で行われた戦争でした。この後、日露戦争が起きて、それは1904年(明治37年)2月から1905年(明治38年)9月にかけて大日本帝国と南下政策を行うロシア帝国との間で行われた戦争でした。
大正7年(1918)、大学令というものができて(施行は8年)、帝国大学以外の大学が初めて公式に認知されました。それ以前から、早稲田大学、慶應義塾大学など、私立の大学があったではないかと思われるかもしれませんが、それら私立大学は法制度上、正式の大学ではなく、大学の名を呼称として用いることが許された専門学校でしかなかったのです。
関東大震災は、1923年(大正12年)9月1日に発生した大地震によって南関東および隣接地で大きな被害をもたらしました。死者・行方不明者は推定10万5,000人で、明治以降の日本の地震被害としては最大規模でした。
大正デモクラシーの時代に政治は、近代的立憲君主制の側面である政党政治のレベルにまで至っていのですが、5・15事件が契機となって、政党内閣が終わり、途中で断ち消えとなってしまいました。1932年(昭和7年)5月15日(日曜日)に日本で起きた反乱事件で、武装した海軍の青年将校たちが内閣総理大臣官邸に乱入し、内閣総理大臣犬養毅(いぬかいつよし)を殺害しました。その後、2・26事件、支那事変と、軍部の暴走が連続的に起こり、軍隊は天皇にはアンコントローラブルな組織に変わっていきました。2・26事件とは、1936年(昭和11年)2月26日(水曜日)から2月29日(土曜日)にかけて発生した、日本のクーデタ未遂事件です。皇道派の影響を受けた陸軍青年将校らが1,483名の下士官・兵を率いて蜂起し、政府要人を襲撃するとともに永田町や霞ヶ関などの一帯を占拠しましたが、最終的に青年将校達は下士官兵を原隊に帰還させ、自決した一部を除いて投降したことで収束しました。
1937年7月7日、盧溝橋事件から始まった日中両軍の武力衝突は事実上の戦争の開始でありましたが、日本は宣戦布告をせず、支那事変と称しました。1941年(昭和16年)12月8日、日本軍はアメリカの真珠湾を攻撃、太平洋戦争に突入しました。そして、1945年8月15日に終戦を迎えました。これで、近代日本の国制(国体)たる天皇制の終焉となりました。
昭和戦前期の日本において、天皇制の抱える矛盾が、国体問題という形をとって、何度も何度も噴出しました。そしてついには、天皇以上にラディカル(急進的の意)な天皇中心主義者(右翼国粋主義過激派)たちが、国体明徴運動に名を借りて、ほとんど無血クーデタを成し遂げたの如く、国政と社会体制と国民感情を欲しいままに動かしていく体制が作られてしまいました。そしてそれが、軍部と結びつくことで、支那事変以後、国家総動員体制が作られていきました。それが軍部主導のいわゆる日本型ファシズムでした。そして、暴走が暴走を生み、ついには対英米開戦にまで入ってしまいました。1945年に天皇の終戦決断、つまり軍部への統帥権行使によって天皇が事態のコントロール能力を取り戻されました。
日本人は今こそ近現代史を学び直すべき時
日本人は今こそ近現代史を学び直すべき時なのです。日本の教育制度の驚くべき欠陥のために、現代日本人の大半は、近現代史を知らないままに育ってきました。私(立花隆)にしても、一応人よりは歴史に通じているつもりだったのですが、どれほど自分が近現代史を知らなかったかを思い知らされました。一言でいうなら、現代日本は、大日本帝国の死の上に築かれた国家です。大日本帝国と現代日本の間は、とっくの昔に切れているようで、実はまだ無数の糸で繋がっています。大日本帝国の死体はとっくの昔に朽果て分解して土に返ってしまったようで、実は、その相当部分が現代日本の肉体の中に養分として再吸収され、再び構成成分となっています。あるいは分解もせずそのまま残っています。あるいは甦って今なお生きている部分すらあります。歴史はそう簡単に切れないのです。大日本帝国はなぜ、どのように死んだのでしょうか。世界指折りだった大帝国はなぜあそこで消滅してしまったのでしょうか。その消滅を決定づけたクルーシアル(crucial・きわめて重大な)な時間帯はどこにあったのでしょうか。そこがわからないと、日本の未来も見えてこないでしょう。
日本の近現代史における最大の役者は、なんといっても天皇でした。その時代時代の個別の生身の天皇がそれだけ大きな役割を果たしてきたということではありません。天皇という観念、あるいは制度としての天皇が中心的な役割を果たしてきたということです。「大日本帝国」に君臨する君主としての天皇は、一時代前のヨーロッパに君臨していた絶対主義的君主に近い性格を持つと同時に、歴史時代以前から日本に君臨していた巫術王(ふじゅつおう)としての天皇の性格を合わせ持ち、また古代日本において大化の改新という武力革命によって政治権力を確立した武力王としての天皇の性格をあわせもつ一種独特な存在でした。天皇はある場合は、近代国家を作り上げることに邁進する開明的な君主の役を演じ、ある時は、文武両官の上に君臨する絶対君主の役割を演じ、またある時は、まつろわぬ者(大和朝廷に服従しない人)たちを征伐して、天下を統べたいらげんとする武力王の役割を演じました。
天皇は天皇を崇(あが)めたてまつらんとする人々のその時々の思いなしが二重三重に投射されるが故に、あまりにも定義しがたい存在です。それゆえに、天皇は同時にあまりにも多面的な性格を合わせ持たされた日本独特の摩訶不思議な政治装置として機能してきました。この神聖シンボルは日本国の最高価値として崇められ、日本人の生活を律する原理となっていきました。それが天皇機関説問題を契機として始まり、日本中が瞬く間にそのとりことされた、「国体」という観念が日本を魔術的に支配した時代に起きたことです。
*巫術王(シャーマン「巫師・祈祷師」の能力により成立している宗教のトップ)
西洋に追いつくために
伊藤博文は明治憲法を作りましたが、後年、自分たちが若かった頃に受けた教育を振り返って、こう語っています。
「我々は幼少のときには、諸君が今日、学校で修学しているような学問をしようとしても、学校もなければ教える人もなく、わずかに日本の歴史や支那の歴史や兵書のごときものを読んで、その日を暮らしておったのであるが、これすら修めるのに中々容易ならぬことであった」。(「伊藤公直話」 1936年刊)
「我らが幼時にあたって学んだ学問は、わずかに経書や歴史のごときものであって、これに加わるに多少の算術ぐらいを学べは、これをもって足れりとしていたのである。ここに歴史といっても、日本の歴史と漢土の歴史とを除くの外は、他の各民族の歴史を研究することは、もちろん当時においてはできなかったのである」。(「伊藤公直話」 1936年刊)
そのような研究ができない理由は、情報がないという以上に、攘夷論の故だった。「予らが幼時にあたって、学問をなすに困難であった有様をお話ししよう。 維新前十年ないし十四、五年には、国を開いて他国と交際をするかせんかという議論が一定せずして、あるいは鎖国論を主張し、あるいは攘夷論を主張する有様であった。ときにはたまたま開国論を主張するものがあっても、その開国がまた数派に分かれて、ほとんど水火あい容れぬ勢いをなし、党派の分裂を起こすようなことになったのである。しかし当初においては誠に僅々(きんきん・わずかの意)たるものであって、攘夷の議論はほとんど一世を風靡する有様であった。かくの如き時にあたって、欧州の文明を輸入するなどというようなことは、なかなか夢にも思えぬことであった。もし欧州文明を輸入することができなければ、今日行われている社会百科の学が導かるるものでは決してなかったのである。当時においては、洋学を学ぶに際して、翻訳書を尋ねても翻訳書はない。あったところがわずかに砲術書か築城書ぐらいのもので、それもすこぶる陳腐なるもので最近のものではない。しかもこれを読んで、噛み砕くことを得る人間が、日本には極めてわずかであった。この時に当たって、ヨーロッパの学問をしようということを思い起こした者は、ほとんど我が国にはなかったのである。ただ先見有識の士がこれを研磨して、もって大いに国家を誘導しなければならぬという考えを起こしたのである」。(「伊藤公直話」 1936年刊)
日本の洋学というと、よく医学の流れが言及され、1774年に杉田玄白たちが「ターヘル・アナトミア」を翻訳して、「解体新書」を出版したことがその出発点とされます。医学以外にもう一つの重要な洋学の流れとして、実は天文学の流れがありました。この2つの洋学の流れが、東京大学の源流を作りました。
天文学は、古来、天文暦学としてあり、そのいちばん大切な任務は正しい暦を作ることにありました。日本の暦は、平安時代に中国の唐の暦書が輸入され、それがそのまま江戸時代のはじめまで800年以上もあらためることなく使われ続けました。しかし、どんな暦でも、800年も使い続けたら狂います。実際、江戸時代のはじめにおいて、冬至の日付において、2日間の狂いが出ていました。この狂いを何とかしなければならないというので、渋川春海という暦学者が、初めて日本独自の暦(貞亨(じょうきょう)暦)を作りました。この春海は、中国の暦書を参考にするのですが、当時の中国で最も正しいとされる暦書は、イエズス会の神父によって、中国に導入された西洋天文学を基盤とするものになっていました。それは天体運動論はもとより、東西に離れた地点間の時差の割り出し方まで含む理論書でした。はじめ日本の学者たちは、中国経由の西洋天文学の知識を再輸入するだけで済ませていましたが、やがて、それでは日食予報が正しくできないなど現実との食い違いが出てきたために、自ら継続的に天体観測をすることを始めました。あるいは中国の最新天文学の知識はヨーロッパから来たものであることを知って、長崎のオランダ通詞経由で、その知識を直接ヨーロッパから求めました。古代から正しい暦を宣布することは政治権力者の権力の証の1つで、暦が自然の時の流れと狂ったり、予測できない日食が発生したりすることは、権力者にとっても困ったことでありましたので、鎖国下にあっても、このようなヨーロッパ天文学の知識導入の動きは、幕府公認のものとして行われました。特に8代将軍吉宗は、新知識の導入に熱心で、禁書の制限をゆるめ、中国在留のキリスト教神父の書いたものであろうと、科学技術書に関しては輸入を許しました。
そのような流れの中で、やがて「ラランデ暦書」も入ってくるのでありますが、これを初めて手に取った時の驚きを、高橋至時(たかはしよしとき)は次のように記しています。この本は、18世紀末の天文学の名著のアンソロジー(作品集)のようなものでしたから、当時の天文学の最新の知識が全部入っていたのです。全5冊もありましたが、高橋は、他の仕事を全部投げ打ち、寝食を忘れてその翻訳に没頭しました。これ以後、日本の天文学は完全に洋学化し、同時代のヨーロッパの知識にあまり遅れをとらないものとなっていくのでした。観測器具も相当精密なものが作られ、常時観測が行われるようになりました。この時代、伊能忠敬の詳細な日本地図作りが行われましたが、彼の地図がなぜあれほど正しかったのかというと、精密観測器を持った天文方の人間が同行し、天体観測を常時行っていたからなのです。
明治新国家は、あらゆる意味において西欧国家に追いつくことを最優先の課題として、高等教育は、留学生をどんどん送り出すことと、外国人教師を雇って、外国語でそのまま教育を受けさせる(これを正則といい、高等教育機関における日本語を用いた教育は変則といわれた)ことで、現在の外国における教育水準を保ったまま日本に移植しようとしたのです。明治初期、毎年数十人の留学生が各国に送り出され、そのための費用は、国家総予算の2%、教育予算の8分の1に達したというから、生まれたばかりの国家にとって、留学生送り出しの経費がどれほど大きな負担になっていたかわかるでしょう。しかし、明治10年代、20年代に入ると、これら留学生が続々と帰国してきて、教壇に立ち、お雇い外国人教師による教育から留学帰りあるいは、日本の大学卒業者教授による教育に置き換えられていきました。教育現場だけでなく、国家行政機構あるいは国家の中で行われつつあった殖産興業のあらゆる場面で同じ事態が進行していきました。お雇い外国人の手から、日本人の手に仕事が移っていきました。
福沢諭吉の私学
この時代、つまり明治初期においては、大学と国家はある部分では一体化していたのです。つまり国家との一体感が保てるポジションにいることに安心し、誇りも感じるというマインドの持ち主は、大学の至るところにいたのです。そのようなマインドの持ち主に対して、正面から反発したのが、福沢諭吉です。福沢は、明治7年に書いた「学問のすすめ」第四編「学者の職分を論ず」において、官へ官へ流れる洋学者流の知識人たちを批判しました。なぜそれを批判するかといえば、福沢は日本について最も心配していたのは、「政府は依然たる専制の政府、人民は依然たる無気無力の愚民のみ」という現状でした。このような現場を続けていては、「国の独立は一日も保つべからず」ということになるからです。
日本の人民には、自立心がありません、独立の気概がありません。千数百年の専制政治の歴史の中でスピリットが歪められ、卑屈不信の気風が骨の髄まで染みこんでいます。その結果、心に思っていることを口に出していうことができません。人を欺(だま)す、不誠不実、恥を知らないなど、どうしようもない行動様式が出来上がっています。独立心がないから何でも政府を頼みにし、政府に頼ろうとします。しかしそのくせ、政府を欺いて、個人的な利益を得ようとします。官を欺いても、いささかも恥とは思いません。問題は何よりも人民のそのようなマインドを改めることにあります。そのような問題の所在を指摘し、ではどうすべきなのか、何をどのように改めればよいのかという明確な指針を出して人民を導くことができるのは洋学者しかいません。ところが、その洋学者たちは、みんな政府にくっついてしまいました。あくまで野にあって、人民の側に立とうとする者がいません。その結果、「日本にはただ政府がありて、未だ国民あらずと言うも可なり」ということになってしまいました。
福沢は、ここに引用したような表現で、官に流れた洋学者たちを批判し、彼らは独立自尊の心を忘れ、安易に権力にすり寄ってきた姿勢は、日本人全体の気概を失わせた要因の1つと指摘したのでした。
時代の逆行の始まり
元田永孚(もとだながざね)は熊本の出身で、藩侯の侍読(じどく・じとう)を務めていた儒者でしたが、明治4年に、三條実美、大久保利通の推薦で天皇の侍読となりました。侍読とは、天皇の側に仕えて学問を教授する学者のことです。そのときすでに天皇の侍読であったのは、加藤弘之、西周(にしあまね)などの洋学者で、天皇の教育は洋学中心でした。元田は、こういうことではいけない、やはり東洋の君主の帝王学は、四書五経を中心にすべきであると主張して、それを自ら熱心に教えました。明治天皇もその教えを好んだので、元田は、天皇の一番の側近になっていきました。明治天皇は、即位した時わずか15歳で、ほとんど少年でしたから、初期の政治は、自ら親裁することなく、事実上、大久保、木戸、西郷ら維新のリーダーたちの手に委ねられていました。しかし、明治10年、11年に一大転機が訪れます。維新の三傑(木戸、西郷、大久保)の相次ぐ死と、近衛兵が反乱を起こした竹橋事件です。元田ら天皇の側近たちは、これを機に天皇は自らの手で政治をするように求めました。帝王学を身につけ、年齢的にもそれにふさわしい年の頃になっていた明治天皇は側近の助けを得ながら、そうすることを決意しました。天皇が最初に取り組んだことは、教育の刷新でした。洋学中心をやめ、儒教を復興させ、仁義忠孝の念を国民すべての心にしっかり植え付けようとしたのです。明治12年、元田に命じて、「教学聖旨」を起草させ、これを教育の基本方針とすることを命じました。そして、天皇の周辺では、明治維新以来の洋学中心主義にブレーキがかけられて行きました。その中心になったのが、元田でした。
仁義忠孝の心を植え付けるのに大切なのは、何といっても幼少期にあるということで、元田に命じて作ったのが、「幼学綱要」(明治15年)でした。これは、孝行、忠節、忍耐、剛勇など20の徳目を選び、それにふさわしい章句を、四書五経などから選んで掲げ、さらに、その徳目にまつわるエピソードを中国、日本の古典から選んで絵入りで掲げるというスタイルがとられていました。「幼学綱要」の編集に協力を求められた学者は、道徳は世界共通なのだから、欧米のエピソードも取り入れてはどうかと進言したのですが、元田は道徳は教育の基本だから、日本と中国中心がよいといって、欧米のものは一切取り入れませんでした。「幼学綱要」は、ほとんどそのまま子供用儒学の教科書といってもよいものでした。このあたりから、文明開花の明治は、国粋主義の明治へと大きく梶を切り替えていくのでした。彼らが目指していたのは、「古今を折衷(せっちゅう)し、経典を斟酌(しんしゃく・相手の事情や心情をくみとることの意)し、一の国教を建立する」そのことだったのです。つまり、「幼学綱要」から「教育勅語」に至る道です。元田の「教育議附議」は、そこを明確にしています。
国教を作る賢哲を待つ必要はありません。天皇その人が人民の君であり師であることを天職としている人なのですから、天皇以外の賢哲を待つ必要はありません。大変なゴマのすりようもあったものです。要するに、天皇が勅語という形で国教を建てればよいというのです。国教の内容を新しく作る必要もありません。天皇の先祖の教えを継承するだけでいいのではないかというのです。瓊々杵尊(ににぎのみこと)以来の天祖を擁し、それに儒教を加えればよいというのです。要するに、天皇を、祭祀の長であると同時に、政治の長でもあり、教学の長でもある祭政教学一致の存在にしてしまおうということで、復古主義そのものなのであります。このあたりから、天皇の神格化が始まります。明治12年前後にこのような文明開花・欧化主義から天皇中心の復古主義への大転換がありました。
元田と明治天皇は文部行政について、初等中等教育については、元田が作った「幼学綱要」を宮内省から直接に配布するという文部省頭ごしの異例の教育干渉をしたことで、それなりに満足していましたが、高等教育については、不満がいや増しにつのっていたのですが直接の口出しもできないでいました。要するに明治天皇は、理系の学科にはほとんど関心がなくて、大学に修身はあるのかないのかが、もっぱらの関心事だったのです。理系の学科を卒業して人物をなしても、それはそれぞれ特定のサイエンスの分野で評価される人間になるに過ぎません。政府に入って大臣など国家をになう人物(入りていて相となるべき者)になるわけではありません。今の日本はまだ明治維新の指導たちによって支えられています。しかし、彼らとて、そう長くは指導者の位置に止まれません。彼らの後継ぎが必要です。しかし、国家の指導者になる者に何より必要なのは、修身の学、仁義忠孝のわきまえです。それが高等教育に欠けているではないかということなのです。
日本の歴史学の回生
久米は旧佐賀藩士で、藩校の弘道館では、大隈重信と同窓でした。旧佐賀藩主鍋島直正の近習となり、その推輓(すいばん・ある地位や役職に推薦したり引き上げたりすることの意)によって岩倉使節団の一員に加えられた時、33歳でした。久米はその能力をかわれて政府の修史館の編修官に任ぜられました。修史館というのは、明治維新後、国家的歴史の編纂事業をするべく太政官正院に作られた修史局の後身です。修史局以来、この仕事を中心的に推進していたのが、旧薩摩藩士の重野安繹(やすつぐ)でした。彼は中国史の考証学と西洋史の実証主義の影響を強く受け、史料批判と考証に長じていました。日本が初めて生んだ本格的歴史学者というべき人で、のちに、史学会の初代会長に選ばれるなどその学殖は高く評価されていました。旧来の史料編纂(へんさん)をしていた修史局が、明治21年に、そのまま帝国大学文科大学に移管しました。それが東京大学史料編纂所の始まりでした。修史局の中核的存在であった、重野安繹、久米邦武らは文科大学の教授に選任されました。
日本の従来の歴史学の最大の欠点は、歴史と物語が分かちがたく絡み合っているところにあります。本当の歴史学を樹立するには、まず「この物語の弊風(へいふう・悪習の意)を脱する」ことが何より必要です。ただ事実のみを追求し、事実が発見されたら、筆を曲げずに、それをストレートに伝える、これこそ、歴史学において最も大切に守らるべき大原則です。重野も久米も見解を同じくしていました。大衆と大衆レベルの歴史家が、歴史に持ち込み易い誤りが、勧善懲悪のイデオロギーです。歴史においては、結局、善なるものが勝利し、悪は滅んできたという思い込み、あるいは、歴史を書くものは善を勧め、悪を懲らしめるように書かねばならないとする思い込みがあります。この2つの思い込みが歴史における勧善懲悪イデオロギーを形成しますが、日常生活道徳や社会道徳における勧善懲悪イデオロギーと並んで、日本人の心性の中に深く入り込んでしまっています。日本人の歴史観は基本的にこのイデオロギーによって染め抜かれてしまっています。
孔子は、春秋時代の中国の思想家、哲学者で、儒家の始祖です。そもそもなぜ孔子が「春秋」を書いたのかというと、世の道徳が廃れ、邪説暴行が幅を利かせている現状を嘆いてのことでした。孔子自身は、「わたしは世の乱臣賊子(らんしんぞくし)に筆誅(ひっちゅう)を加えようとして「春秋」を書いたと、自著について語っている通り、これは勧善懲悪の書なのであります。だから、これは、歴史的事実をそのまま記述した歴史書ではなく、いろいろ理屈をこねては、乱臣賊子は悪業の報いによってこれこの通り滅びの道をたどりましたとこじつけていった書物なのです。このような勧善懲悪的イデオロギーから早く脱して、事実を事実として見すえるところから出発しなければ、真の歴史学の確立はないということを力説したのが、久米邦武でした。これは、日本の歴史学を長らく害してきた儒教主義(春秋の筆法、勧善懲悪主義、大義名分論)への決別宣言といえるでしょう。史学会は、このような決別宣言を持って、史学をスタートさせようとしたのです。しかし、現実には、決別どころか、生まれたばかりの新しい日本史学は、旧来の儒教主義的(+皇道主義的)史学に全面屈服してしまいました。
再び従来の歴史学への回帰
問題は、久米邦武が、「太平記」批判に続けて、「史学会雑誌」に書いた「神道は祭典の古俗」と題する論文をめぐって起きました。この論文は、神道の淵源を辿ったもので、神道とは宗教ではなく、ただ、お祭り、災いを追い払い、福をもたらすべくお祓いをするというだけの古来の習俗であるという主張なのです。それは習俗であって宗教ではないから、仏教あるいは他の宗教と並び行われても少しも問題は生じません。事実、日本では昔から敬神と崇仏が並び行われてきました。
考えてみると、あらゆる宗教は、このようにして神なる概念を考えだし、それを拝むことによって始まりました。その拝む対象は、だいたい天でありました。天にいる神でありました。同じ天にいる神を拝みながら、神道が他の宗教と違うものになったのは、他の宗教は、教義体系や教団などを作り、組織化された制度化された宗教になったのに対し、神道は救主も救済もなく、教義体系もなく、ただ古来の自然崇拝的な習俗のままにとどまったという点だといいます。だから宗教でなく習俗だという捉え方をすることができます。 要するに、神道は、極めてプリミティブ(原始的の意)な発展段階にあった原始宗教であり、一つの宗教として自立する以前の宗教的雰囲気を伴う習俗にとどまっていました。そこに高度に発展した仏教が入ってきたのですが、神道にはそれに宗教として対抗するだけの内容もなく、そうする意志もなかったと考えられます。かくして神道は、宗教以前の段階で止まり、それ以上宗教として発展することをやめてしまったから、かえって、その後も他の宗教と融和・共存しつつ長い生命を保つことになったというのがこの論文の基本的な趣旨です。そういわれて見ると、なるほどと思われる分析ですが、神道の側はこのような分析に怒り狂い、総力をあげて久米と、その背後にいるとされた重野を攻撃しました。攻撃のポイントとは、この論文は、皇室と皇室の祖先を侮辱する不敬不忠の論文だということにありました。
この主張によって、問題はみるみる政治問題化し、文部省は久米を非職にして公務員の身分は残しますが、その職務は一切取り上げるとしたので、久米は自分から職を辞して、早稲田大学(東京専門学校)に去り、重野は免職となりました。 史学会は会長とエース級の学者を失い、東大の国史科は2人の教授を失うことになりました。これは日本の大学に初めて起きた、学問の自由、大学の自治を揺るがす大問題であったにもかかわらず、大学の内部からも外部からも、この2人に救いの手を差し伸べようとする動きは全く出ませんでした。
今から考えてみると、久米邦武事件(明治25年・1892)は、大きな歴史の曲がり角でした。あのあたりから、国家は学問を支配することが始まり、日本の歴史学はねじ曲げられ、神話が歴史を抑え込み、国民は子供の時から神話的国家観を頭に叩き込まれるようになったのです。天皇神格化は明治天皇自身のヘゲモニー(覇権)で行われました。明治14年の教則綱領によって、それまで小学校で教えられていた万国史(西洋史と中国史)の授業が廃止となりました。天皇に忠誠を励む人間であれば、国際性なんて全く欠如していても問題ではないとされたのです。その後の日本を特徴づける完全内向き型人間づくりの基本レールはこの時に敷かれたのです。
大正デモクラシーの輝ける旗手・吉野作造
吉野作造は、明治37年(1904)法科大学政治学科を首席で卒業し、明治42年(1909)法科大学助教授に任ぜられ、翌年から3年間欧米に留学しました。帰国するとすぐに、「中央公論」の主幹の滝田樗陰(たきたちょいん)の訪問を受けました。滝田の勧めによって書いた「学術上より観たる日米問題」が高く評価され、それから吉野は、ほとんど毎号のように、「中央公論」に書くことになりました。
特に著名なのは、大正5年(1916) 1月号に乗った「憲政の本義を説いて某有終の美を済すの途を論ず」という、100ページにも渡る長大な論文です。これは、従来、天皇制の日本において、人民主権のデモクラシーを唱えることは、国体に反する危険思想とみなされていたのに対し、巧みなレトリックをもって、天皇制とデモクラシーは決して矛盾しないどころか、明治憲法の精神を本質的に実現しようと思ったら、むしろ、デモクラシーによらざるを得ないということを説いて、天皇制とデモクラシーを調和させ、大正デモクラシーの基礎理論となった論文であります。
どのようなレトリックで天皇制とデモクラシーを調和させたかというと、デモクラシーを1つの概念として捉えず、実はこれを2つの面を持った複合概念であるとして、1つの面は捨てるが、他の面を拾うことによって可能となるとしました。具体的にいうと、国家権力の所在がどこにあるかという権力論としてのデモクラシーは人民主権説であり、これはたしかに天皇に国家主権が帰属するとする日本の憲法の立場とは全く相容れない危険思想であるとします。しかし、デモクラシーには、もう1つの面、政治のあり方としてのデモクラシーがあるといいます。どのような目的を持って政治を行うのかといえば、民衆の利福のためであるべきであり、政策決定はどのようになされなければならないのかといえば、民衆の意向に沿う形でなされるべきであるという意味においてのデモクラシーであります。この意味でのデモクラシーは天皇制とも調和します。歴史的天皇主権の政治も民衆の利福のためになされてきたのだし、民衆の意向に沿う形でなされてきたのです。そして、こちらの意味のデモクラシーのためには、現実政治にもっと議会中心主義的要素を入れていった方がいいと主張しました。そして、デモクラシーのこの2つの面を区別するために、後者の意味のデモクラシーの訳語は、民本主義とするのがよいとしました。従来の民主主義という訳語は権力所在論としての人民主権論であるとの誤解を招きやすいからであります。吉野の民本主義は冬の時代として閉塞状態にあった社会思潮に明るい灯をともし、その上に、大正デモクラシーの花が咲いていきました。
上杉慎吉は、希代の天皇中心主義者
上杉慎吉は明治10年(1878)福井県の生まれで、明治36年東京帝国大学法科大学政治学科を卒業後、すぐに助教授に任ぜられました。上杉は、希代の天皇中心主義者、天皇の権力絶対主義者でした。彼は、天皇がいついかなる理由によって、いかなる勅語を下そうと、それは天皇の絶対的自由に属することだから、臣下はそれに口を挟んだり、その形に関して疑問を持ったりなど、してはならないことだと考えました。現代人は「上杉の国体論」に違和感があるかもしれません。戦前の日本は天皇制の国だったとしても、天皇は専制君主ではなく立憲君主だったのではないでしょうか。日本には憲法があり、議会もありました。天皇の統治も、憲法に従って行われ、議会の協賛によって行われたのではないのでしょうか。そうだとしたら、天皇の権力はオールマイティーではなく、法と議会の制限のもとにあったのではないでしょうか。明治憲法の下にあっても、天皇の権力はこのように理解されていたと考えるかもしれませんが、必ずしもそうではなかったのです。後に紹介する美濃部の天皇機関説、あるいは吉野作造の民本主義など、自由主義的な傾きを持つ所説の持ち主はそう考えていましが、伝統的な国家公認の学説はそうではありませんでした。上杉の憲法論によれば、日本の憲法(明治憲法)は議会政治を排斥するものであるから、議会政治をよしとする主張そのものが誤っているのです。なぜ議会政治が排斥されるのかというと、日本の憲法はあくまで天皇中心主義であり、天皇を唯一の主権者と認めているからです。イギリスのような(それは戦後の日本のようなということでもありますが)、議会の多数を握った政党が内閣を自由に組織し、大臣の任免権も行政権も握って一国を支配するというような制度が日本でも実現したら、天皇制は有名無実になってしまいます。
上杉は国体と政体を区別して論じます。国体という言葉は、現代においてはほとんど使われないから、なかなか理解が難しいのですが、要するに国体とは、国家権力の根源の所在がどこにあるかという意味での国家の根本的なあり方のことで、政体とは政治権力のあり方、すなわち政府の形態ということであります。国体という言葉は、もともとは、国がら、国ぶりといった意味から、国家の体制(政体)の意味に至るまで幅広く用いられてきました。ある時期から、天皇制そのものといっても政治的権力機構としての天皇制ではなく、ときどきの政治権力のあり方がいかに変わろうとも、その上位に伝統的宗教的権威としての天皇が連綿として存在し続け、それが世俗権力の権威を認証するという形で政治権力に正統性を与えるメカニズムということを意味するようになりました。
明治国家は、しばらく天皇親政という形をとり、国体と政体の間に乖離(かいり)がないシステムをとっていましたが、明治18年の内閣制度発足、明治22年の憲法発布、翌年の帝国議会開設によって、国体と政体の間にしだいに乖離が生じ、政治制度の運用の問題としても、政治思想としても、政治のあり方はどうあるべきか、それをこれからどう変えていくべきかの議論が盛んになったがというのが、この大正デモクラシーの時代なのでありました。
上杉慎吉のような天皇中心主義者にとって、政治はすべて天皇の統治大権によって、天皇は自分の意の赴くままに行ってよいものだから、民意は必ずしも問う必要がありませんでした。議会はあっても、それは天皇に協賛することだけを目的とする機関(立法機関ではない)でしたから、あまり重要視する必要はありませんでした。議会に根を張る政党などというものは、政治的諸悪の根源に過ぎないから早く撲滅すべしというのが上杉の主張でした。
天皇機関説の主帳
天皇機関説とは、大日本帝国憲法下で確立された憲法学説で、統治権は法人たる国家にあり、天皇はその最高機関として、内閣をはじめとする他の機関からの輔弼(ほひつ・天子の国政を輔佐することの意)を得ながら統治権を行使すると説いたものです。
東京帝大教授の一木喜徳郎は、統治権は法人たる国家に帰属するとした国家法人説に基づき、天皇は国家の諸機関のうち最高の地位を占めるものと規定する天皇機関説を唱え、天皇の神格的超越性を否定しました。この説は国家の最高機関である天皇の権限を尊重するものであり、日清戦争後、政党勢力との妥協を図りつつあった官僚勢力から重用されました。
日露戦争後、天皇機関説は一木の弟子である東京帝大教授の美濃部達吉によって、議会の役割を高める方向で発展しました。すなわち、ビスマルク時代以後のドイツ君権強化に対する抵抗の理論として国家法人説を再生させたイェリネックの学説を導入し、国民の代表機関である議会は、内閣を通して天皇の意思を拘束しうると唱えました。美濃部の説は政党政治に理論的基礎を与えるものとなりました。
天皇機関説とは何かといいますと、国家の主体はどこにあるのかという問題です。言葉を換えていえば、国家の統治権はどこに属しているのかという問題です。国家の統治権は、天皇個人に属していて、天皇はそれを自分の好き勝手にどのようにしてでも行使してよい権力として持っているのか、それとも、統治権の主体は国家そのものにあり、天皇個人は国家の最高機関としてそれを行使する機能を持つに過ぎないのかという問題です。つまり、日本という国はルイ十四世の「朕は国家なり」タイプの専制主義国家か、それとも、国家元首といえども法に基づいてその統治権を行使しなければならない立憲君主制の国なのかという問題です。
美濃部達吉の息子である美濃部亮吉は、「苦悶するデモクラシー」(文芸春秋新社刊)において、この問題をわかりやすく次のように解説しています。
「父は、天皇は国家の機関であると主張します。というのは、国家は団体であり、統治権を持っています、しかし、国家そのものが直接に統治権を行使することはできません、団体がその権利を行使するには、それを代表する機関を通じなければなりません、会社にしても、その機関である株主総会なり、重役会なりによって、その権利を行使します、国家の場合も全く同様で、統治権という権利は、その代表機関を通じて初めて行使することができるのだと説明します。そして、天皇もそういう機関の一つであり、「天皇之を統治す」という条文も、天皇は国家の機関の一つとして、国家のためにそれを代表して統治権を行使するのだと解釈します。(略)
あらためて思うことは、天皇機関説について誤解を受けずに書くことは難しいということです。だいたい天皇機関説という言葉それ自体が誤解を受けやすいと思います。天皇機関説と聞いても、そのままでは意味が掴(つか)めず、天皇を国家の一つの機関とみなす説だと解説されても、その意味がわかりません。機関とは何なのですか?天皇を機関とみなすとはどういうことなのですか?と幾重にも疑問に疑問が重なって、いつしか訳のわからなさに入り込んでしまうのが、普通の人の天皇機関説理解の一般コースでしょう。
それは今に始まったことではありません。昭和10年に起きた天皇機関説問題は、世を揺るがせたといっていいほど大きな社会的事件になりましたが、その渦中においても、天皇機関説を法理論として正しく理解した上で議論をしていた人はむしろ少なく、大多数の人は意味がよくわからないままに、議論に参加していたのでありました。「天皇陛下を機関呼ばわりするなんてけしからん」という程度の誤解に満ちた大衆の反応が社会を動かしたのです。確かにあの時代、天皇機関説はけしからん、の声が世に満ち、美濃部の天皇機関説は社会から排斥されていきました。その時の機関説に対する反発は、主として理論的内容に対する反発ではなく、天皇機関説という言葉の持つ異様な語感によって醸し出された心情的反発であったと思います。それは理性よりも、情動反応に基づく反発でありました。しかし、社会心理学が教えるところでは、世の中しばしば、理性的判断より、情動によって、より大きく動かされるようです。
私(立花隆)も今は慣れましたが、初めて「天皇機関説」の言葉を聞いた時は何か異様な気がしました。天皇と機関がなぜ結びつくのかわかりませんでした。美濃部だったか、他の機関説論者だったか、機関説の「機関」は、もともとorganの訳語として生まれた言葉なのですが、むしろ、「器官」と訳しておけば、もっとずっと理解してもらえただろうといっていました。なるほど、その方が多少の風当たりが少なかったかもしれません。「器官」の言葉を用いるとして、どういうイメージを持ってもらったら、いちばん誤解が少なくなるでしょうか。それはやはり頭部でしょう。国家を人体に見立てて、その頭を天皇に見立てるというのが、天皇機関説のそもそもの発想でした。実は同じようなことを、明治天皇自身は軍人勅論(ぐんじんちょくゆ)の中でいっています。
「朕は汝等軍人の大元帥なるぞ。されば朕は汝等を股肱(ここう)と頼み、汝らは朕を頭首と仰ぎてぞ、其親は特に深るべき」
訳すと、「天皇は軍人たちを自分の手足と頼むといい、軍人たちには自分を頭首と仰いで、その関係は特に深くなくてはならぬ」、といっているのです。明治天皇自身も「天皇は国家の最高機関である。機関説で良いではないか」といったといいます。
軍人勅論のこのくだりこそ、まさに天皇機関説のイメージそのものだと説明していれば、このような反発を受けなかったに違いありません。天皇機関説といわず、天皇頭首説といっていたならば、歴史は変わっていたに違いありません。要するに天皇機関説とは、国家生命体論です。
軍部が執拗(しつよう)に美濃部攻撃を続けた背景には、海軍も陸軍も、反軍国主義的イデオローグたる美濃部を相当恨んでいたという事実があります。それは天皇の神格化の問題に絡んできます。軍が機関説で許せなかったのは、それが天皇の聖性を弱めるということでした。軍にとって日本の国体の本質は、天皇の神聖不可侵さにありました。そしてその神聖不可侵さに軍が統帥権で結びついていることにありました。しかし、陸軍大臣、海軍大臣が議会でこの問題に対する見解を問い詰められ、天皇機関説反対の意見を何度も表明しているうち次第に、「政治にかかわらず」を原則としてきた軍部も、この問題ばかりは、中心的にかかわっていくようになりました。そしてついには、軍が天皇機関説排撃の最も中心的な勢力となり、軍の主張に沿う形で現実政治を機関説排除の方向に動かして行くようになりました。それもはじめは控えめな現人神信仰の表明と機関説容認の困難さの表明にとどまっていたのに、途中からは、主張からも行動からも、控えめなところが吹き飛び、あからさまに政府に圧力を加えるようになっていくのでした。それは同時に、天皇機関説問題が国体明徴運動(こくたいめいちょううんどう)に転化して行く過程でもありました。国体明徴運動も、はじめはもっぱら政治的要路の人々(政府当局者、各大臣)に対する、イデオロギー的見解表明(天皇機関説反対、国体擁護)の慫慂(しょうよう・誘って勧めることの意)ないし強要でしかなかったのに、やがて、社会のあらゆるセクターでの国体明徴運動に転化していきました。それに伴って、機関説排撃の根拠としての現人神信仰が社会全体に押し広げられていきました。その行く着く先は、現人神信仰とミリタリズムを社会の基盤に据えた、独特の日本型ファシズム社会でした。天皇機関説問題が歴史的に果たしたいちばん大きな役割は、このような社会変化をもたらす最大の動因となったことであると考えられます。
天皇機関説問題は、1935年(昭和10年)2月18日における貴族院本会議での菊池武夫(元陸軍中将)議員による美濃部を「反逆者」「謀反人」「学匪」呼ばわりしての排撃演説から始まりました。東京帝国大学法学部内部には、上杉慎吉、穂積八束(やつか)など、天皇は現人神であり、当然のことながら絶対的な権力を持つという神がかり的な絶対主義的君主主権説をとる学者がいましたし、それと結ぶ、右翼政治団体、軍部などの勢力もありました。それら諸勢力が連合して美濃部を追い詰めていったのが、天皇機関説事件です。その背景には、統帥権問題という、統治権と並ぶ天皇の大権の問題が絡んでいました。
戦後の天皇機関説については、第二次世界大戦後、改正憲法の気運が高まる中、美濃部は憲法改正に断固反対しました。政府、自由党、社会党の憲法草案は、すべて天皇機関説に基づいて構成されたものでありました。しかし、天皇を最高機関とせず、国民主権原理に基づく日本国憲法が成立するに至り、天皇機関説は憲法解釈学説としての使命を終えました。
明治憲法の由来 王権神授説と現代におけるエンペラーという呼称
明治政府の憲法草案は、明治19(1886)年から、ドイツ人顧問のロエスレルらの助言を得て、伊藤博文を中心に井上毅(いのうえこわし)・伊東巳代治(いとうみよじ)・金子堅太郎らにより作成されました。明治憲法は天皇制の神聖な部分と、近代的立憲君主制をうまくつなぎ合わせようと、伊藤博文が苦心惨憺(くしんさんたん)して作り上げた不思議な憲法でした。
それは第一条(大日本帝国は万世一系の天皇之を統治す)、第二条(皇位の皇男子孫による継承の規定)、第三条(天皇は神聖にして侵すへからす)によって、天皇制の血脈由来の神聖なる性格(万世一系)を保障し、それ以下の条項で近代的立憲君主制の君権制限的部分(統治権は憲法の規定に従って行使するとか、立法権は議会の協賛をもって行うとか、国民に一定の権利を保障するなど)を並べるという構造になっていました。それ以外に、実は現代人のほとんどは読んだことがない部分として、最初に「告分(こうもん)」という、神主があげる祝詞(のりと)のようなものがついていました。さらに、憲法発布にあたって発した「勅語」と、憲法の公布にあたって付した「上輸(じょうゆ)とがついていて、この三つが一体となって、いわば現代の新憲法の全文と同じ役割を果たしていました。天皇はなぜ憲法を作って、それを臣民に与えるのか、その理由を説明し、神話にまで遡って、その意義と正当性を説明していました。それは同時に天皇という存在の正当性の神話的説明でもありました。こういう構造を取ることで、明治憲法には、ヨーロッパの近代国家は近代に移行する際に捨て去った王権神授説的部分がそっくり残ることになりました。それによって、日本国は、近代国家の体裁を保ちながら、同時に、万系一系の神聖天皇は天の命令によってこの国を永遠に(天壌無窮)支配することになっている宗教的神聖国家であるという独特な性格が付与されていました。その関連もあって、日本の立憲君主制のシステムにおいては、君権は必ずしも十分には制限されず、議会などの掣肘(せいちゅう)を受けない天皇大権はかなり強力に残されました。また、重要な天皇大権として、軍を率いる統帥大権(第十一條)と、軍の編制並びに常備兵額を決める編制大権(第十二条)とがありましたが、それと議会の持つ権限(法案並びに予算の審議権)、並びに内閣の持つ権限との関係にも曖昧な部分が残りました。
英語で天皇は「エンペラー」と訳されますが、こういった経緯からエンペラーと呼称されているのだと思います。天皇は天子の尊号であります。王権神授説的な歴史的意味合いから日本という国のシステムに組み込まれているゆえの名称であると思います。
昭和15年の「小学国史上巻尋常科用」を開いてみます。まず、「神勅」というものが、頭のページに載っています。
神勅 豊葦原(とよあしはら)の千五百秋(ちいほあき)の瑞穂(みずほ)の國(くに)は、是(これ)吾(あ)が子孫(うみのこ)の王(きみ)たるべき地(くに)なり。宜(よろ)しく爾皇孫(いましすめみま)、就(ゆ)きて治(しら)せ。行矣(さきくませ)、宝祚(あまつひつぎ)の隆(さか)えまさむこと、当(まさ)に天壌(あめつち)と窮(きはま)りなかるべし。(神代紀、第九段、―書第―)
(訳)日本はわたしの子孫が天皇となる国です。その皇位は天地とともに永遠に栄えることでしょう。 これは「日本書紀」にある言葉で天壌無窮(てんじょうむきゅう)の神勅と呼ばれています。天照大神が、自分の孫である瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)を地上降らせる(天孫降臨)ときに、与えたとされる言葉で、天と地がきわまりないように、おまえの子孫がずっと豊葦原(日本のこと)を支配するのだぞという意味です。
これが万世一系の天皇の支配権の根拠になっています。天照大神はそう命じたのだからという訳です。文書記録上、天皇の支配権の根拠は、「日本書紀」のこの記述にしかありません。大日本帝国憲法の第一条「大日本帝国は万世一系の天皇之を統治す」の根拠はこれだということは、憲法を作った伊藤博文が明言しています。要するに、天皇制はすべてが、この神話の上に築かれているのです。だから、それをまず、小学校の歴史教科書のはじめに載せたわけです。
キリスト者・矢内原忠雄の論文「日本精神の懐古的と前進的」
矢内原忠雄(やないはら ただお)は、1910年(明治43年)に旧制第一高等学校に入学し、在学中に無教会主義者の内村鑑三が主催していた聖書研究会に入門を許され、キリスト教への信仰を深めていきました。東大に入学後は、吉野作造の民本主義や、人道主義的な立場から植民政策学を講じていた新渡戸稲造の影響を受け、思想形成を行っていきました。
矢内原は、生涯独立の信仰者(伝道者)として歩いていく決心をしました。矢内原の生涯は3つの側面を持っていました。学者(東大教授)であり、教育者であると共に、クリスチャンの世界では、矢内原は内村鑑三の流れをくむキリスト教の独立伝道者としてよく知られていました。内村はいかなる教会にも属さず、無教会主義を唱え、個人的な聖書研究集会を毎日曜日に開くことと、独自に発行する個人雑誌を通じて一生を伝導に捧げる生涯を送りました。その弟子たちも、師にならって、それぞれ独自の聖書研究を続け、個人雑誌と個人集会を通じて伝道生活を送った人が少なからずいました。そういう活動を通じて、無教会派は日本のキリスト教界で、独自の影響力を今日も持ち続けています。
矢内原の人生は、ここにある「自分の公に言うべきことは言う」ために費されたといってよいでしょう。しかし、満州事変以後、急速に言論の自由が失われつつある日本で、言うべきことを言うのは、そうたやすいことではありませんでした。しかも、矢内原が考えていた「言うべきこと」とは、経済学部における「満州問題」講義でなした程度の遠回しの国家政策批判ではなく、もっとストレートに、満州事変以後の日本の国家政策が、根本的に誤っているとする主張でした。それも単に政策上の誤りを批判するという程度の話ではなく、日本という国家が、神の前に不義とされるような存在になってしまっているということをはっきり糾弾すべしと考えていたのでした。しかし、国家主義が日本全体をおおいつつある当時の世の中において、そこまでいうのは大いなる勇気を必要とすることでした。
この講演会の直前に「理想」という雑誌(昭和8年1月号)に寄稿した、「日本精神の懐古的と前進的」という論文で、矢内原は日本的国家主義について、もっと厳しいことをいっていました。そこでは、国体、天皇神性、国家至上主義の問題という、当時、天皇主義者以外のインテリは誰一人、火傷をすることを恐れて、取り上げようとしなかったテーマに正面から取り組んでいました。問題はキリスト教と国体との根本的関係であります。難解な論文だから、ここで詳しくは論じられませんが、そのエッセンスは、なんといっても、天皇の神性の問題にあります。キリスト教信者である矢内原にとって、天皇の神性をキリスト教の神の神性と同列におくことだけはどうしもできませんでした。天皇に神性ありとしても、それはキリスト教の神の全知全能でかつ宇宙の全てを造った造物主であるという意味での神性とは別の神性であるということを矢内原は論証しようとしました。
まず、天皇中心主義者が、「天皇は宇宙の道義即ち至尊に従わなければならぬ」というとき、天皇とは別なるものとして、「天皇以上、天皇の基礎たる、天皇も亦(また)之(これ)に適順せざるべからざる宇宙の道義の存在することが前提されている」のではないかといいます。その一方、天皇中心主義者たちには、天皇は至尊そのものであるという主張もあるといいます。そうなると、「天皇は至尊たるべしといふのは、天皇の理想であるのか、現実であるのか。天皇の守るべき格率であるのか、天皇が格率そのものであるのか」などと問い詰めていくことによって、「天皇神性の基礎は人格よりも位体に於(おい)て存し、天皇人性の基礎は位体よりも人格に於て存ずる。現実の天皇は国家的位体に於て神性であるので、人格的に至聖至愛全知全能の神性をもつとの謂れ(いわ)ではありません。生活及び人格に於ては凡(すべ)ての人間と同様、造物主に相対して人性を有(も)つものである」という結論に導いていきます。天皇も創造主たる神を前にすると、他のすべての人間と同様人性を持つ存在なのだから、キリスト教の教義と矛盾しないという結論であります。(修正・卒を率に変更・2023/4/27・修正)
また、国家至上主義は、「国家の欲するところ、国家の利益とするところ、之即ち道義であるとの主張を産み出す」ことになってしまうが、「かかる国家主義は理想の国家と現実の国家とを混同」するもので、「結局現実国家の利益が即ち道義であるといふ主張」になってしまうとしました。そして、「斯(か)くの如(ごと)きは極めて浅薄(せんぱく)なる道義観又国家観であって、独りよがりの我儘(わがまま)者の人生観に類するものである。真の愛国心は国家以上に宇宙の公理としての道義を認め、その道議によって自己の現実国家を批判し、道義に反したる点は之を指摘(してき)匡正(きょうせい)して以て道義国家の理想に近づけ、道義の光をその中により放たしめんとするものでなければならない。故に真の愛国心は国家の利益を考へずして、国家の道義を考へる」としました。国家の利益を優先させるな、まず国家の道義を考えることこそ本当の愛国心だ、としたのです。この論文は、この時代を覆っていた天皇中心主義者たちの国体絶対視の論調、国家至上主義万々歳の論調に正面対決して一矢報いた論文として記憶されるべきでしょう。
新聞記者ゾルゲの見方
ゾルゲが新聞記者として来日したのは昭和8年で、逮捕は昭和16年です。ゾルゲは新聞記者として、天皇機関説(昭和10年)も、2・26事件(昭和11年)も、同時代の出来事としてレポートしていました。ゾルゲは、スパイとしても優秀でしたが、新聞記者、社会評論家としてもすぐれた実績を残しました。
レポート「日本の軍部」には、昭和10年の時点での、軍部の政治進出の問題が取り上げられていました。まず、陸軍パンフレット問題(昭和9年)と、天皇機関説問題(昭和10年)を取り上げ、その成り行きから見て、日本では、軍人が政治に関わることが禁じられている(軍人勅論に明記)にもかかわらず、これからは軍部が大きな政治的役割を果たしていくことになりそうだと分析していました。そういう分析の背景として指摘していたのは、日本には政治指導部といえるほどのものがなく、他の政治セクターがみんな弱いということでした。「この重大な情勢下で日本には政治の指導者はいません。すでに多年来政府は、(略)軍部と官僚と財界と政党の諸勢力の混ぜものに過ぎないのであります。以前は強力であった政党も汚職と内部派閥の闘争のため、政治危機的には全く退化し、国民の大多数から軽蔑されています」。
ここにゾルゲが書いたように、軍部の政治力が急に増すのは、5・15事件と満州事変以後であります。軍部は、満州事変を起こし、満州国という人工国家を作ることに成功した後、その国家を思うがままに(軍事的にはもちろん政治的にも経済的にも)を支配し経営していきました(関東軍が、満州国の事実上の独裁的支配者となった)。満州国で軍中心の国家経営のうまみを覚えた軍部は、その成功体験を日本国内でも生かし、軍部による国家支配を実現しようとしていました。その背景には、現代の戦争は戦場における戦闘中心の戦争から、国力の総力(特に経済的生産力)をあげてぶつかり合う総力戦の時代になったという認識があり、日本でも早く総力戦体制(国家総動員体制・高度国防国家)を築き上げるべしという発想がありました。その方向に向けて全国民の精神を統一するための精神統制が欠かせないと主張しました。つまり、「皇国の使命に対する確乎たる信念」を持たせるとともに、個人主義、自由主義を排し、尽忠報国、自己滅却、挙国一致の精神を持たせるということです。
天皇機関説問題はこのような流れの一環として出てきたのだと考えると分かりやすいでしょう。ゾルゲはそのあたりを、この昭和10年の論文で見抜き、その中心にあるのが、「日本主義」に基づく「国家総動員」体制であると指摘していました。その核心にあるのが皇道の理念のおし広げであり、美濃部の天皇機関説問題はそのプロセスで出てきた問題だとして、次のように書いていました。
「『日本主義』思想は核心を包む枠組みに過ぎないものとして理解されなければなりません、この核心は皇道の理念であります。特に近頃は日本の皇道理念の純粋性をめぐる闘争が熱心に行われていますが、今のところ攻撃の対象は主に西洋の公法及び国家哲学的影響に向けられています。今や数十年来一般に認められていた美濃部説が批判され、その著書は禁止されました。美濃部はその業績のため天皇(昭和天皇)自身から尊敬され、強い西洋の影響を受けている明治天皇の憲法を西洋の概念で解釈した人である、と認められています、という内容でした」。 特に美濃部を、「明治天皇の憲法を西洋の概念で解釈した人」としての説明はその通りといってよいでしょう。天皇は美濃部を尊敬しているという話が出てきます。これは事実であり、今はよく知られていることですが、当時は一般には知られていなかったことでした。
天皇の意見
天皇機関説問題で不思議なのは、天皇の意向に何よりも高い価値をおき、いついかなる場合も天皇の意向に従うことを最優先すべしと「承詔必謹(しょうしょうひっきん・必ず謹んで実行するの意)」を解く人々が、天皇機関説に対する天皇の意向をまるで無視していたことであります。天皇は、その意向(「天皇機関説で良いではないか」)を秘めていたわけではなく、様々な人に対して、機会がある度に何度ももらしているのでした。それは、天皇の侍従武官長であった陸軍大将本庄繁の日記『本庄日記』、元老西園寺公望の秘書をしていた原田熊雄の『西園寺公と政局』、首相であった岡田啓介の『岡田啓介回顧録』などによくあらわれています。
例えば、『岡田啓介回顧録』には、次のようにあります。「私は今になって打ち明けるんだが、この問題について、陛下は、どんなお考えであったか、というと、陛下は「天皇は国家の最高機関である。機関説で良いではないか」とおっしゃった。そして困ったことを問題にしておる、というご様子でした。しかし私は、このお言葉を持ち出して機関説を排撃する連中を抑えようとは思いませんでした。かりそめなことをして、累を皇室に及ぼすようなことは慎まねばならない、とそう考えて私の胸におさめておきました」。 『西園寺公と政局』には、鈴木貫太郎侍従長の口を通してという形ではありますが、昭和天皇が美濃部をはっきり評価していることを述べる部分があります。
「甚(はなは)だ畏れ多いことではあるが、陛下はかういふ問題について頗(すこぶ)るよくわかっておいでになつて、侍従長の話では、『これは絶対に秘してあるけれども、陛下は「主権が君主にあるか国家にあるかということを論ずるならばまだ事が判っているけれども、ただ機関説が良いとか悪いとかいう議論をすることはすこぶる無茶な話である。君主主権説は、自分からいへば寧(むし)ろそれよりも国家主権の方が良いと思ふが、一体日本のやうな君国同一の国ならばどうでも良いじゃないか。君主主権はややもすれば専制に陥り易い。(略)美濃部のことをかれこれ言ふけれども、美濃部は決して不忠なものではないと自分は思ふ。今日、美濃部ほどの人が一体何人日本にをるか。ああいふ学者を葬ることは頗る(すこぶ)惜しいもんだ」と仰せられ、なお(本庄繁)侍従武官長に対しては、「一体、陸軍が機関説を悪く言ふのは、頗る(すこぶる)矛盾じゃないか。軍人に対する勅論の中にも、朕は汝等の頭首なるぞ。といふ言葉があるが、頭首と言ひ、また憲法の第四条に、天皇は国の元首にして・・・といふ言葉があるのは、とりもなほさず機関ということであるのだ」といふお話をされた。なほ陛下のお話に、「美濃部のは、多少の行きすぎたところがあるかもしれないけれども、決して悪いとは思わん」といふことをしきりに仰せられてをられた。』
天皇の生言葉は、決して外部に漏らしてはならないことになっていたから、このような話が活字になって外に出たのは全て戦後になってからですが、天皇の気持ちははっきりしており、当時からその気持ちは様々な形で表現されていたから、権力中枢の人には、ある程度伝わっていたはずなのであります。
また陛下は、次のように仰せられました。
『議論を究(きわむ)れば結局、天皇主権説も天皇機関説も帰するところ同一なるが如きも、労働条約其他(そのほか)債権問題の如き国際関係の事柄は、機関説を以(もっ)て説くを便利とするが如(ごと)し云々(うんぬん)と仰せらる。之(これ)に対し軍に於(おい)ては天皇は、現人神と信仰しあり、之を機関説により人間並に扱うが如きは、軍隊教育及び統帥上至難なりと奉答(ほうとう)す』
これは最後の二行がポイントです。天皇が、天皇主権説も天皇機関説も、理論の究極までいけば同じようなものだが、国際関係(債権問題など)の事柄は、機関説を以て説くを便利とす、としているところが注目に値します。これは、天皇が機関説問題のポイントをよくつかんでいたことを示しています。
美濃部が挙げているように、君主主権説で一番問題になるのは、君主が死んだ場合、生前君主の主権を前提としてなされた法的行為の効力が、死後断ち消えとなってしまうのか、それとも、国家に引き継がれるのか、なのであります。実際、天皇は現実政治の上でそういう問題が起こるということ自らの体験で知っていました。それは、ロシア革命(1917・大正6年)によってロシア帝政が終焉した時に、日露戦争後に結ばれたポーツマス条約は、今でも有効かという重大問題でした。日ソ両政府は、北京で大正12年から2年超しの国交回復交渉を行い、大正14年にようやく、日ソ基本条約を結び、ポーツマス条約の完全存続をソ連に認めさせることができたのです。この時、日本がロシアにそれを認めさせるために使った論理は、国家主権説でした(ポーツマス条約は、ニコライⅡ世個人が勝手に結んだ条約ではなく、ロシアという国家の代表者として結んだ条約なのだから、その国家を継承したソビエト新政府は、その条約も丸ごと継承しなければならない)。この時、日本側の当事者として直接この問題を扱ったのは昭和天皇でした。(大正天皇はご病気でありました)
また、満州の奉天で起きた張作霖爆死事件(1928・昭和3年)がありました。この事件は、国際的な大きな注目を浴び、国際連盟から調査団が派遣されため、日本政府としても独自の調査で、関東軍の謀略であることを突きとめました。時の首相田中義一は、ことの概略を天皇に報告し、犯人を厳重処罰することを約束しましたが、軍部とそれをと結んだ一部の政治家が、真相発表や犯人処罰に強く反対したため、田中首相は天皇との約束を守れなくなり、それについて天皇は強く怒り、田中に対して、「それでは前と話が違ふではないか、辞表を出してはどうか」と強い語調でいいました。怒りで内閣を1つ吹っ飛ばしたわけで、天皇の心に大きなトラウマを残しました。以後天皇は、輔弼(ほひつ)の任にある者が、手順を踏んでもってくる話はそのまま受け取り、自分の恣意的(しいてき)な判断によって諾否(だくひ)を決めないようにしたといいます。これを契機に天皇は天皇機関説型の天皇に徹する決心をして、これが正しい立憲君主の在り方と信じていたということです。これが「昭和天皇に戦争責任なし」論の最大の論拠になります。昭和16年の開戦決定にしても、正規の手続きを踏んで自分のところまでは上げられてきた案件を、自分が勝手に拒否することなどということは日本の国制上できなかったというわけです。
また、『本庄日記』に記されていた天皇の発言で、そこで天皇は、自分は肉体的には普通の人間と同じなのだから、 天皇機関説を排撃しようとするあまり、天皇の神格化をどんどん進める形になるのは迷惑だ、つまり人間としてふるまえなくなるということでした。天皇は内輪では、こういう形で、すでに「人間宣言」をしていたのです。
戦後
1945年(昭和20)8月15日は終戦の日で、第二次世界大戦が終結(終戦)した日のことです。1945年8月15日を、私(立花隆)がなぜ重要視するのかというと、この日を境に日本の国が根本的に変わったと思うからです。日本は国体の護持を条件にポツダム宣言を受諾したという建前をとっていますが(日本側の理解。アメリカ側の理解はまた別)、それは形式論であって、日本の国体はあの時点で根本的に変わったのです。
木戸幸一は、昭和天皇の側近の一人として東條英機を内閣総理大臣に推薦するなど、太平洋戦争前後の政治に関与しました。木戸幸一は1951年10月、天皇に「退位」の意を伝えてほしいと宮中関係者に伝言しています。その後も何度か、人を介して、天皇に退位をすすめました。天皇は、その忠言をいれて、退位する意思があったのに、マッカーサーと吉田首相が、政治的マイナス効果が自分たちに降りかかるのを恐れて、それを妨害したとされています。
天皇制の存続については、政府首脳も疑心暗鬼でありましたが、米側から国家の元首は憲法の下で認められた権限内で行動しなければならないとの考えが示されていたことから、米国は天皇という存在を念頭に置きながら発言しているのとの感を深めました。天皇の主権は連合国軍最高司令官の命令下に従属せしめられるべしと規定して、言外に天皇の地位を承認したのであります。ポツダム宣言の受諾以後は、その絶対の天皇の意志が、連合軍最高司令官(マッカーサー)に服従する(subject to)ことになったのだから、ここで日本の国体は根本的に変わったといえるのです。この日以後、連発されるマッカーサーの指令に天皇も日本政府も全面的に従わなければならないことになりました。そして同時に、占領が終結した後の日本国の体制は、自由に表明された日本国民総体の意志によって決定されることになったことは、ポツダム宣言に明記されています。天皇だけが主権者だった国から、国民の総体の意志が主権を持つ「主権在民」の国になったのです。これは日本の国体の根本的な変革です。
昭和21年2月11日の紀元節式典で行われた南原繁のスピーチ
南原繁は、戦後初代の東大総長です。この年の初めに発表された詔書、いわゆる人間宣言によって、天皇は自らの神格を否定しました。天皇をもって現人神(あらひとがみ)とする戦時中の通念を、自ら「架空の観念」と言い切りました。天皇を現人神と信じきっていた人々にとって、この宣言ほどショックを与えたものはないでしょうが、南原はこの人間宣言を持って、日本の宗教改革としました。
その頃、南原総長の演述が1カ月に一度の割合で安田講堂で行われました。とりわけ大きな社会的インパクトを与えた発言を拾ってみれば、まず、昭和21年2月11日の紀元節式典で行われた南原繁のスピーチがあります。
オリジナル・テキストを引用しながら、わかり易くいうならこのようになります。『これまでの紀元節は、日本の政治を支配する軍国主義者と国粋主義者が、日本の民族神話の伝統を「濫用し、曲解し、自己の民族の優越性を誇称し、東亜をひいては世界を支配すべき運命を有するかの如く喧伝」するためのものとしてありました。大東亜戦争のスローガン「八紘一宇(はっこういちう)」は、世界を一つの屋根のもとに置くということですが、天皇を頂点とする世界帯国帝国=大日本帝国を築くことを意味しました。それは一種の選民思想的独断と誇大妄想以外のものではありませんでした。そのような神話的世界認識から、戦争が起され日本を破局に導きました。(2023/5/3・修正)
天皇の「人間宣言」詔書は、そのような「日本神学と神道的教義からの天皇自身の開放、その人間性の独立宣言」でした。それは同時に、日本人と日本文化の開放でもありました。具体的に言うと、それは何からの解放でしょうか。過去を見る目でいえば「日本神学からの解放」ですが、それは同時に、未来に向けては「あらたな『世界性』へ向けての解放」ともいえます。なぜなら、これまでの日本の文化が「民族宗教的」なものに束縛されていましたが、それから脱したことで、これからは広く世界に理解してもらえる普遍的文化となりうる基礎が獲得できたからであります。 戦争の終わりは、一般の日本国民だけでなく、天皇という存在が日本から解放され、世界のための存在になることができるようになったということもできます。結果的に見て、戦争は天皇の解放の為でもあったという解釈ができます。国民は国民たると同時に世界市民として自らを形成し得る根拠を、ほかならぬ詔書による人間宣言で裏づけられたということです。また、法的かつ政治的には、天皇には責任がないことは明白なのですが、それでも天皇には、道徳的、精神的に責任があります。天皇歴代の祖先に対してあり、国民に対してあります。』
令和の時代から象徴天皇を考えてみる
今まで、立花隆の「天皇と東大」(文藝春秋)という上・下巻あわせて1500ページ以上のボリュームのある本を読んできました。内容を紹介するために私(清水)が重要であると思える部分約23ページ分を抜粋してまとめて転記して編集しました。明治維新後の日本の選択肢をたどる行程を書き出してみました。学校の教科書やいろいろな戦争映画などで断片的には見聞きしましたが、流れをまとめて勉強したのは始めてでした。この本にも記載されていましたが、日本の近現代史は私が若いころにもあまり詳しくは学校で取り扱わずスルーしていました。おそらく現在でもあまり詳しい取り扱いはないと思います。
私(清水)の感想ですが、明治維新から時代が150年余も経過した現在からさかのぼって見ると、天皇主権説推進者たちは、もしも国家主権説推進者たちが推す「天皇機関説」にいったん主導権を奪われると、時代の流れから見て、天皇主権説は現実世界において、二度と取り上げられることはなくなる、つまり我々の考えを、この思いを世界に問いかけることができるのは今しかない、この機会を逃すと、日の目を見ることが永遠になくなる、顧みられることがなくなる、それが、たとえ短い間だったとしても、と考えたに違いありません。だから天皇主権説推進者は、何が何でも天皇機関説を排除することに、あらゆる手段を講じて邁進したと思います。つまり、我々の出番は今しかないと、決死の覚悟を持つことができた、と考えられます。天皇主権説を推し進める当事者たちもいわゆるインテリジェンスの高い人々なので、国家主権説という考えを当然理解することはできましたが、排除することを止めることができず、時代に流されて、成すがままに任せるしかなかったのではないでしょうか。時間をかけて、さんざん議論を尽くしたはずですから、その原因をさぐれば、それは1868年の王政復古の大号令にあったと思います。天皇という存在が、明治憲法でシステムに組み込まれた以上、この状況を実体化しなくてはなりません。そう考えると、従来の日本人が持っていた心情を表現した天皇主権説に心を引かれたのでしょう。当時の日本人のありようを世界に示すためには、これがぴったりだと思いました。天皇主権説というものが日本人の琴線にふれたと思います。天皇主権説というのは従来の日本人が持っていた、天皇に対して寄り添いたいという気持ち、慕わしく思うことを表した考え方であると思います。
海行かば 水漬く屍 山行かば 草生す屍 大君の 辺にこそ死なめ 顧みへりみはせじ
「海行かば」という曲をご存知の方も多いと思いますが、この歌に従来の日本人が持っている心情がよく現れていると思います。「海行かば水つく屍・・・」の古歌について一言しておきます。これは、万葉集十八巻の大伴家持(おおとものやかもち)の歌で、天皇のおそばで死ねるなら、その後、海で水漬く屍になろうと、山で草むす屍になろうとかまいはしないという意味です。これは武人の心構えを歌った歌で、おそらく、家持は、武人として山野を渡り歩いた経験から海や山の戦場跡で、死屍累々の光景を見たことがあり、その実感を歌ったのでしょう。
この歌は、天皇機関説問題が、そのまま国体明徴運動に転化して行く過程で、国体観念のシンボル的存在となっていきました。あの時代の日本人にとっては、天皇のために命を捧げることが最高の道徳とされ、そのシンボルとして、この歌があったと思われます。国民精神総動員中央連盟が作られ、神社参拝、勅語奉読、戦没者慰霊、軍人遺家族の慰問、出征兵士・英霊の歓送迎、建国祭、ラジオ体操、国防献金、勤労奉仕などが奨励され、各地で集団的に盛んに行われました。運動の一環として、国民精神強調週間なるものが設定され、各種の行事が行われました。そのテーマ曲として作られた歌が、この大伴家持の歌に信時潔(のぶとききよし)が曲をつけたものでした。戦時中、最大の国民歌謡として、ことあるごとに歌われた「海行かば」でありました。
現代という令和の時代から考えてみると、天皇に対する日本人の心情というのはこのようなものだけではありません。つまり、天皇主権説的な考え方のように無条件に寄り添いたいということだけでは日本人の心持ちが十分に表現できていないと思います。当然戦後になって、憲法も変わり日本国憲法となって、憲法の中での天皇という存在のあり方も変わりました。天皇機関説おきましては明治憲法における天皇機関説の解釈では、天皇は国の最高機関であるという存在でしたが、新憲法では、天皇は「国政に関する権能を全く有さない(第4条)」ということなので、天皇を最高機関とせず、国民主権原理に基づく日本国憲法が成立したことによって、天皇機関説は憲法解釈学説としての使命を終えました。そして天皇は、新たに「日本国の象徴である」として新憲法に組み込まれました。憲法の中で「天皇」という存在の取り扱いは変わりましたが、天皇という存在は引き継ぎました。(2023/5/4・修正)
世界史の中で、ヨーロッパ諸国では廃止した時期に、あらたに王権神授説を採用して明治憲法を作り世界に進出したという、世界でも珍しい歴史的経験をした日本という国は、どのような国であるかということを、どのように諸外国に説明するのか適当なのでしょうか。憲法が新しくなったとはいえ、天皇という名称を持つ存在を引き継いでいる以上、王権神授説的要素が全くなくなったとはいえません。どうすれば「なるほど、そういうことですか」と、日本という国を理解してもらえるのでしょうか。この問題は、現在になってもまだ完了していません。終戦と共に天皇が退位されて、天皇という存在がなくなっているならば、新たに考える必要はないのですが、天皇は日本に存在し続けています。そういう話題はほとんどなく、現在まで休止したままです。
戦後、天皇という存在は日本の新憲法とかかわりがない存在になってしまったのでしょうか。そのようなことはなく、象徴天皇としてしっかり日本国憲法第1条の中に組み込まれています。
象徴天皇制 日本国憲法第1条は、天皇を日本国と日本国民統合の「象徴」と規定する。その地位は、主権者たる日本国民の総意に基づくものとされ、国会の議決する皇室典範に基づき、世襲によって受け継がれる(第2条)。天皇の職務は、国事行為を行うことに限定され(第7条)、内閣の助言と承認を必要とする(第3条)。国政に関する権能を全く有さない(第4条)。
Wikipediaより
象徴天皇は、政治の内容に直接関わることはありません。天皇は日本国憲法の定める国事に関する行為のみを行うとされ、国政に直接関与する権能を有しない、ということです。また、憲法学では「象徴」は法的意味を持つ語ではなく、政治的意味または、社会学的意味しか持ちません。象徴とはあるもののイメージを任意の記号に仮託したものであり、人々が日本国と日本国民統合のシンボルが天皇であると思っている限りにおいて、天皇が象徴として成り立っており、その地位が「国民の総意に基づく」という部分と同じ意味です。
Wikipediaより
戦前においてなぜ、日本は暴走してしまったのでしょうか。当時の世界状況が植民地の獲得合戦のような状態でありました。自国を守り、植民地を獲得して領土を広げるということを考えれば、当時のような政策をとることが考えられたのかもしれませんが、そのようなことをしない選択肢もありました。
日本人が世界に対して敵対的態度をとらず、寄り添おう、寄り添いたいとする気持ちを表すために、キリスト教を使って表現する方法があったのではないでしょうか。別な言い方をすると、世界に共感する力を表現するということもできます。
立花隆の「天皇と東大」に紹介されていましたが、以下のような記述があり、紹介されていました。
日本の大学は、大学という制度そのものが輸入の産物であっただけでなく、そこで教える知識もテクノロジーもそのほとんどすべて(法学、経済学、哲学、文学、歴史学などの文科系学問も含む)が、輸入学問でした。それはいってみれば、明治初期の文明開化のスローガンであった「和魂洋才」のうちの「洋才」の輸入総代理店の趣を持っていました。「和魂」の方は、「洋才」専門の大学のカリキュラムにうまく収まらず、国史と国文学を除くと、事実上ありませんでした。
なぜ、日本という国が世界に共感していくという道をとれなかったかというと、明治以前にはそれを表現する思考が日本にはなかったということになります。この記述によれば、洋魂は拒否したということになります。つまり、キリスト教を禁止したわけではないのですが、キリスト教を全くといっていいほど受け入れなかったということです。私(清水)が思うのですが、イエス・キリストは、科学の何たるかということを教えてくれた人だと思っています。
イエス・キリストに対して人間は責任を負っています。それは、人間は神の子イエス・キリストを十字架につけてしまったゆえの、その責任は、後世の人間が負わなくてはなりません。イエス・キリストを十字架につけてしまった結果、全能の神は、人間に対する神の愛の証としてイエス・キリストを復活させてくださいました。人間は復活されたイエスキリストの招きに従って、自力で未来を切り開いて行かねばならなくなりました。その責任を負っているのは、ユダヤ人だけではありません。全人類といってよいでしょう。科学の出所を正しく理解することが必要です。当時の一般的な日本人は自分の身の回りのことぐらいにしか目がいかなかった、気が回らなかったのです。そのような状況にありながら、一気にまとめて学問を与えてくれたのは、西洋の国々の方々でした。当然、お礼というか、お金(代金)を支払ったとは思いますが、それ以上に価値のある何百年もかかって獲得した科学の知識やそれを応用した技術を得ることができました。実はそのことに対しては、イエス・キリストに対する責任も含まれていたのでした。当時の日本人はそのことに気がつきませんでした。天皇が神として存在している日本の神道や仏教だけでなく、キリスト教の中にも日本人に潜在的に持っていて、共感できる要素が存在しているものが見つけられるはずであると思います。それを見つけて日本人として表現しなくてはなりません。
神道、仏教、または儒教など伝統的な東洋の思想では表現できない潜在的な日本人の思いを、キリスト教を通じて表現できたらよいと思います。そういった思いを、国の象徴である天皇陛下のおかれましては、取り上げていただきたいと思うのです。