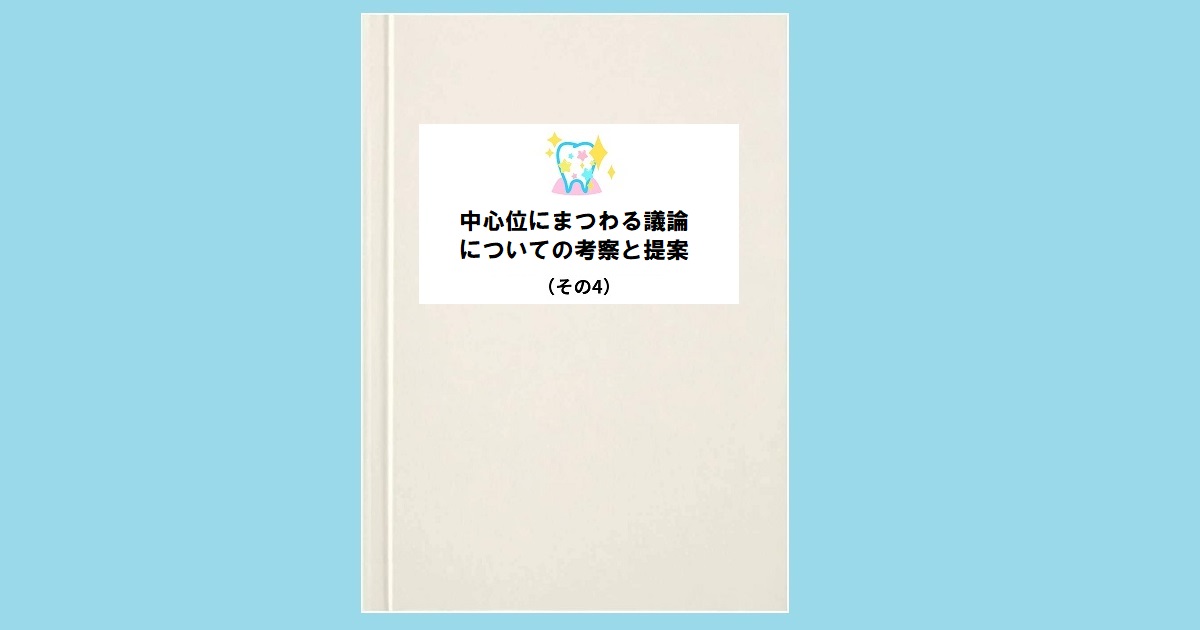SolidworksというCADを使った歯科補綴物の設計について
Solidworksは、「Standard、Professional、Premium」という3つのライセンスのスタイルがあります。機能の内容によって基本的な料金が違います。「汎用CAD」は、機能だけでなく、価格的にも歯科専用CADよりもお得であると思います。製品の仕様は、従来からある永久ライセンスタイプと契約期間中だけ利用できるライセンスタイプがあります。永久ライセンスタイプは、一度購入すると、バージョンアップはできませんが永久にそのバージョンのライセンスを使い続けることができます。バージョンアップするためには、ライセンスとは別にサブスクリプションという、年間保守契約を結ぶ必要があります。永久ライセンスを購入した場合、サブスクリプションは初年度だけは必須です。
契約期間中だけ利用できるライセンスのタイプは、1年間と3カ月間の2つのタイプがあります。この契約期間内にサービスパックの更新やバージョンアップがあれば追加料金なしで利用できます。ライセンス購入の価格は代理店によって多少違っていて、条件やサービスなども違うようです。
なぜ「汎用CAD」推奨するのか、ということですが、それは、「汎用CAD」はサーフェスモデリングとソリッドモデリングの両方に対応した形式だからなのです。また、サードパーティー製のオプションを追加するとサブディビジョン・サーフェスの機能も使うことができます。サブディビジョン・サーフェスの機能とはサーフェス、またはソリッドをポリゴンモデラ―のように、つまり粘土細工のように扱うことができます。このように様々なモデリング形式に対応できるので、ひとつのCADで目的に合わせて使い分けることができます。
現在ではSolidworksとシームレスに連携する、サブディビジョン・サーフェスのモデリング機能が追加され、Solidworks純正の製品で幾何学的ではない形状や複雑なサーフェスを手軽に作成できるようになりました。
専用プラグインの使用について
「Power Surfacing RE v6 for Solidworks」は、Solidworks専用のプラグインです。Solidworksにサブディビジョン・サーフェスを扱う機能を追加します。おかげで、Solidworksを歯科技工に供することができるようになりました。
汎用CADを使用して歯科技工をする場合、少し準備が必要です
「汎用CAD」を使うことの価値は、歯の形状のモデリングだけではありません。下顎運動の研究をすることができ、また咬み合わせの研究も自分独自の方法で行うことができます。複数の下顎の運動の軌跡をCADに取り込めるので、測定や分析する装置をCAD内で自由に作ることができます。
ジルコニア製のフレームによるブリッジの製作方法
ジルコニア製のフルブリッジの製作をデモしました。実際には、このような長いブリッジを製作することはありませんが、製作法を考察するためにデモビデオを作りました。セメントスペースやブリッジのポンティックを作る行程も示しています。また臼歯の補強部の作成も含まれています。
ジルコニア製のフレームによる単冠の作り方
下顎の前歯のフレームの作成を中心に示しています。
セラミッククラウンの作成方法
せっかくコンピュータを使って歯科技工を行うのにもかかわらず、従来のワックスアップの操作を単にコンピュータの操作に置き換えただけではつまらないと思います。やはり、コンピュータを使って歯科技工を行う場合には人工知能による「歯冠形状の回復」が必須であると思います。コンピュータがこのような機能を獲得すると、誰でも簡単にストレスなく業務を行うことができるようになると思います。残念ながら現状ではそれを行うことができません。
インレーの作成方法
上顎大臼歯ケースです。基本の面形状を作ることがかなり面倒です。
ディスクへの埋め込み
フレームの形状を削り出すための操作です。
金属床の作り方
右側第一大臼歯、第二大臼歯欠損のケースです
総義歯の作り方(下顎のみ)
デモは下顎のみになります。既成品の人工歯は仕えないかもしれません。
CATIA と Solidworks を使用シミュレーションの設定
下顎を運動させることができます。
そのための設定を示しています。
咀嚼運動シミュレーション
通常の側方運動ではなく、モノを実際に噛んだ場合、砕かれた食片が頬側や舌側にどのように排出されるか、シミュレーションします。
有限要素法の応用
どこまで有効なのかわかりませんが、有限要素法を適用してみました。
人工知能を歯科技工に応用する
人工知能や機械学習、ディープラーニングを利用することが産業界でさかんに話題になって以来、しばらく経ちます。音声の合成や画像の修復などいろいろな分野ですでに実用化されています。歯科専用のCADにも一部、この技術がすでに使われていると聞きます。私は「汎用CAD」を歯科分野で使うことを推奨してきましたが、残念ながら希望するような人工知能の機能が組み込まれた「汎用CAD」は現在では、まだ存在しておりません。
私の考える最終的な目的は、歯科医師がCADで自ら補綴物を設計していただけるようになったり、臨床の場において、歯科医師による直接的な歯冠形状の研究に供することができるようになったりすることです。このような状況になるためには、人工知能による歯冠形状の自動生成機能の獲得が必須です。CADの操作が煩雑である場合、歯科医師は、やはりこういうことは歯科技工士さんにやってもらおう、ということになってしまうと思います。せっかく簡単に精度よく誰にでもできるようにと歯科技工を「汎用CAD」に移植してきましたが、やはり個別の歯冠形状の「生成・編集」の課題は残ってしまいました。
単冠や3ユニットのブリッジ程度ならば、あらかじめ作っておいた基本的な歯冠形状を読み込んで手作業で個別に編集してもそれほど負担になりません。しかし上顎と下顎からなるフルブリッジで28本の歯を個別に手作業で編集するのは大変な作業になると思います。歯科医師が診療の片手間に行うなどということはできません。「下顎運動を伴う歯冠形状の自動生成」の技術は長年の夢でした。歯科技工を「汎用CAD」に移植してきた最大の理由は、歯冠形状の自動生成と形状の編集操作を結びつけるためであったといえるでしょう。
それでは、どのようにして歯冠形状の自動生成を実現したらよいのでしょうか。人工知能の機能を使うことになると思いますが、現時点においては具体的にどうすればよいのか分かりません。ディープラーニングの分野では、「Python」を使う例が多くの参考書によく登場しますが、2次元の画像認識での使用例が多いようです。
今回の例のように3次元形状を作成する場合でも、「点群」を操作するような特別なライブラリー、例えば、3Dを対象にした機械学習を行う場合には、PyTorch3Dが役に立つようです。しかし、現時点においてはそれほど普及していませんし、一般人が入手できる適切なマニュアルも存在しません。
Googleトレンドでも、「PyTorch3D」のデータが収集できないレベルです。現在ではほとんど検索されていないようですが、3Dは近い将来必ず普及する分野といえます。Googleトレンドとは、Googleにおける検索の動向をチェックできるツールのことで、Google社が提供しているキーワードの検索回数の推移が分かるツールのことです。
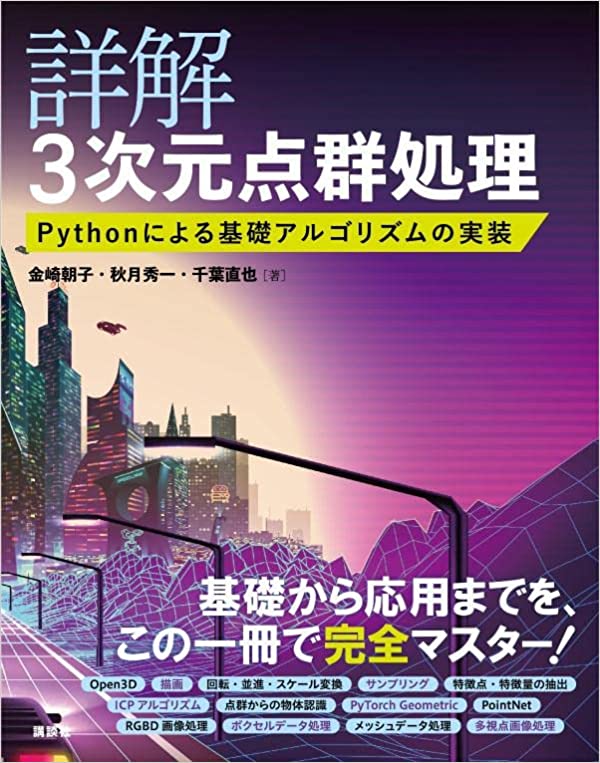
最近このような本が出版されました。「詳解 3次元点群処理 Pythonによる基礎アルゴリズムの実装 ・出版社・KS理工学専門書・2022_10_5」という本が出版されました。3次元の形状修復が実現できる日も、徐々に来るのではないかと思います。