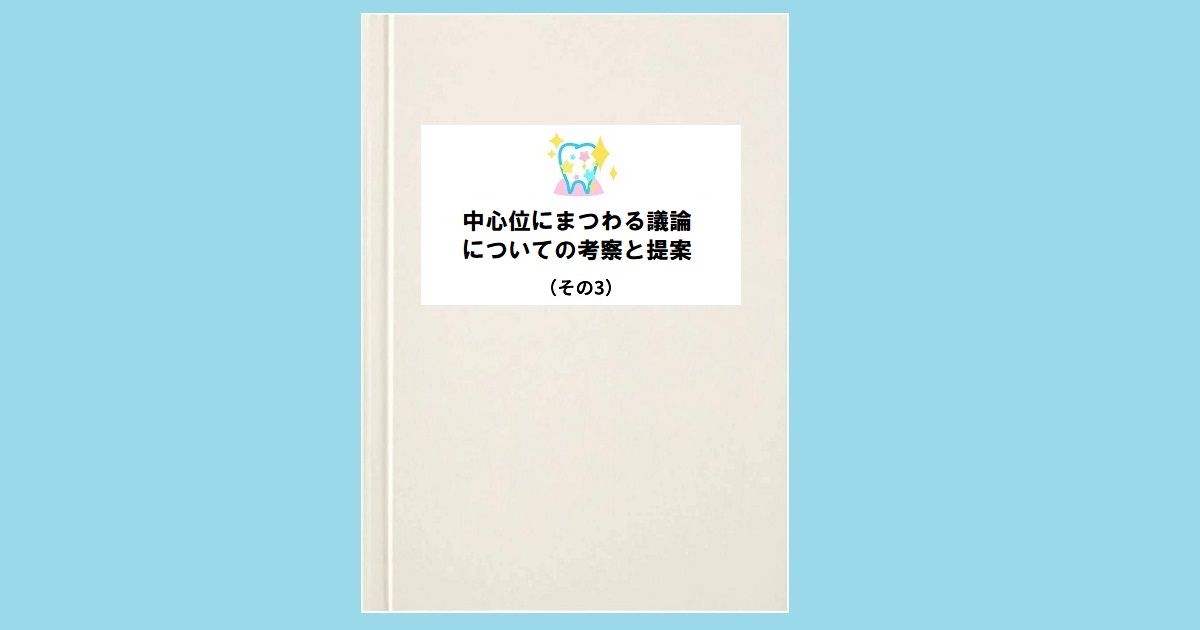存在論と認識論が由来の二つの測定法と再現方法
存在論からの測定法と再現方法とは、いわゆる従来のパントグラフ法です。存在論的な下顎の運動について考察してみます。
下顎が開口するとき、左右の顆頭間軸を貫く軸付近で回転運動を始めます。さらに大きく開口すると、回転しながら左右の下顎頭がほぼ均等に前下方に滑走します。
次に左右の側方運動について考察してみます。右方向の側方運動をするとき、右の顆頭が下顎窩内でわずかに外側移動を伴う回転をします。それに対して左の顆頭は前下内方に滑走します。左方向の側方運動をするときはこれとは逆の運動をします。
下顎運動の決定要素が支配する考察方法です。前方の決定要素について、接触運動のときはアンテリア・ガイダンスです。開口運動のときは前方の決定要素がありません。
これらの表現は生体の仕組みに由来する存在論的な下顎の運動の解釈です。これに異論を唱える人はいないでしょう。だからこそ、従来の測定方法ではパントグラフなどの器具を使って皮膚の下の顆頭の位置を探り顆頭間軸を求めました。また左や右の側方運動時における作業側や非作業側の顆頭の移動や回転を調べました。これらの測定行為はまさしく「存在論に由来の考察方法」といえるでしょう。
一方、私が提案する仮想運動軸法という下顎の運動の測定と再現に関する方法は、生体の下顎運動の仕組みである左右の顆頭やアンテリア・ガイダンスに由来しない方法です。
仮想運動軸法は何に依存するでしょうか。それは下顎運動の測定方法に依存します。下顎骨は剛体と考えることができます。しかし下顎骨は筋肉や皮膚といった軟組織に覆われていて、外側からでは簡単に正確に下顎頭の位置を見つけることができません。
下顎骨には皮膚の外部に露出する歯列が接続しています。この歯列と下顎骨は歯根膜によって強固に一体となっています。したがってこれらは一つの剛体であると考えることができます。
つまり、下顎の歯列の運動を計測することは、下顎の運動を計測することになります。この測定方法は個人によって変わる顆頭間距離に依存することがありません。まさにそれは認識論的な測定方法といえるでしょう。
下顎骨と歯根膜によって強固に連結されている下顎の歯列に3点を付与することによって下顎の正確な運動経路を取得することができます。この3点は直接歯列上に設定しなくてもよいのです。本例のように3点がついたプローブを歯列とリジッドに連結すればよいのです。
下顎の運動経路を知るには3次元空間の中での3点の変位を数学的な処理をしなければ知ることはできません。下顎頭のように下顎骨の特定する位置の運動経路を知りたい場合は、MRIの3次元画像が必要です。つまりこれら2つの測定方法は相補性であり、下顎の運動全体を知るためには両方の情報が必要です。
取得したデータを咬合器で使うためには、フェイスボウ・トランスファーと3点の運動経路で十分です。MRIの3次元画像は必要ありません。
仮想運動軸法は、歯列につけられた3つの座標点を計測します。つまり下顎運動を3次元空間で数学的な表現方法で表す必要があります。厳密に顆頭の位置を特定しなくてもよい場合、フェイスボウ・トランスファーをするだけで咬合器の回転軸が生体の顆頭間軸になります。
下顎骨のMRIの3次元画像データを歯列に重ねると正確な顆頭の運動を見ることができるようになります。これらの方法を極めて簡単に実現できるのが、「汎用CAD」です。
生体は人間が作った機械とは少し違う運動様式を持っています。生体の運動はロボットのような幾何学的な運動とは違い、揺らぎをもっています。その微妙な運動を正確に抽出してCAD上で復元すると詳細な下顎骨の動きを何度でも見ることができます。
任意の3点の計測において、左右の顆頭と前方基準点は下顎運動の決定要素であるので発振部と喩えることができます。任意の3点は下顎全体の位置と運動経路の送信部になります。カメラは歯列の移動と下顎の姿勢の変化をとらえるので、カメラなどのセンサーは受信部です。
CAD内でMRI画像を重ねると顆頭の位置を復元できます。咬合器にデータをトランスファーするにはフェイスボウ・トランスファーをすれば充分です。CAD内で下顎の運動経路を知ることだけが目的ならば、フェイスボウ・トランスファーも必要ありません。測定法由来の方法なので、このようなことが可能です。
オートポイエーシスで語る、新しいナソロジーを探します
私が考える新しいナソロジーは、現実世界を理想世界に変換することから始まります。歯科補綴物作成の技術の発展は、歯科補綴物作成のための間接的な環境を得るためのものでした。加えて、歯の並び方などに関する規範のようなものを探す歴史であったともいえるでしょう。具体的にこの規範とは、フェイスボウ・トランスファーされて上下の歯列模型が装着された咬合器と、顔にある各基準点との関係や歯の並び方のルールのようなもののことです。複雑なものから簡単なものまでいろいろありました。例えば、歯科補綴物作成のための理想的環境として、「咬合器」があります。口腔内で直接的に歯科補綴物を作るわけにはいかないので、作製のための間接的な環境が必要です。また、「Bonwillの三角」や「スピーの彎曲」、「モンソンの球面説」などは歯の並び方などに様々な指針を与えてくれます。
最近私は最初にナソロジーを考案したナソロジストたちは、中心位をどのように解釈するかを世界の人々に問いかけたのではないかと考えるようになりました。私はその問いかけに対して、「仮想運動軸」と「デカルト座標系」を使う方法を提案します。現在では、CADで代表されるようにコンピュータ技術が発達しています。コンピュータ技術を使うと歯科医師が望めば下顎の運動経路をいくつでも取得できます。また咬合に直接関係のない下顎の開閉運動についても運動経路に追加することもできます。このように従来のような実体の「咬合器」に理想環境を求めるのではなく、CADという新しいアイテムを利用することによって、柔軟な環境で下顎の運動を考察することができると思います。
わたくしの意見ですが、ナソロジーに出てくる用語の「ターミナル・ヒンジアキシス」(終末蝶番軸)や「中心位」という位置は、実はこの世のものではなくて、歯科における理想世界、つまり形而上学的な物語の中心アイテムではないか?ということです。つまり、現実世界の物語ではないということです。理想世界と現実世界にはギャップがあります。簡単には理想世界の存在物が現実世界に現すことはできません。何らかの手続きが必要です。
ナソロジーが発表されてからかなり時間が経ちますが、その間に中心位の定義が何度も変更されました。それだけ定義することが難しいことだと思います。その難しさの原因は、理想世界と現実世界のギャップにあると思います。このギャップがいつまでたっても解消されていないような気がします。現実世界では、必然性と偶然性が相互浸透していて、中心位に適用される下顎の顆頭間軸における回転運動、つまりヒンジアキシスのみの純粋なる回転運動だけを確認することがとても難しいことが原因ひとつです。
患者自身が、どれほど下顎の移動を伴わないように開閉運動だけをするように心がけても、また、歯科医師が細心の注意を払って誘導して、純粋に開閉運動だけをさせようとしても、これを行うことは容易ではありません。このことは、歴史的に多くの歯科医師が経験してきたことだと思います。しかし絶対にできないというわけではありません。
下顎頭が完全なる球形かつ、下顎骨が左右対称形ならば、回転軸は一つしかないかもしれません。しかし、人間の下顎頭は完全な球形ではなく、また下顎の骨は完全に左右対称ではありません。更にいえば、下顎頭の周囲には骨だけでなく、いろいろな緩衝するための組織が介在しているがゆえに、もしかしたら回転軸が2つあるかもしれないし、もっと複数個所存在するかもしれません。それどころかエリアとして存在しているかもしれません。そういうことになると、回転軸が無数に存在する可能性があることになります。これは、あくまで考察しただけのことであって、よく調査しないと実態はよくわかりません。
ここで、ターミナル・ヒンジアキシス(終末蝶番軸)と中心位の関係を考えてみましょう。「歯界展望」の2022年7月号に特集されている、「中心位を再考する(理論編)」より引用させていただきましたが、以下のような定義と理解できます。
ここで、ターミナル・ヒンジアキシス(終末蝶番軸)と中心位の関係を考えてみましょう。「歯界展望」の2022年7月号に特集されている、「中心位を再考する(理論編)」より引用させていただきましたが、以下のような定義と理解できます。
ここで再度ターミナル・ヒンジアキシス(終末蝶番軸)や中心位の定義を考えてみます。最初に終末蝶番軸とは、1ミクロンのブレも許さず、純粋な回転軸なのか、それともいくらかのブレを許容するのか、この当たりが問題です。現在、終末蝶番軸というものが厳密に決められているわけではないようです。そのあたりの最新事情は、歯科の業界紙である「歯界展望」の2022年7月号に特集されていて、「中心位を再考する(理論編)」という記事が記載されています。杉田龍士郎という歯科医師が記述しています。この記事によると、中心位での回転軸は、形而上学的な定義によるような、「1ミクロンたりともブレも許さず」ということではなく、「目視で観察してブレなければよい」という表現でした。
デカルト座標系に、終末蝶番軸を伴う中心位をお迎えすることについて
歯科医師が考えている「中心位での回転軸」とは、理想世界のものではなく、実用的な意味での現実世界における定義のようです。現実世界では行為に対して必然性と偶然性が不可分で、相互浸透しているために純粋な回転運動のみを抽出することが難しいのです。コンピュータを使ったCADの理想世界では、各種の下顎の開閉運動からその運動を分析して回転成分と移動成分とに分けることができます。コンピュータを使ったCADでは、デカルト座標系を採用しており、運動データを取り込んで解析すると、そのことがよくわかると思います。
開口運動のとき、初期の純粋な下顎の顆頭間軸の回転運動、つまりヒンジアキシスのみの初期の回転運動が可能なのか、否かを探ることを可能にします。また、複数存在する可能性などもわかると思います。開閉運動のパスはいくつでも採得することができ、更に側方運動などもいくつでも追加することができます。
3次元デカルト座標系をロボットなどの人工物の運動の解析に適用することは、容易に実現できます。しかし生物の運動を精密に解析するには複雑な回転運動と平行移動が絡み合っているために厳密に再現することは困難な作業です。中心位を解析するためにコンピュータを使ったCADの理想世界である3次元デカルト座標系に導入すると、いろいろな解析や検証をすることができると思います。
CAD上では3次元デカルト座標系では簡単に座標変換をすることができます。身体上で下顎の運動を測定する位置と咬合器の駆動部の位置が違っていても測定位置の座標データを咬合器の駆動部の座標データに座標変換することができます。座標変換をすることで従来通りの咬合器上での下顎模型の運動を再現することができます。また運動方程式を導入することで、CAD上で下顎の位置と時間の関係式が作られるので下顎の位置を時間で管理することができます。
そのための手続きとして、歯科領域にオートポイエーシス理論で詳細を示した、ダイナミカル・システム理論を導入するとよいと思います。 ナソロジーの歴史の中で、「1921年 McCollumは、ヒンジアキシス・ロケーターを考案し、ターミナル・ヒンジアキシス(終末蝶番軸)の存在を実証した」とあります。ただし、これはあくまで目視レベルでの話でしょう。どの歯科医師が下顎を誘導してもミクロンレベルでは必ずブレが存在すると思います。現実世界において、再現可能な純粋な終末蝶番軸を見つけることは容易ではないと思います。
咬合器のセントリックラッチを作動させると咬合器の下顎部はブレのない純粋な回転運動のみを行うことができます。これと同様なことを現実世界で下顎の運動をさせることはできないと思います。歯科医師が手で拘束を加えても相当難しいと思います。現実世界では「運動の6自由度」がすべて、または複数の要素が身体によって複雑に結びつけています。3次元デカルト座標系を用いた理想世界では、複雑に組み合わされた「運動の6自由度」の下顎の運動を分解して各成分を表示させることもできます。
仮想運動軸法について
なぜ、生体のヒンジアキシスと咬合器の回転軸を一致させる必要があるのでしょうか。必要があるというよりは、従来の下顎の運動の測定方法に由来していると思います。咬合器に設定してある下顎を開口するための軸は生体の顎に準じた位置に設定しなければなかったと思われます。歯科の業界紙である「歯界展望」の2022年7月号に特集されていて、「中心位を再考する(理論編)」という記事にも以下のように記載されています。
「ターミナル・ヒンジアキシスこそがナソロジーの中心教義です。すなわち、ターミナル・ヒンジアキシスを同定し、それを咬合器の開閉軸と一致させることで、患者の開閉口運動を咬合器上に再現することこそがナソロジーの至上命題でありました。これが正確に行われれば、咬合器上で咬合高径を変更して製作した歯科補綴物が、患者の口腔内に最小限の調整で装着できるため、臨床上のメリットは計り知れません。」
このようにナソロジーの目的が記されています。事実として、多くの人の終末蝶番軸と中心位の関係は、中心咬合位のとき、中心位と終末蝶番軸が一致する人は少ないようです。これらがずれているからといって、顎関節症になるとか、なり易いということもないようです。上記の記載中には歯科医師の操作上のメリットはありますが、ナソロジーの目的が健康上にある理由ということはなさそうです。やはり、ナソロジーは生体機械論という原理主義に則った構造主義由来の概念であると考えられます。
※構造主義とは、20世紀の現代思想のひとつです。広義には、現代思想から拡張されて、あらゆる現象に対して、その現象に潜在する構造を抽出し、その構造によって現象を理解し、場合によっては制御するための方法論を指す語です。Wikipediaより
治療とは関係がない歯がたくさんある場合、咬合の基準は中心咬合位です。通常、歯科補綴物の歯の形状は前歯も臼歯もこの位置を基準にして形成します。現実世界において本当に生体の中心位と咬合器の回転軸を一致させることができると、咬合器上で自由に中心咬合位を決めることができます。つまり咬合高径を変えることができるということです。咬合器のインサイザルピンを調整するだけで実行できます。ただこれを実際に活用できるのは、上下の歯列全部わたって歯科補綴物を作成するときだけです。咬合面をセラミックで製作するときなどは便利な方法です。
私の考えですが、現実世界において、生体には下顎の純粋な回転軸は存在しない可能性が高いと思います。たとえ、1ミクロンでもぶれるのであればそれは下顎の純粋な回転軸ではありません。下顎の純粋な回転軸は、理想世界においては確実に存在します。理想世界と現実世界にはギャップがあり、簡単には重なりません。ギャップを解消すること、もしくは両者の橋渡しが必要です。理想世界と現実世界をつなぐためには、どのようにすればよいのでしょうか。
1つのアイデアとして仮想運動軸法を紹介します。仮想運動軸法とは、どのようなものでしょうか。言葉で表現するとこのようになるでしょう。上顎の歯列模型を咬合器に装着したとき、その咬合器の顆頭間軸が自動的に下顎の歯列模型の運動軸になります。上顎の歯列模型をフェイスボウ・トランスファーによって咬合器に装着すれば、生体の平均的な位置に下顎の顆頭間軸が設定されます。目分量で行えば、それなりの位置に設定されます。これが仮想運動軸法です。
生体の下顎の開閉運動と咬合器の開閉運動は違います。たとえ、違っていても問題はないと思っています。歯科補綴物をつくるとき、単純な開閉運動における軸の位置の違いが歯の形状に及ぼす影響はなく、作業上問題になることはありません。仮想運動軸法を採用するのは、現実世界ではターミナル・ヒンジアキシス(終末蝶番軸)を伴う中心位という位置で純粋に回転する軸を見つけることは非常に難しいという考えからなのです。また中心咬合位だけを問題にしているケースでは、軸の一致は関係ありませんので、仮想運動軸法で十分です。終末蝶番軸は、理想世界では存在していると思っています。ただ、その位置を現実世界に出現させる方法が見つかっていないだけだと思います。
仮想運動軸法では、患者が下顎を開閉運動させた時、その時の回転軸の移動量を測定していません。また、それを再現する方法もとっていません。したがって、咬合器のインサイザルピンを調整して咬合高径を変化させると必ず誤差が出てしまいます。咬合高径を変化させる、つまり、中心咬合位を変化させる必要があるときは、生体上で確認用のマッシュバイトを採得する必要があります。咬合器にマッシュバイトを使って下顎模型を再装着しなくてはなりません。
本当の下顎の開閉運動の軸を知りたいときは、CAD上にある咬合器に上下の歯列模型が装着された環境に下顎骨のMRIの立体像を読み込む必要があります。下顎骨のMRIの3次元像を読み込んで下顎模型に重ね合わせると、生体の左右の顆頭部が表示されます。おそらく咬合器の顆頭間軸とは少しずれていると思います。計測したデータを使って下顎を運動させると、CAD上で下顎のMRIの立体像の顆頭部がどのように運動するか見ることができます。
歯科医師たちは従来の方法で下顎の運動を計測してきたので、下顎頭が3次元的に運動する動画をおそらく見たことがないのではないでしょうか。従来の方法は下顎頭の3次元的な運動は2次元平面に投影した軌跡に基づいて運動を判断する方法です。また実体の咬合器上では下顎の開閉運動を再現することはできません。
理想世界について
理想世界に「ターミナル・ヒンジアキシス(終末蝶番軸)を伴う中心位」をお招きしましょう。理想世界には誤差が存在しません。ミクロンのレベルのおいても回転軸のブレは0です。理想世界では「剛体の運動の6自由度」を個別に駆動させることもできます。また移動と回転の要素を複数組み合わせて運動させることもできます。また理想世界では時間を順方向に進むことも、逆方向に進むこともできます。物体と物体は重なることも、接触することも離れることも可能で、ぶつかることもできるし、すり抜けることもできます。理想世界とは、例えばセオリーや物理学などの数学で記述された世界もそれに相当するのかもしれません。
理想世界には誤差がなく、現実世界には誤差があります。この誤差とは、偶然性と必然性の影響で思わぬところで、寸法的な違いが出ることを指します。理想世界でも、設定いかんによっては、数学的に小数点以下の設定の桁数が非常に多くなる場合があります。
また、理想世界では要素が個別に存在できるのに対して、現実世界では複数の要素が結びついて存在しています。これは相互浸透の考え方から生じることです。簡単には人間が分けることができません。したがって、現実世界と理想世界の間にはインターフェイスが必要で、理想世界と現実世界を直接的に重ねたり連結しようとしたりしてもうまくいかないと思います。現実世界から理想世界にアクセスするためには、誤差の解決と現実世界からの理想世界の解釈が必要です。
実際に下顎の測定の操作をするのは歯科医師です。歯科医師や歯科技工士はCADなどの操作を行いますが、日常の業務で行える範囲の操作方法でなくてはなりません。あまりに高価な機材や操作に手間や時間がかかるものは実用上受け入れられません。
理想パーツについて
間接的に表現する下顎運動のための構成関連要素はCAD内で「理想パーツ」として製作します。たとえば、理想世界の左右の顆頭間軸の長さは万人共通で、110mmです。従来の方法では顆頭間距離を変える必要がありました。また、理想世界における下顎の左右の顆頭の形状は完全な球形で、位置的には正中矢状面と完全な左右対称です。回転軸は1つしかありません。なぜこのようなことを考えるかという理由ですが、下顎というよりも歯列の運動を正確に再現するということに焦点を当てました。これらは3次元デカルト座標系における「座標変換」をすることで可能になりました。
フェイスボウ・トランスファーをしないで上顎の歯列模型を咬合器に装着すると、上顎の歯列模型は咬合器の基準面からずれて装着されます。その場合でも仮想運動軸法では下顎の運動データには誤差を生じません。ただ生体の基準面と咬合器に設定された基準面との間に誤差が生じているだけです。またフェイスボウ・トランスファーしない場合、側方顆路角、矢状顆路角や切歯路角が平均的な値から外れる可能性があります。
仮想運動軸法では、左右の顆頭間軸の長さは110mmで固定されています。男女の差もなく、年齢も関係なく、民族も関係ありません。すべてにおいて一定です。何らかの理由で本当の左右の顆頭部の運動を知りたいときは、下顎歯列と生体の左右の顆頭部の位置関係をCAD上で示すことで可能となります。左右の顆頭間軸の長さが110mmというのは、現在生体と同等な大きさの咬合器で採用されている長さです。3次元デカルト座標系における「座標変換」という技術は、このようなことを可能にします。
咬合器の左右の顆頭部は、咬合器の下顎部分の運動を操作するときの基準になります。生体では個人によって左右の顆頭間の軸の長さが違います。また生体の顆頭部の3次元的な位置関係は正中面を中心とした完全な左右対称ではありません。この仮想運動軸法で重要視しているのは、上顎の歯列に対する下顎の歯列の三次元的な位置の変化です。
下顎の歯列の3次元的な位置の変化は、「口唇前の測定法」で収集します。このデータを使ってCAD内の咬合器上で、下顎模型の位置の変位の再現をします。口唇前で採得したデータを左右の顆頭間軸の長さが110mmという仮想運動軸の顆頭球とインサイザルピンの先端の運動に変換します。生体に存在している左右の下顎頭の特定の位置の運動経路の再現ではありません。
測定のためのレベルの高いプロビジョナル・レストレーションについて
歯の本数が多い歯科補綴物を製作する場合、上顎の歯列と下顎の歯列位置関係の測定のための精密なプロビジョナル・レストレーションが必要でしょう。その前歯郡の部分は解剖学的形態を有していて、正確なアンテリアルガイダンスが付与されています。また臼歯部は咬合高径を確保し、中心咬合位を確実に保持、再現させます。臼歯部も解剖学的形態があるとさらに良いと思います。それは生体と歯列模型の間をインターフェイスします。3Dプリンタの利用が考えられます。
理想世界でできることとは何ですか?
偶然性と必然性というカテゴリーからの発想がありますが、突然何かに妨げられたり、また何かに導かれたり、このようなことは現実世界のみを見つめる人たちの間で通用するお話でした。このように現実世界だけに固執すると、未来に関しては確定できることは何もありません。いつでも不安がつきまといます。
また、「理想世界」という言葉がありますが、これは都合の良い世界ということではありません。理想世界では未来に関しては、すでに確定しており、偶然性と必然性からの発想からもたらされる未来のようなことはありません。なぜなら、理想世界では過去も未来もなにもかも、すべてお見通しなのです。陰に隠れても見つかってしまいます。あらゆるものが丸見えなのです。まるで、旧約聖書の創世記のアダムとエバの世界のようです。
しかし人間には理想世界のことがすべて明かされているわけではありません。また人間も努力はしていますが、まだ十分には理想世界にアクセスできていないということです。偶然性と必然性というカテゴリーからの発想では、属する世界が違うので理想世界を記述することも、説明することもできませんし、もちろんアクセスすることもできません。このようなわけで、偶然性と必然性というカテゴリーからの発想からでは、理想世界に対して交流することができません。
理想世界にアクセスするためには、唯一性と多様性からの発想が必要です。唯一性と多様性からの発想では、多くの可能性の中から一つの現実に収束する、と考えます。理想世界にはあらゆる可能性がありますが、すべてが現実世界において実現できるわけではありません。整合性の問題があるからだと思います。理想世界は現実世界の上位概念であり、理想世界と現実世界を共有することで現実世界を理想世界に近づけることができます。理想世界は、現実世界からみると、抽象的な世界を取り扱うことと言い換えることができるかもしれません。
理想世界と現実世界のつながりを説明する、または、表現する手段として対称性という言葉があります。対称性は、扱う学問的な領域によって意味合いが少し違います。一般的には、対称性とは対称変換のように、見た目を変えない操作のことを示します。また、物理学における対称性とは、物理系の持つ対称性、すなわち、ある特定の変換の下での、系の様相の不変性である、ということです。数学では、ガロア理論のように方程式が解けるかどうかという問題や群論の行使によって明らかになる代数的構造の構成的方法の表現などがあります。
対称性とは、「動かしても見た目が変わらない」という性質のことです。ですから、「動き」や「変化」とは裏腹の関係です。このような性質を利用して咬合面間の空間の変化の解析ができるのではないかと思います。上顎と下顎の臼歯の咬合面の近接関係の研究や咀嚼のメカニズムは、今まであまり研究の対象になっていない、またされたことがないと思います。咬合面間の空間の変化、それを解くカギが対称性であると思います。上顎と下顎の臼歯の咬合面の形状は変わっても、変わらないのは中心咬合位の時の咬合高径です。咬合面をどのような形状にすればよく噛むことができるのでしょか。また歯根への負荷を考えた場合、生理的に合理性のある咬合面の形など、研究する要素はいくつでも探すことができます。
どんなに立派な歯でも対合歯を考慮しなくては機能について語ることはできません。つまり臼歯の咬合面の形状の分析は、対合歯を考慮にいれなくしては意味がありません。機能するということは下顎が運動することに大きく関与します。それは、上下顎の臼歯咬合面の近接関係を分析することであり、言い方をかえると咬合面の形状を対称性という観点から見てみるということになるのです。要約すると、私は歯の咬合面そのものを研究することよりも、今度はそれらが作り出す空間の変化を研究するということが新しい機能の発見につながると思います。
確かに臼歯の咬合面の凹凸は、対合歯の凸凹と呼応して存在しているのだけれども、一体どうしてこのような形状になっているのでしょうか。なにがどのように役に立っているのかわからないもの、それが咬合面の形状です。ただ闇雲に凸凹しているのではないとは思いますが、理由はよくわかりません。もちろん、それは対合歯の存在と下顎の運動を前提として形作られていると思います。
歯科において対称性とは、対合歯との咬合面間の空間の変化のしくみを研究することであると思います。有限要素法や流体解析の利用が重要です。対称性とは、自然世界の仕組みであり、それは構造とエネルギーからできています。対称性を利用すると、物事の一部分、もしくは半分から、関連性などを元にして全体を知ることができます。物事を抽象化や理想化、数学モデルを使うことで、今までにない奥行と広がりを出すことができるでしょう。人間は現実世界から抽象的世界を抽出しましたが、実は理想世界の方が現実世界よりも先行していて、現実世界は抽象的世界が結実してできたと私は思います。
歯科技工に興味がある歯科医の先生方へ
ナソロジーが衰退した理由として、時代の流れとともに歯科技工が歯科技工士に移譲されてしまったことにあると思います。歯科技工が歯科医師とのかかわりが少なくなってしまいました。歯科補綴物を十分に、また、自由に設計するには治療に対する100%の裁量権が必要です。ナソロジーを受け入れて実践している歯科医師の先生方には、歯科技工に対して並々ならぬ関心があると思います。それは歯科の歴史を紐解けば一目瞭然でしょう。咬合器という生体の擬似的な理想的環境の構築の歴史は、理想的な歯科補綴物製作のためという目的があったからであり、歯科技工というものにも歯科医師が積極的にかかわるべきものであるという認識が大きいと思います。現在、人工知能の活用も本格的に可能になる時代を迎えました。自分で歯科補綴物を設計してみたいと思われる歯科医師の先生方も多いと思います。人工知能の力を借りて歯科医師の手に「歯科補綴物の設計」をすることを取り戻していただきたいと思います。