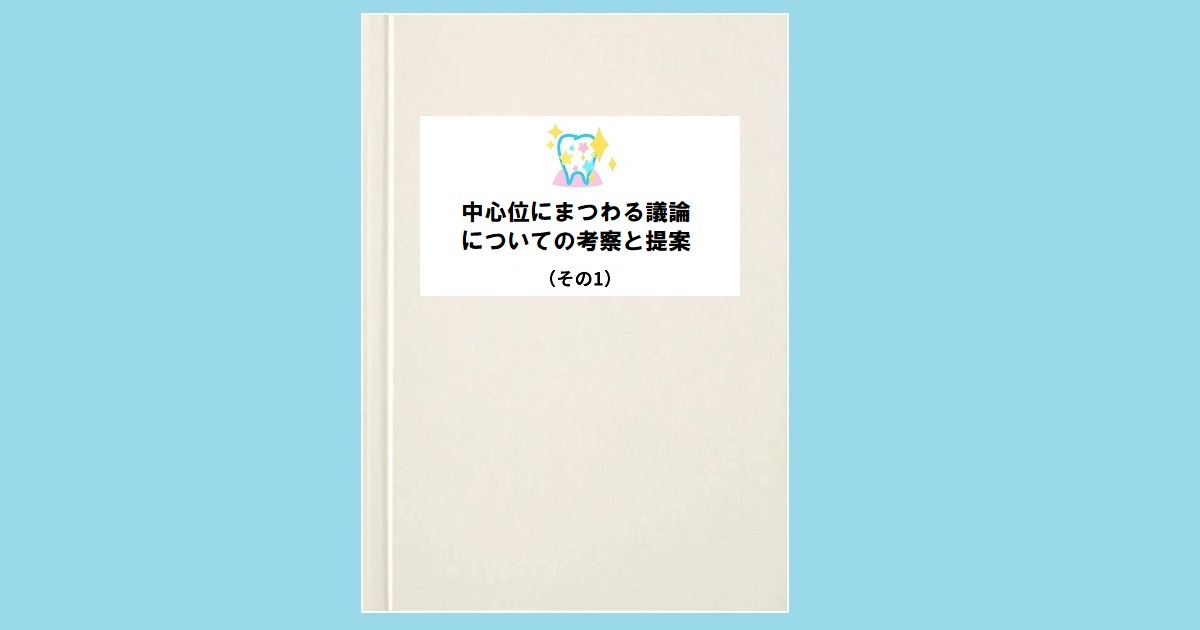ご注意ください
以下の文章の表現方法に、何か違和感を覚えるかも知れませんが、それは科学になる一歩手前の表現だからです。
2023年10月20日に「人工知能がアシストするCADを使えるような日を迎えるために、いかにすべきかを考察する(修正版・Ver.2)」に更新しました。
- 中心咬合位をどこにするのか、また中心位に関することのような、歯科医師でなくては語ることができないと思われることに歯科技工士が言及できるのでしょうか。
- ダイナミカル・システムの構成要素である、オートポイエーシスとはなんですか?
- 複雑系とは何でしょうか?
- オートポイエーシスと歯科技工にはどんな関係があるのでしょう?
- コンティンジェンシー(contingency)と、ダブル・コンティンジェンシー(double contingency)という言葉は分かりにくい言葉です。他の言葉で表現できませんか?
- そもそも社会システムとは何ですか?
- オートポイエーシスの「構造的カップリング」について
- 必然性と偶然性について
- 唯一性と多様性について
- 社会科学の重要性について
中心咬合位をどこにするのか、また中心位に関することのような、歯科医師でなくては語ることができないと思われることに歯科技工士が言及できるのでしょうか。
私は生体を操作するとき、それらに関する専門分野の問題には歯科医師が担当すべきだと思います。また、診療や診断に関しない要件をCADで操作するとき、歯科技工士の考えで設定の選択について歯科医師に要求することは、ある程度の範囲でできると思います。
CADを使って補綴物を作成するとき、このシステムについて語ることはできます。歯科技工士の立場から補綴物の製作に関して、このようにすれば現在抱えている問題を解決とまではいかないけれども、アイデアを提案して問題解決を前進させることができるのではないかと思います。
※中心咬合位は、上下の歯列の位置関係のことで、中心位とは、側頭部の下顎窩と下顎の下顎頭の位置関係に関する、骨と骨の位置関係のことです。中心位は歴史的に定義が変化しています。
※ターミナル・ヒンジアキシス(終末蝶番軸)と中心位の関係(Centric relation in the terminal hinge position of the mandible , in which the hinge axis is constant to both the mandible and maxilla.)「下顎が終末蝶番軸を中心として純粋な蝶番運動を営むときの上下顎の位置関係が中心位である」。これは、「歯界展望」の2022年7月号に特集されている、「中心位を再考する(理論編)」より引用。
※「歯界展望」は日本の歯科業界誌です。
上下顎に及ぶような大規模な歯科補綴をするケースについて:中心咬合位や中心位の位置の決定は、診断に関することなので歯科医師が行います。
補綴物の臼歯の咬合面の形状について、現在ではほとんどの場合、歯科技工士が形状の作成を行っています。しかし私はできることなら、歯科医師が設計を行う方がよいと思っています。その理由は、歯科技工士は最初に教えられたことを反復的に行うことから自力では脱することができないからです。できることは技術をシェイプアップすることや製作時間の短縮ぐらいです。
歯科技工士は患者さんとの直接的なかかわりがないので、そういうことになるのです。また、職務権限上の理由ということもあります。患者は歯科医の先生を頼って来院するのであって歯科技工士ではありません。権限と責任について当然そうなります。また、アカデミックな発表の場において症例報告するとき、「歯科医師が設計し、技工士に制作を依頼した」といった方が聴視者の興味が増すと思います。
歯科医師の場合は、患者さんという生体と関わることで、対話的に補綴物を変化させることができると思います。現在では、歯科医師が補綴物を直接作ることがほとんどありませんので、歯科医師がCADで補綴物の設計を行い、歯科技工士が製作を行うとよいと思っています。それでは、歯科医療の業界で、このような「新しいモノづくり」をするためにはどうしたらよいのでしょうか。
現在、注目されているシステム理論のひとつに「オートポイエーシス」というものがあります。このオートポイエーシスを実際に歯科の補綴分野の歯科技工、補綴物の製作に導入することができれば「新しいモノづくり」が実現できると考えます。それは歯科医師がCADを使ったシステムで補綴物の設計に積極的に参加することによって、オートポイエーシスは実現されると思います。
歯科医師が経済負担をすることなくCAD を自由に使うことが難しいことが考えられます。また今まで歯科医療の現場で具体的な補綴物の設計を歯科医師が行い、製作は歯科技工士が行うという習慣がありませんでした。本来的にいえば、歯科医療では治療と補綴物の製作、両方ともに歯科医師が行うことが建前であると思います。したがって、歯科医師がCADで設計を行うことに歯科医師法、歯科技工士法から考えても全く問題はありません。「新しいモノづくり」を何か阻むものがあるのでしょうか。あるとすれば、歯科技工士が補綴物の具体的な設計を行うという習慣でしょうか。歯科医師がCADを使うということに関しては、現在ではCADのライセンスの形態もいろいろあって経済的な負担も軽減されていると思います。
CADが登場する前には、歯のようなオーガニックな3次元形状を具体的に設計するということはできませんでした。作りながら設計するというスタイルを踏襲するしかありませんでした。
一般の工業界においては、1960年代に2次元製図システムが登場し、1980年代に入って3次元CADシステムの商品化がされるようになりました。歯科用CADとしては、1985年にスイス・チューリッヒ大学のグループが、ドイツ・シーメンス社と共同で開発して世に送り出した「CERECシステム」が最初であったと考えられています。
何らかの技術的なきっかけがあれば、現在の歯科技工士が補綴物の具体的な設計をしている状態を、理想的な姿に戻すことが可能であると思います。理想的な姿とは、歯科医師が補綴物の設計をして、歯科技工士がそれに基づいて製作するということです。もしくは、完成時のデザインを歯科技工士が作成して、歯科医師が製作する前に確認するということでもよいでしょう。オートポイエーシスが指し示す「最適化」という操作は、患者との接触がない歯科技工士には難しい操作であると思います。
そもそも歯科技工士という職業は、歯科医師が治療で忙しくなったので歯科治療に供する補綴物の製作ついて、診断や治療については十分な知識がなくても、歯科技工という範囲に限って助手に任せたというのが始まりであったと思います。その後、独立した専門職業となりました。しかし、歯科技工士には患者に直接に接する機会がないので、口腔内に装着した補綴物の評価をすることができません。このようなことから補綴物の具体的な設計に歯科医師が直接関わった方がよいと、私は主張します。
その補綴物の具体的な設計に歯科医師に参加していただくことの合理性を説明する必要が生じてくると思います。口腔というシステムを取り扱うための「複雑性の縮減」、つまり「オートポイエーシスの概念」の導入を提案いたします。「複雑性の縮減」とは、システムを取扱いやすくするための手順と言いかえることもできます。人間が新しい方法で自然と関わりあおうとするとき、そこには順序だった作法のようなものが必要で、単にできればよいということではないようです。その手順を示すのが「オートポイエーシス」です。
ダイナミカル・システムの構成要素である、オートポイエーシスとはなんですか?
1960年代に新しいオートポイエーシスというシステムの基本モデルとなる概念がチリの生物学者であり神経生理学者であるフランベルト・R・マトゥラーナとフランシスコ・J・ヴァレラの二人から発表されました。ギリシア語のautos(=自己)とpoiein(=つくる)から合成されたオートポイエーシス(Autopoiesis)という人工語は、自己産出といったようなことを意味しています。彼らは、この概念を超自然的な力や原理の助けをかりず、物理学的、化学的な自然法則だけに訴えるアプローチであるとしています。
オートポイエーシスは生命システムの謎、とくに免疫的なシステムの謎を解くための概念として考えだされました。生命が「非自己」を活用しつつ自己組織化をとげながら、それでもシステムとしての「自己」を環境の内外で保持しているのはなぜなのでしょうか。そこには「自己を再生産するための自己準拠」や「自己による自己再帰」のしくみがあるのではないのかと考えられます。
生命は自分自身についての「自己言及」をしながらもそこに生じる自己矛盾(コンフリクト)をたくみに超越するしくみをもっているのではないのかとも考えられます。それはオートポイエーシスとでもいいうるものではないのか、マトゥラーナとヴァレラはそういう仮説をたてました。彼らの試みは、オートポイエーシス概念を用いて、生きているものの一般的な組織原理を、つまり、すべての生命体に妥当する組織原理を定式化することです。また、ニクラス・ルーマンはオートポイエーシスをもとに、社会システム論をつくりました。ここで論ずるシステム論は、ニクラス・ルーマンの社会システム論を参考にしています。
複雑系とは何でしょうか?
ニクラス・ルーマンは世界や社会をつねに複雑系として捉えました。世界や社会を形成する根源的な単位を「意味」に求めようとしつづけたこと、その意味を加工編集するものはすべからく「システム」であるとみなしました。
ルーマンは、社会は複雑なシステムであり、そのシステムは人間の理解する意味によって構成されるとみなしたのです。複雑系の科学は、部分が系の全体としての挙動にどのような関係性を持つのか、どのように系が相互に、あるいはそれが属する環境に関係性を持つのか、といったことに関して研究する科学に対する新しい手法です。
2つの側面からアプローチすることが有効とされます。例えば下顎の運動時における咀嚼運動を考えてみましょう。自然科学からの側面は、実体の歯の形態である咬合面の形状を取り扱い、一方社会科学からの側面は、咬合面間空間の変化を取り扱います。
まさに、「咬合面間空間は上下の歯のコミュニケーションの場」であるといえるでしょう。複雑系の科学の具体的な研究方法として、CADでのパラメータの変更による設計や有限要素法による構造・運動の連成解析などありますが、シミュレーションは有効な技法の1つです。
歯の形1本からだけでは、システムとしての歯の機能を見いだすことはできず、臼歯の咬合面の形状は咀嚼運動という行為でつくり出されるコミュニケーションを考えないと理解することができません。上顎と下顎の臼歯の咬合面は、中心咬合位における接触関係だけでなく、下顎運動時における近接関係の変化が問われます。咬合面間空間の変化とは、食物をかみ砕くために下顎が運動したとき、上の顎の歯と下の顎の歯の間にできる隙間が変化することをいいます。近接関係の変化と同じです。
社会システムのような複雑性は、システム理論によって内的対立から絶妙な複雑性の縮減や解放がもたらされて解消されます。対象となることがらが複雑であればあるほど、さらなる複雑なシステム理論が必要となります。歯科医療に限らず、医療は一般に応用自然科学の分野に属しているといわれます。また、医療は人間が組織だって行うために社会科学の分野にも属しているといわれています。つまり、社会システム理論は人間世界と自然世界を区別しながらも、統合して人間独自の解釈にもとづく世界観をつくります。
オートポイエーシスと歯科技工にはどんな関係があるのでしょう?
私は補綴物の具体的な設計に歯科医師が積極的にかかわるべきだと考えます。それを実現するためには、そのことに対応できるCADシステムと導入のための概念(コンセプト)が必要です。その概念として、オートポイエーシスが適当であると思います。歯科技工というよりも、もう一つ枠を広げて歯科補綴分野にオートポイエーシス概念を導入するということになります。こうなると歯科技工士がカバーする範囲を超えますので、ここでは歯科技工に関する分野に限って述べます。人間社会の社会システムに限らず、歯科技工にもオートポイエーシス概念を導入することができると思います。
※歯科補綴分野とは、歯科補綴学のことです。歯科補綴学(prosthodontics)は歯学の専門分野の一つであり、臨床歯科医学の一分野で、歯や関連組織の欠損によって生じる顎口腔系の機能障害、審美性を回復することを目的とする学問です。単に補綴学(ほてつがく)とも呼ばれます。ウィキペディアより
補綴物であるクラウンの臼歯の咬合面の形状を考えるとき、自然物としての歯の本体と社会物としての咬合面空間の両面を考えてつくらなければならないということになります。実際に、食物を噛み砕いたり、噛み切ったりするのは、上下の歯の隙間・空間の変化であり、実体の歯ではありません。上顎、または下顎の片側のみに、どんなに立派な歯があったとしても本来の機能を果たすことはできません。私は「下顎の運動によって生ずる臼歯の咬合面間の空間の変化は、創発的に設計されるべきだ」と考えます。
臼歯の機能を表す咬合面の形状や前歯の切縁の形状は社会科学的な取り扱いをしないかぎり、形状の意味を解釈できないと思います。臼歯の咬合面の凸凹は、部位によって特定のパターンをもっています。歯根も臼歯の部位によって1本のところ、2本のところ、3本のところがあります。また、臼歯の歯根は複雑に湾曲しています。下顎の左右の関節も3次元的なスライドと回転が混在して、単純系へのモデル化が困難なほど、様々な要因が複雑に絡まった複雑系であると思います。
歯科医師が咀嚼運動時に機能する臼歯の咬合面の凸凹のパターンがなぜこのような形をしているのかということをオートポイエーシス概念の立場から述べるためには、内部構造や形状を正確に計測する必要があります。また正確な下顎の運動を分析する必要もあるでしょう。さらに下顎の運動に合わせて上下の歯列の咬合面間の隙間がどのように変化するか正確に測定する必要があると思います。
歯は人間がつくったものではありません。「実体としての人間の顎システム」はすでに存在しています。したがって、現実の顎の関節や歯、骨などの構造・形状はすでに、ソリッドで硬質な物体として存在しています。これを詳細に分析します。歯のエナメル質は硬質な物質であり、はっきりと境界をつくりますが、経時的に徐々にすり減ります。上顎の歯と下顎の歯の咬合面間の隙間が、どのように変化するのかということについて考える必要性とは、咬耗する前には、未知なる何かがあったけれども、経時的に何が変化したのかを知らなくては治療できないからです。歯の咬合面間の隙間は時間とともにだんだんと変化します。その治療とは変化したものを回復させることであり、このような創発した内容についても新たな治療対象になる可能性があります。
CADによる設計には、同一の対象に対して、スタティック・デザインとダイナミック・デザインが必要になると思います。スタティック・デザインとは、通常の意味での設計図です。歯の寸法や位置、傾きなどです。ダイナミック・デザインはスタティック・デザインの説明のために必要なもので、設計図が二種類必要になるというわけではありません。なぜ、そうしたのかという「スタティック・デザインの理由」を設計するために必要なのです。ダイナミック・デザインは、四次元の設計です。設計には時間が組み込まれています。
コンティンジェンシー(contingency)と、ダブル・コンティンジェンシー(double contingency)という言葉は分かりにくい言葉です。他の言葉で表現できませんか?
コンティンジェンシーは、「別様の可能性」とか「機能的な等価性」と訳されたり、「偶有性」と訳されたり、文脈によっていろいろな訳し方があるようです。また、コンティンジェンシーには、2つの意味構成があります。一つは「あるものに依存する」ということです。もう一つは「他にも可能である」ということです。つまり「不可能性」と「必然性の否定」としてのコンティンジェンシーということになります。ダブル・コンティンジェンシーは、「二重の条件依存性」と言い換えることができるようです。
そもそも社会システムとは何ですか?
パーソンズは、自著の『社会体系論』で解決しようとした問題とは何であったのでしょうか。それは有名な「ホッブズ問題」とよばれるものです。「ホッブズ問題」とは、人々が功利的に利害を追求するとき、いかにして社会秩序は可能かという問題です。パーソンズによれば、トマス・ホッブズはこの問題は諸個人が社会契約することで解決するとしました。しかし、パーソンズはこれを功利概念の過大な拡張であり、実際には解決できていないとしました。『社会体系論』においては「ホッブズ問題」はダブル・コンティンジェンシー(二重の条件依存性)」の問題へとおきかえられています。
その「ダブル・コンティンジェンシー」とは、自己と相手の欲求の充足がそれぞれ相手の行為に依存するのですが、この相手の行為がこちらの行為のいかんに依存していることを意味します。こうして社会秩序の問題は、2者関係における相互行為の安定性条件の問題へと移しかえられます。つまり、社会システムによって自己と相手の安定、維持をはかります。これは人間社会のシステムについて述べていますが、言いかえることによって、自然物にもあてはめることができると思います。それは結局、人間自身の問題だからです。人間がどうとらえるかということなのです。
オートポイエーシスの「構造的カップリング」について
ここで臼歯の咬合面の形状の再構成を行う場合について、オートポイエーシス論の「構造的カップリング」を適用してみます。上顎の歯列、もしくは下顎の歯列はそれぞれ自己の価値体系という閉鎖的なシステム内にとどまっており、自己のシステムの機能性を向上させることに有益であれば、相手の顎の歯列と相互的な関係を構築させるように形成させます。
一方、「相互浸透」というのは、二つの異なるシステム、つまり上顎の歯列と下顎の歯列を相互に関係させることによって、それぞれの咬合面のかみ合わせが複雑性を増していくことによって生ずる現象を指します。ルーマンによると、相互浸透の鍵は、二つのシステムが互いに開放的であり、各々のシステムの複雑性を他方へ移転させることが可能なことにあります。こうした相互浸透によって、お互いのシステムは変容を遂げていく機会を得るのです。上顎の歯列というシステムと下顎の歯列というシステムのそれぞれの咬合面は閉鎖的ではなく開放的なものとなり、相対するシステムの複雑性と自己のシステムの複雑性をやり取りするようなあり方になっています。この姿はまさしく相互浸透的であると表現できるのではないでしょうか。
人間は自然世界の仕組みが理解できたとしても、自然世界と同じことはできません。人間の想像力に頼らないと、できないことがあるのかもしれません。歯の形状の生成に関して、自然世界においては遺伝子によって定められているのかもしれませんが、人間がその一部を再構成する場合、遺伝子操作によって作ることはできません。
自然世界で行われたであろう結果的な存在をリバースエンジニアリング的な思考で再構成して目的を成し遂げることになります。その方法がオートポイエーシスによる歯の形状の再構成方法ということになります。従来の方法では人間の想像力をもとに手作業で歯の形状の編集が行われていましたが、新しい方法では上顎の歯列と下顎の歯列、2つのシステム間のコミュニケーションの役割を人工知能が行い、補助的な形状の作成はCADで行うことになります。
必然性と偶然性について
対象の内部に働いているものを必然性と偶然性というカテゴリーではなく、唯一性と多様性というカテゴリーに変更することは、人間の自発的な感性を信頼して二分したことになります。この二つの観点から対象を認識することにより、それが「最適化」されていると定義されるのではないでしょうか。このように二元化する方法を変えることによって何が変わるのでしょうか。
最初に必然性と偶然性について考えてみます。唯一性と多様性については後で述べることにします。必然性と偶然性というカテゴリーも人間が作りました。これは、唯物論における重要な見解となっています。この二つの組み合わせで見える視座は、いったいどこにあるのでしょう。また、新しく提起した唯一性と多様性というカテゴリーが見える視座との違いはどこにあるのでしょう。前者は過去だけを見て未来は見ないでおいて、未来は向こうからやってくるに任せると考えます。後者は過去も未来も両方とも見て積極的に関わらなければならないと考えます。
進化論は過去に起こったであろうことを物的証拠を元に分析して作り上げました。最先端は現在です。これより先はありません。進化論は、いったい何を説明したいのでしょうか。それは現在というものであり、現在において存在している我々人間を含む自然世界です。現在ある我々はこのような道をたどってきたという過程です。進化論は現在ある我々の世界はこのような理由で存在しているということを説明します。未来については具体的な資料がないので分析できません。それは不明です。当然なことです。あるとすれば、未来においても存在したいという人間の希望でしょう。
唯物論は過去を二つに分けました。二つに分けたといいましたが、実は分けていません。実際には過去を必然性と偶然性というように二つに分けることはできません。これは結果が分かっているからこそ、このような表現ができるのです。現在というものはすでに確定してしまっていることなのです。未来については適用できません。確定してしまったことに対する人間の評価です。過去に対して、たとえどのような評価を与えても物質的な意味での現在は変わることはありません。
必然性とは、そうなることが確実であって、それ以外はありえないということであり、また、いつ起こるのかということもわかっているのです。偶然性とは、予期しないことを起こす要素、性質のことです。偶然性は現在を変化させるのですが、どのように変化させるかはわかりません。また、いつ変化するのかはわからないということです。確実なことを起こす原因と不確実なことを起こす原因があり、これら2つが渾然一体になって世界は成立してきたとしています。
このカテゴリーでは、未来については100%の偶然性、つまり不確実なことということになります。必然性は過去に経験したことのみ見出すことが出来ます。未来はまだ存在していないのであり人間が軽々しく口にすべきことではありません。また未来のようなことに関しては人間は具体的な分析対象としていません。一方向の時間の経過とともに、何が現在を作っているのか、現在の存在理由の説明をして、自然に対して受動的であった人間の立場が説明されます。未来への展望はありません。
必然性と偶然性というカテゴリーは対立関係という認識を軸にしています。必然性と偶然性は二者択一ということです。「わかるもの」と「わからないもの」、または、「はっきりしたもの」と「ぼやけたもの」など、相対的な関係になっています。これは人間の思いであり、人間の内なる対立する心が、現存する問題を解決しようとしてこのように分け方を考えだしました。このような対立関係から現在というものを説明する方法です。
現在から未来を見ても確実なことを見出すことができません。確かなものは過去にしか見出すことができないのです。現在見ることができているものは、すべて過去に生産されたものです。過去だけを見つめることを、必然性と偶然性というカテゴリーからの発想といいます。必然性と偶然性というカテゴリーは、過去を認識するためのツールです。過去は関係が確定しているから分けることができません。物事の因果関係は確定していますが、ただ人間はすべて知ることができないだけなのです。
進化論を支える必然性と偶然性というカテゴリーは、言い換えると混然としたものと言い換えることができると思います。必然性と偶然性の2つに分けるということは言葉のレトリックにすぎません。実際は2つが分けられないような状態をあらわしています。必然性と偶然性というカテゴリーでは、未来に対してもそのような態度をとることを勧めています。
唯一性と多様性について
人間にとって唯一のこととは、どのようなことでしょうか。それは、人間世界の永遠性であると思います。人間にとってこれ以外のことはないでしょう。また多様性とは、二者の間の選択肢の比率のことを指しています。多様性というからには、1に対して10,000倍とか、1に対して100,000倍とか、それ以上の比率ということになるでしょう。とにかく相手には一つしか選択肢がないのだけれども、私にはそれに対して圧倒的な数の選択肢を持っているということです。このことは自然界の中で人間が特別な存在であるということを自らが自負すべきであると思います。
ところで、科学は有用であり、現在、人間がもっとも力を入れている分野であると思います。科学は人間が能動的に未来に関与するための道具であり、過去における成果を未来へ投影するためにつくられたのです。未来はまだ存在していません。未来は「必然と偶然」によって自然に任せるべきものであり、自動的に作られていくものなのでしょうか。それとも、人間が創らなければならないものなのでしょうか。未来を創る素材は過去から現在に至るまでに用意されているよう思います。未来について人間のなすべきことが特別に何かあるのでしょうか。私が思うことですが、未来について確かなものとは、それは人間です。人間が未来を考えることができる限り未来はあります。未来を考えるのは人間しかいません。未来を考えるには基本的なカテゴリーとして唯一性と多様性という、この2つが必要です。
一つは人間世界の永遠性で、もう一つは人間が自然世界でいろいろな意味での多様的で圧倒的な存在であることの認識です。それらは人間の責任で果たされるべきものです。責任を感じなくしては、なしえないものです。唯一性と多様性というカテゴリーは、一致という共通の認識を持っています。この二つの概念の一致なくしては、人間は未来において存在できないからです。調和や統一ではありません。
ここで提起した「唯一性と多様性」というカテゴリーで歴史というもの考察した場合、どのように取り扱ったらよいのでしょうか。私は歴史とは人間が思考し認識する際に参照できる証拠と事実に基づいた現実の記録であり、生成され得る可能性の中から合理的であると思われる 1つの可能性を選択して記述したものであると考えています。これは非常に主観的な見方といえるでしょう。選択する主体者は人間であり、あらゆる可能性の中から一つ選び、事実として最適なものが記述されたもの、それが歴史になると考えます。
それゆえに、未来の歴史は現在よりも時間的に進んだ方向の記述となりますので、まだ現実には起きていません。記述された未来と現在からの道筋を作るのは人間です。「唯一性と多様性」というカテゴリーで考えることは、人間自身によって人間の未来を守護するのであり、この世を支えているのは人間であるという確信を持つことだと考えます。
必然性と偶然性というカテゴリーで歴史というもの考察した場合、どのように取り扱ったらよいのでしょうか。客観的な表現をしていても主体者は間違いなく人間なのです。これは従来からの歴史の見方です。進化論もこれに含まれると思います。「唯一性と多様性」と「必然性と偶然性」とはカテゴリーが違います。当然ですが2者の表現の仕方が違ってきます。過去の歴史とは、人間の客観的な判断によって選ばれどのように選択されてきたのか、記述されてきたものです。
ここで何を言いたいのかといえば、「唯一性と多様性」というカテゴリーで考えれば、人間は未来を自由に作ることができるということになります。また、過去に関していえば、過去は物理的に操作することはできませんが、過去に対しての評価は変えることができます。「必然性と偶然性」というカテゴリーから「「唯一性と多様性」というカテゴリーに変えることによって、人間の未来にとって重要なものを過去からもっと多く見つけ出すことが出来、未来に向けて転用できると思います。
サルが人に徐々に進化したのか、それともいきなり肌のつるつるした人間が登場したのかはわかりませんが、人間はいつの間にかこの世に登場しました。赤ちゃんも成長して子供になり、いつのまにか世の中について理解する心ができます。人間が自分の記憶の中で、みずからの赤ちゃんのころを思い起こすことがむつかしいように、人間が人間の歴史の最初を知ることはむつかしいことです。記録がないので、これを知ることは想像にたよるしか方法はありません。また、必然性と偶然性というカテゴリーで未来をみている限り、過去の再生産ばかりして、少しも前に進まないと思います。
社会科学の重要性について
人間の顎の関節の構造、上顎の歯と下顎の歯の全体かたち、臼歯の咬合面のパターンなどを見るとき、それらが機能する状況を見ることができます。それらの機能と形状が一致しており、そこには矛盾や対立は見出せません。食物を咬み砕いたり、発音したりする場合、口腔の各部分が目的に対して一致し、それぞれが固有の機能を発現する状況を見ることができます。私たちはこの状況から自然科学からだけでは到達することが出来ない社会科学的な共同体としての認識や知識の体系を見つけることができます。
これが社会科学にも注目する理由です。それは人間が観察して考えたことだからです。人間は、人間というしがらみからは逃れることができません。人間が作ったものではないものでも、観察者が人間ならば、人間というフィルターを通しての事実となります。どのようにしても人間というフィルターは、はずすことができません。もしもはずすことができたとしても、それは人間の理解できないものになってしまいます。意味のない羅列になってしまうでしょう。人間は、人間の理解できる意味や価値観としてのみ認識することができます。
人間は自然世界の一部であり、かつ独立した存在ではあるのだけれども、今まで人間は何から何まですべて自然の中から見つけて利用してきました。人間が本当に作れるのは理屈(理論)だけです。物については、100%自然界のものを利用します。ただ、これさえも作ったというよりも、発見ということになるかもしれません。 理屈(理論)の表現方法には、哲学、数学などがあります。これらは人間の発明品です。しかし、自然世界に対して人間が発明したルールを付け加えることはできません。できるのは、自然のルールに関与することだけです。人間ができることは自然の力、仕組みを利用することだけです。
自然界において人間だけが一つ持っていたのは「人間というフィルター」だけだと思います。「人間というフィルター」とは、頭の中にある参照するデータのことです。このフィルターを通して見たり、聞いたり、考えてきたりしました。このフィルターを持っていたために、現在のように栄えることができるようになりました。それは、人間世界の永遠性と人間が自然世界でいろいろな意味での圧倒的な存在であることの認識であり、未来を考えたことです。これが自然科学だけでなく、社会科学の必要性の理由です。