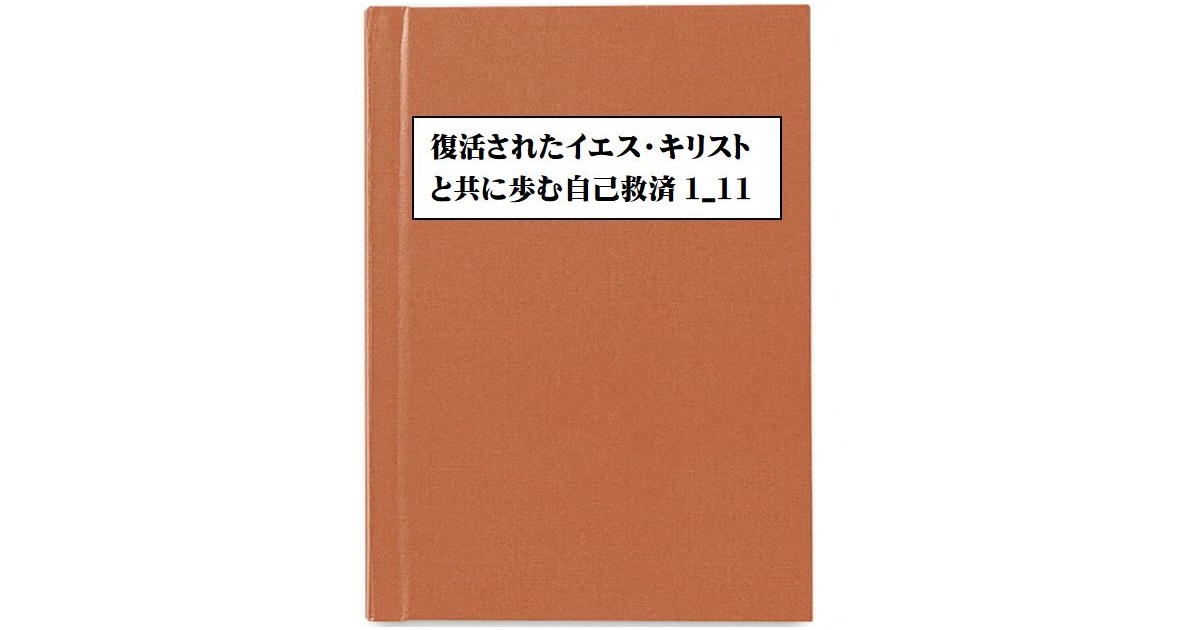この表について説明します
|
コンティンジェンシー Contingency 「偶然性」「偶有性」「不確実性」 「偶発事件」「不慮の事故」などのこと。 依存する」という意味もあります。 この用語を使った「コンティンジェンシー理論」という言葉がありますが、日本語では「環境適応理論」と訳されます。世の中には、さまざまな環境が存在しますが、唯一で最良なシステムというものは存在しないので、環境が変わればシステムも変わるべきだとする理論です。 |
ダブル・コンティンジェンシー Double contingency 「二重の条件依存性」のこと。 選択するということは、他でありえた可能性の否定であり、その意味で二重の否定です。自我が他者を自らにとっては不透明なもう一人の自我(他我)として体験することによって、選択において否定された潜在的な可能性が、自我と他我の双方において相互的に、現実化はされないが含意はされている可能性として保存され、安定化される。こうした事態を、ルーマンはダブル・コンティンジェンシーとしました。 |
|
| 1 | 存在論 | 認識論 |
| 2 | 継続 | 変化 |
| 3 | 設計 | 最適化 |
| 4 | 相対性 | 対称性 |
| 5 | デジタル | アナログ |
| 6 | 環境 | システム |
| 7 | 因果 | 循環 |
| 8 | 有限(時間) | 無限(空間) |
| 9 | 階層 | ネットワーク |
| 10 | 多様性 | 唯一性 |
| 11 | 死 | 復活 |
| 12 | 統一(調和) | 一致 |
| 13 | 俗 | 聖 |
| 14 | 体(物質) | 魂(生命) |
| 15 | 体験 | 知識 |
| 16 | 物 | 言葉 |
| 17 | 価値 | 意味 |
| 18 | 現象 | 原因 |
| 19 | 考える | 感じる |
| 20 | 最後まで | できるところまで |
| 21 | 相対性理論 | 量子力学 |
| 22 | 粒子(量子力学) | 波(量子力学) |
| 23 | 質量 | エネルギー |
| 24 | マクロ | ミクロ |
| 25 | 自然科学(自然側からのアプローチ) | 社会科学(人間側からのアプローチ) |
| 26 | 運 | 技術 |
| 27 | (記憶力)自己認識 | 想像力 |
| 28 | 進化 | 創造 |
| 29 | 形状 | 機能 |
| 30 | (過去から現在まで)これまで | (現在から未来へ)これから |
システム理論について
この表について説明する前に、システムということについて簡単に説明させていただきます。Webサイトからの情報を参考にしました。
たとえば、社会システム理論とは、社会をシステムの観点から読み解こうとする理論であります。システムとは一つのまとまり、または集合、つまり、「集まり」であり,それを構成する要素、たとえば部分、または成分は互いに関連し、なんらかの機能を果たしていることを前提としています。システムの機能は、それぞれの要素の機能の総和以上のものとなります。システムの要素間の相互作用から生じる効果は創発効果とよばれます。
システムという概念は非常に一般的であるために、システムの観点から、諸科学で扱うモデルの同型性に着目して、諸科学の分類や統合的な見通しが可能になります。これがシステム的思考であり,1950年代に諸科学の共通性に着目するシステム理論が明確な形で姿を現わすことになりました。
システムには、機械などの物質で構成されたシステム、動物などの有機的な生体システム、概念、文字、数式などを要素とする抽象的システムなどさまざまな種類があります。心理学が対象とする人間は、一つのシステムとして考えることができます。このシステムは閉じておらず、他の人間と交流する開放的なシステムであります。同様に組織や文化などもシステムであります。知覚のような、より基本的な心理機能においても、ゲシュタルト心理学、つまり、人間の精神を、部分や要素の集合ではなく、全体性や構造に重点を置いて捉える心理学が指摘するように、全体性が重要な決定因であります。心理学もこの統合的な見通しによって、他の学問分野のモデルを直接的に導入することや、理論の完成のために欠けている部分のヒントを得ることができます。
完全な形でシステムという概念が現れた理論は、人類史上で見てもシステム理論が初めてであります。しかし、システムという概念が何の礎も無く突如として出現したわけではなく、システム理論の提唱以前にも生気論と機械論の対立など、システムに繋がるような議論が数世紀に渡って継続的に行われて来ていたことに、注意する必要があります。
19世紀以前にはシステムを抽出する前提となる諸分野が未発達であったため、諸分野から完全な形でシステムを抽出して説明することが出来ず、全体性に関する種々の説明が形而上学としてみなされるなどして要素還元主義の牙城を崩すには至っていなかったのであります。
さて、最新のシステム理論である、オート・ポイエーシスは、1970年代初頭、チリの生物学者ウンベルト・マトゥラーナとフランシスコ・バレーラにより、「生命の有機構成とは何か」という本質的問いを見定めるものとして提唱されました。生命が自律的に、いかに生成するのかということにまで言及できる理論といわれています。
オート・ポイエーシスは、主観世界すらも説明可能なシステム論であると言われており、生命の自律性に対する言及ができない「自己組織化」までのシステム論の限界を、突破することに成功していると言われています。 特に細胞の代謝系や神経系に注目した彼らは、物質の種類を越えたシステムそのものとしての本質的な特性を、円環的な構成と自己による境界決定をする機能を盛り込みました。 現在では、このような自己言及的で自己決定的なシステムを表現しうる概念として、元来の生物学的対象を越えて、さまざまな分野へ応用されるようになりました。最先端であるがゆえに、学術界では現在もオート・ポイエーシスに関する統一された見解はなく、多様な解釈に基づいて議論が展開されています。 なお、オート・ポイエーシスという語はギリシャ語でオートは自己、ポイエーシスは製作・生産・創作を意味する造語であり、日本語ではしばしば自己創出、自己産出とも書かれます。
ビーレフェルト大学社会学部の教授であった、ニクラス・ルーマンは、チリの生物学者ウンベルト・マトゥラーナとフランシスコ・バレーラにより、「生命の有機構成とは何か」という本質的問いを見定めるものとして提唱された、オート・ポイエーシスという言葉をキーワードに社会システム理論を構築しました。 もともとは生命を定義するための生物学の理論として提唱したものです。つまり、マトゥラーナは「生命はオート・ポイエーシス・システムである」と考えました。一つの生物学の理論にすぎないのだけれども、1980 年代にドイツの社会学者ニクラス・ルーマンが、この理論を社会学に応用して、独創的な「社会システム論」を発表しました。これは社会をオート・ポイエーシス・システムとして考察したもので、これをきっかけに様々なものがオート・ポイエーシス・システムとして見なされるようになって、いろいろな分野でオート・ポイエーシス論が応用されるようになってきています。
この表について説明します
ニクラス・ルーマンの社会システム論は、多次元的・相互補完的・相互浸透的なシステムを基本としています。なぜ、私がニクラス・ルーマンの社会システム理論を人間の意識と理性の表現に利用したのかという理由ですが、物事を仕組みとして考えるとき、また、他の人に自分の意図することを伝えようとするとき、万人に共通の、つまり普遍的な表現方法で伝えるためには最新といわれる方法で行うことが良いと思われたからであります。複数の要素が、一つの仕組みとして有機的に機能している様子をイメージしてみますと、人間の意識と理性の表現には、オート・ポイエーシス・システムとして考察することが適当ではないかと考えて、ニクラス・ルーマンの社会システム論を採用しました。
オート・ポイエーシス・システムは、自己を構成する要素を自ら生み出し、つまり、自己産出をして、姿を変えるシステムであります。
複雑性の縮減について
ニクラス・ルーマンの社会システム論の特徴の一つである、複雑性の縮減ということを簡単に表現しますと、自らが複雑なことに対応するための用意をするということになります。例えば、細かな時計の部品を取り扱おうとするならば、手先が器用でなくてはならないし、また、繊細な神経も必要であり、粘り強い精神が必要です。力は強いが大雑把では、複雑で繊細な対象を扱うことはできません。繊細な対象に気づかず、破壊しかねません。本来的な「複雑性の縮減」とは、力もあり、繊細な対象にも目が届くということであります。「複雑性の縮減」ということは、そういったことに対応できるための素養、つまり、そのような考え方を人間が身に着けることが必要である、ということになります。
具体的に表にして、表現してみました。この表は、人間の普遍的な機能である理性を用いて、表で表した項目から科学的な概念や宗教的な概念の関係性を示すために一覧表で表現してみました。なぜこのような表にして表現したのかという理由ですが、現代社会は断片化し多様化しているので、全体を一挙に捉えることが必要であると考えたからです。
こういった内容を、ひとつずつ箇条書きに列記するのではなく、構造的に関連性を含むように記述することが必要であると思います。意識とは、その人間がどこに気を止めているか、注目しているのか、ということを表しているものであり、理性は意識が参照する対象であります。
ニクラス・ルーマンの社会システム論はオート・ポイエーシスを基に構築された理論であり、人間が人工的に作ったものであると思いますが、自然現象に対してどのような反応をすることができるのでしょうか。オート・ポイエーシス・システムは、もともと有機的な生体の神経のしくみを原理としているので、自然現象とうまくマッチングして受け入れられると考えます。
システムは、より複雑怪奇な外部環境との出入りに耐える程度に、システム自身を複雑化することによって、システム境界を維持しています。これを、「複雑性の縮減」と呼びます。現実世界の複雑性に対応するためのシステムは、自らが複雑性を保持していないと複雑性に対応できないということであります。対応できないということは死を意味します。生命システムにとっての死は、オート・ポイエーシス・システムの作動が止まる、あるいは消滅することです。
この「複雑性の縮減」は、生物において自動的に対応します。たとえば、人間が変化した環境の状況に対するために、脳の再組織化の発現についての例があります。また、自然環境に対する生物の行動なども、その生物が存在するために、最もよいと思われる行動様式に組み直すということも、行われると思います。
「コンティンジェンシー」と「ダブル・コンティンジェンシー」の関係の定義について
左の欄の「偶有性」とは、確実さと不確実さが混じり入った存在であり、現在おかれている状況に、何の必然性もないということであります。そのような世界に、たまたま存在している私たちなのであります。このような状況には、絶対的な根拠は存在しません。実はこのような偶有性とは、生命の本質であります。偶有性は、私たちを不安にさせます。しかし、この不安こそが自らが生命であることの証であるわけです。
右の欄の「二重の偶有性」とは、「二重の条件依存性」ともいわれます。二重の条件依存性は、選択するということは他でありえた可能性の否定であり、その意味で二重の否定です。ここで、二重の否定をして強い肯定を表す例として、文章を示します。
「人間は、誰かを愛さずにはいられない」
上記の例文は、「愛さず(愛さない)」という否定を、さらに「いられない」で否定しています。「誰かを愛する」という肯定文と同じ意味ですが、強調しています。
二重の否定では、強い肯定の表現ばかりではなく、肯定なのか否定なのかわからない曖昧な肯定を表すような二重の否定の用法もあります。
「その意見は 正しくないこともない」
上記の例文は、一読して、正しいのか、正しくないのか、はっきりしません。
この二重の否定の例文は、「正しくない」を、さらに「ない」と否定することにで、「正しい」という肯定を意味しますが、「正しい」と言い切るよりは、微妙なニュアンスを含んでいます。このように、「二重の条件依存性」は、直接的に表現するよりも、本体の文章に付加的な情報を与えています。つまり、何かはあるのだけれども、はっきり見える存在ではありません。
このことを人間の意識に当てはめて考えてみますと、自分自身が他者のことを、自らにとっては不透明なもう一人の自我、言い方を変えると、他我として体験することにより、選択することによって否定された潜在的な可能性が、自我と他我の双方において相互的に、現実化はされませんが、含意はされている可能性として保存され安定化される、こうした事態を、ルーマンはダブル・コンティンジェンシーとしました。
表について、いくつか抜粋して「構造的カップリング」を説明します
構造的カップリングとは、システムは環境の攪乱の中で、自らの構造を変えたり環境を変えたりすることによって再生産機構そのものである、「組織」を保持していきます。このような、システムと環境との間で進行する過程を、マトゥラーナは構造的カップリングと呼びました。現実世界における、環境の限定された領域に、対を成す、システムの限定された領域を、ニクラス・ルーマンは、合わせて「構造的カップリング」としました。
表の右の欄を上から下へご覧になると気がつかれると思いますが、表現するために、媒質に相当するものが必要と思われる要素が列記されています。
たとえば、「継続」と「変化」の構造的カップリング、つまり、組み合わせにつきましては、明らかに右側の「変化」の方が、多くの情報を持っていることがわかると思います。それは、時間の経過に合わせて情報の増減が見られるということです。左側の「継続」におきましては、時間軸に対する情報の断面が一定であり、時間が経過してもそのままです。右側の「変化」では、何が変化しているのかといえば、それは何らかの情報を示す媒質のレベルが増減して、経時的に情報量の断面が変わることを示します。(2023/4/03・文字追加)
「設計」と「最適化」について説明します。一般的に言われていることですが、設計とは、内部構造や各部の寸法、外形のデザインなどを決めることをいいます。そして最適化とは、設計をもう一歩進めて、複数の構成要素からなり、構成要素が互いに影響し合い、全体として何らかの機能を持つようなものをシステムと呼びますが、このシステムの構成要素間の関係をチューニングしたり、システムの状態や動作を修正したり、形を変更したりして、最適な状態に近づけることをいいます。
システムの構成要素を「粒子」として設計に該当させると、各要素間の関係や全体の中の位置や関係を「波」として最適化を表現できます。
「相対性」と「対称性」について説明します。相対性は、物体の運動が観測者によって主観的に認識される認識事象であるということです。物体の運動は、ほかの何かとの間に、何らかの相互作用が生じるとき、はじめて具体的で物理的な意味を持つのであり、相対性には何らかの基準は必要がなく、たとえば観測者自身に対してどのように見えるかという、言ってみれば任意に決定できる主観的な認識のことであります。物体の運動の大きさはもちろんですが、その物体が静止しているのか、あるいは動いているのかという「運動の存在」についても、観測者の立場に完全に依存します。相対性には客観的な立場からの「静止している」、「運動している」、あるいは「速度○○である」と定義できるような、いわゆる「絶対運動」は存在しないとします。相対性におきましては、空間がバックグラウンドとして、いわば、絶対的な座標として何ら役に立たないことを、間接的に述べています。
対称性とは、ある物体に対して、変換をする、たとえば、左右反転や45°回転に関して、変換を適用しても変わらない性質のことをいいます。この変わらないこととは、それは物体の形のことを指します。
一般に、ある対象が、対称性をもつということは、指定された操作を対象に施しても、対象の形が変わらないことをいいます。なお、このような操作を「対称操作」とも呼び、また「変換」とも呼びます。たとえば、「球は回転対称性をもつ」と言えば、球は、その中心を通る任意の直線を軸にして、どんな角度だけ回転させても、もとの球とぴったり重なることを意味します。
物理学における対称性とは、物理系の持つ対称性、すなわち、ある特定の変換の下での、系の様相の「不変性」であるということができます。
不変性とは、ある量を一定にして変化させないという変換を数学的に規定することであると言い換えることができます。この概念は現実世界で観測される基本的な現象に対して適用することができます。例えば、部屋の中の温度が理想的に、どこでも一定であるとします。このとき、温度は部屋の中の位置に依存しないので、温度は測定者の位置の移動に関して「不変」であるといえます。
今までは、数学的にまたは、物理学的な定義としての対称性ということを説明しましたが、内部に対(つい)の構造を持っていて、いろいろな対称操作を加えられても元の姿から変わらないためには、多くの対称性を保有している必要があります。
相対性と対称性の組み合わせについて、人間にとって相対的な見方だけでも現実世界を認識することは可能ではありますが、対称性は、媒質を必要とする性質というか、「二重の条件依存性」にところで説明したように、相対性に追加可能な付随的な仕組み、そのものです。相対性と対称性の関係は、構造的カップリングです。この構造的カップリングというのは対になる両者の利益になることが前提です。両者は対立関係ではなく、相補的な関係です。相対性は基本的な仕組みですが、対称性の特性を加えることで円環的なシステムになります。
対称性を持った性質を、幾何学や物理学としてとらえるのではなく、変形を取り戻す能力として理解することもできます。自然の姿は近年、地球温暖化のためといわれていますが、四季の変化が実感として感じられなくなるようになりました。季節の変化は、春や秋の期間が短くなって、夏や冬の期間が長くなりました。地球温暖化の原因が過剰な経済活動によるものだとするならば、何らかの対策が必要なのかもしれません。ただ、気温の変化を歴史的な長さから考えると、ある時代は暖かくなったり、また氷河期が来たりして、必ずしも同じサイクルを繰り返してきたわけではありません。そういったことは自然に任せておけば良いのか、それとも人間が管理すべきことなのか意見が分かれるところです。
「死」と「復活」について説明します。人間は死後、肉体は消滅します。日本では多くの場合、火葬しますので、そうなります。最新の研究では、人間の心と肉体は、生存中には「身体化されている」と表現されていて、分けられない状態にあります。
ところで、心と魂は同一なものなのでしょうか。心は道徳の分野であるとか、心理学など一般的な分野で使われますが、魂は宗教的な分野で使われます。また、魂は、生前中における人格や行為について評価の高い人の心にも用いられます。死後、魂は体から抜け出して天国とか地獄へ行くと言われています。死後の世界は、おそらく物質で構成されたものではないので、あるとかないとか、科学的に説明できないものであると思います。
決定できないもの、根拠のないものを、生前中にあれこれ考えても致し方ないことなので、ここでは、「現実世界における死と復活」について考えてみたいと思います。 「復活」を「救済」ということと、重ね合わせて考えてみます。「生前中の復活」というと、死に瀕した状態からから免れるということになります。本当に死んでしまったならば、人間には手の施しようがなく、後は解釈の問題になります。
新約聖書・マタイによる福音書 27章
十字架につけられる
兵士たちは出て行くと、シモンという名前のキレネ人に出会ったので、イエスの十字架を無理に担がせた。そして、ゴルゴタという所、すなわち「されこうべの場所」に着くと、苦いものを混ぜたぶどう酒を飲ませようとしたが、イエスはなめただけで、飲もうとされなかった。彼らはイエスを十字架につけると、くじを引いてその服を分け合い、そこに座って見張りをしていた。イエスの頭の上には、「これはユダヤ人の王イエスである」と書いた罪状書きを掲げた。折から、イエスと一緒に二人の強盗が、一人は右にもう一人は左に、十字架につけられていた。そこを通りかかった人々は、頭を振りながらイエスをののしって、言った。「神殿を打ち倒し、三日で建てる者、神の子なら、自分を救ってみろ。そして十字架から降りて来い。」同じように、祭司長たちも律法学者たちや長老たちと一緒に、イエスを侮辱して言った。「他人は救ったのに、自分は救えない。イスラエルの王だ。今すぐ十字架から降りるがいい。そうすれば、信じてやろう。神に頼っているが、神の御心ならば、今すぐ救ってもらえ。『わたしは神の子だ』と言っていたのだから。」一緒に十字架につけられた強盗たちも、同じようにイエスをののしった。
イエス・キリストは、「全能の神」からゆだねられた福音を持ってこられましたが、大衆はイエス・キリストに「自分で自分を救う方法」を尋ねました。大衆は言いました、「他人は救ったのに、自分は救えない。イスラエルの王だ。今すぐ十字架から降りるがいい。そうすれば、信じてやろう。」この問いに答えることがイエス様にとって肉体をもって明かしされた最後の福音となりました。
心無い大衆が発言した、「神殿を打ち倒し、三日で建てる者、神の子なら、自分を救ってみろ。そして十字架から降りて来い。」、さらには、「他人は救ったのに、自分は救えない。イスラエルの王だ。今すぐ十字架から降りるがいい。そうすれば、信じてやろう。神に頼っているが、神の御心ならば、今すぐ救ってもらえ。『わたしは神の子だ』と言っていたのだから。」という言葉を発した、このタイミングが重要なのです。これらの言葉をイエス・キリストに浴びせたときには、イエス・キリストはまだ、生きていました。大衆は、なにも、「死んでから、生き返ってみろ」とは言っていません。
そして、イエス・キリストは復活されました。「自分で自分を救う方法」を自らが十字架にかかって最後に示されました。それは、「罪も犯していないのに捉えられて、裁判にかけられ、死刑の判決を受けて、十字架にかけられ殺されること」でありました。ただ、十字架にかかることは自ら予言されていました。これが真理の教えであるということは、イエス様自身が身をもって示すことしかありません。言葉だけでは嘘かもしれないと大衆は考えます。本当にそのように殺されてしまいました。しかし、死後、復活されたということは全能の神は、その行為が御心にかなったものであったと示されたと理解してよいのではないでしょうか。
さて、死の淵、つまり、終末に追い詰められた人間が、自らその窮地から脱出することができるでしょうか。病については、医学的、薬学的な方法で行うしかありません。その時代の医学的な技術によって救われるレベルも決まってくるでしょう。病気以外の場合では、だれか他の人がその困難を肩代わりしてくれるか、取り除いてくれれば救われるでしょう。それから逃げ出すということもありますが、自ら自分自身を救うとなると、自発的に行うことが基本的条件になります。
このことを言い表す、「天は自ら助くる者を助く」という、西洋の古いことわざがあります。意味は、「天は、他人に頼らずにひとりで努力する者を助けて幸福を与える。」というのがWebサイトで検索した結果です。何となくニュアンスはわかります。あまり人に頼ってばかりいるのは良くないことだ、ということでしょう。
これは西洋のことわざなので、天とは「全能の神」のことであると思います。もっと深読みすると、これは「自分自身が死後に復活するであろうもう一人の私が今、現実世界において助けてくれるので、その存在に気がつきなさい」という意味になると思います。
単一体の自己で自己救済を行う場合、パラドクスやトートロジーが発生してしまいしますので、そのために自己を二つに分割し、自己言及のコミュニケーションにおいて、パラドクス(逆説、背理、逆理)や、トートロジー(同語反復、同義語反復)に陥らないようにするために、自己を単一体ではなく、自己を相互に影響を及ぼしあう要素からなるシステムとして考えます。
自己を二つの要素からなると考えて分割して表現しました。この二つの併記を拡大解釈して、「コンティンジェンシー」と「ダブル・コンティンジェンシー」の組み合わせに特別な意味を与えました。ルーマンはコンティンジェンシーとダブル・コンティンジェンシーを、「構造的カップリング」と呼ばれる仕組みと考えました。
コンティンジェンシーの解釈は、「すべてのことが自分自身に帰結する存在」としました。ダブル・コンティンジェンシーの解釈は、「他の人とのかかわりが避けられない存在」としました。そのほかにも、「自分で実現できる自己」と「他人に委ねなければ実現しない自己」です。また、別の表現をすると、「現実世界に存在するための自己」と「社会に属するための自己」とも表現できます。簡単に表現すると、「プライベートな自己」と「パブリックな自己」と言い表すことができます。
結論として、「死」と「復活」はこのような意味になると思います。現実世界において、生物における死は、必然性を持った要素であり、避けることができません。人間はだれでも必ず死ぬのだけれども、生存中であるならば、たまたま遭遇した事故ともいえるような困難な状況に陥った場合、救われる仕組みが存在していて、再び健全な状態に戻ることができることに気づくことは重要なことであると思います。組み合わせの中に、「最後まで」と「できるところまで」という組み合わせがありますが、右側の欄の、「できるところまで」という言葉には、生の内に踏み留まるという意味もあると思います。
表にはない組み合わせですが、「目的」と「理由」につきまして説明します。たとえば、行為ということについて考えてみると、左側の欄の「目的」だけ与えられると他者から命令されたことになりますが、それに右側の欄の「理由」が合わせて与えられると、たとえ他者から指令されたことでも実際の行為者による自発的な動作ということになります。実際にコミュニケーションするのは「目的と理由」です。「目的と理由」という組み合わせは「自発的な行為」を生み出します。このコミュニケーションには「目的と理由」以外に要素はなにも必要がなく、閉鎖されています。もしも、「目的」だけが他者に与えられると、「理由」の項目には本来入るべきことではないことが入ります。この場合「命令」です。これでも「目的と命令」となり、両者はコミュニケーションして行為は行われますが、本来の要素ではありません。「目的と理由」が望ましいと思われます。オート・ポイエーシス・システムでは「自発性」が基本です。「理由」は、人間に自発性を引き起こす仕組みとも考えることができます。(2023/3/24追加・赤の字)