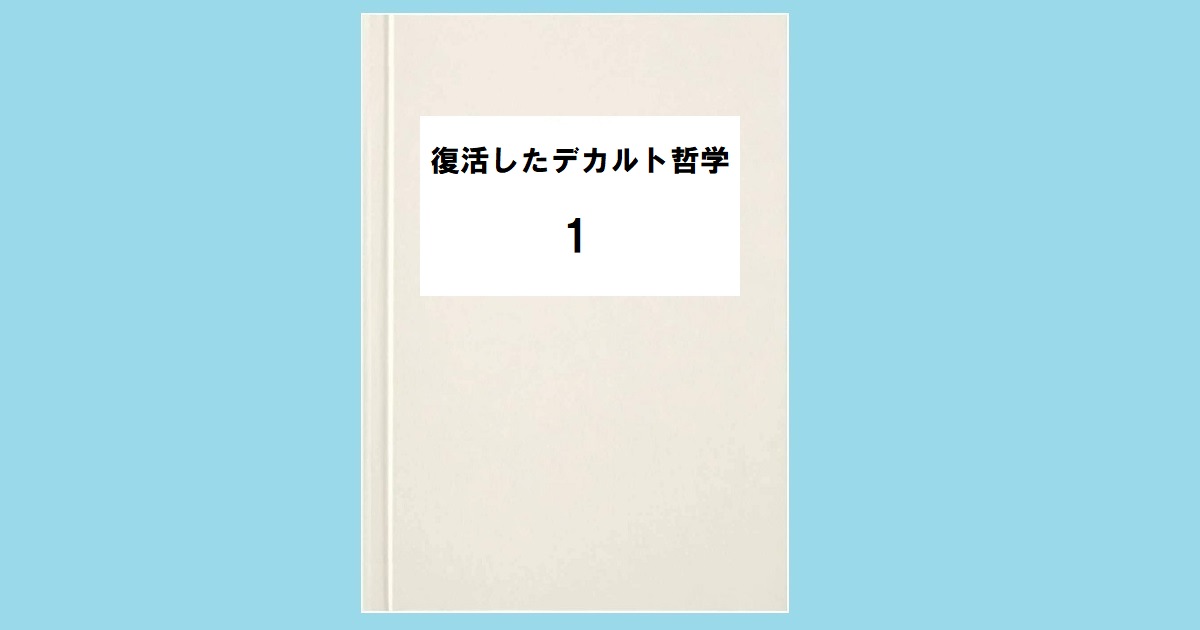(デカルトの哲学を現在の視点で再考して得た真理 1)
- ルネ・デカルトの哲学を現在の視点で再考して得られた真理
- ヨーロッパで17世紀に起きた科学革命について
- 科学革命という言葉
- 科学革命の意義
- 科学革命の意味
- 科学革命が再生させたもの
- ルネサンスの役割
- ギリシア哲学の復活
- 中世思想と科学革命
- 科学革命に賛同する人々
- 科学革命には興味がない人々
- スコラ哲学の教え
- 思惟するだけのスコラ哲学
- スコラ哲学の求めるもの
- スコラ哲学は聖なる世界を求めます
- 宗教改革の役割
- ガリレオの世界観
- 科学革命の時代背景
- 科学革命の到来
- ガリレオの功績
- 地動説の正当化
- 抽象的数学と具体的自然学の同一化
- 異なる実験の考え方をする大陸とイギリス
- イギリスの実験方法
- 実験方法の違いは、宗教が起源
- 実験方法についての考察
- ロンドンの王立協会の役割
- ロンドン王立協会の成功
- 機械論哲学の登場
- 科学革命における数学の役割
- デカルトの世界論という著作
- デカルトの役割について
- デカルトの力学的構想
- 数学的自然学の形而上学的基礎づけ
- ハーベーとデカルトの生理学
- 自由意志の存在について
- 私の意見
ルネ・デカルトの哲学を現在の視点で再考して得られた真理
第一部
第一部で引用させていただいた文献
・一七世紀科学革命(ヨーロッパ史入門) 岩波書店(出版社)
ジョン・ヘンリー、東 慎一郎 (翻訳)
・科学革命(日本科学史学会編) 森北出版(出版社)
湯浅光朝、三田博雄、渡辺正雄、青木靖三、伊東俊太郎
・西洋哲学史 Ⅲ 講談社(出版社)
神崎 繁、熊野 純彦、鈴木 泉
・科学の世界と心の哲学 中央公論新社(出版社)
小林 道夫
・デカルト 清水書院(出版社)
伊藤 勝彦
ヨーロッパで17世紀に起きた科学革命について
科学革命とは、ヨーロッパ史において近代科学の概念的、方法論的、制度的な基礎が一応確立した時期を指して、科学史家たちによって与えられたものです。その正確な時期については科学史家によって考え方が異なりますが、その中心は17世紀であり、16世紀はさまざまな側面でそれが準備された時期、また18世紀はその成果の整理と地固めの時代であるとされています。
近年、中世科学についての研究が明らかにしたこと、それは中世の自然哲学が科学革命の礎石を築いたことです。そのため我々は科学革命の礎石を築いた中世における時期と上部構造の建設期とを時期的に区別できるのです。かつて中世は科学にとっては不毛と停滞の時代であったと思われていたのですが、連続主義の立場から書かれた多くの優れた研究のおかげで、現在では中世の思想家の残した成果を否定する研究者はいなくなりました。特に天文学、宇宙論、光学、運動論といった数学で表現できる学問、そして自然法則の観念や実験的方法の発展において、注目すべき貢献が中世になされたことがわかってきました。
ガリレオが運動論と自然哲学を統合したことで、彼が新しい運動論と呼んだものが生まれました。これは今日でも後世の理論の発展に大きく影響したと考えられています。同様に、ルネ・デカルト(René Descartes)(1596~1650)の自然哲学は大きな影響力を持ちましたが、それは自然哲学に幾何学的推論のもつ確実性を与えようという試みから出てきたものです。またアイザック・ニュートン(Isaac Newton)(1642~1727)の新しい自然哲学は、その主著の題名が示すとおり、数学的原理に基づくものでした。
科学革命において、何が起きたのでしょうか。簡単に言うと、中世においては、自然哲学は数学や実験とは関係ないものでしたが、科学革命がおきると、これらの異なった種類の自然研究方法と自然哲学が融合し、我々の考えるような科学に近いものが生まれたと要約できます。
初期の近代が問題となっている場合、「科学」の代わりに「自然哲学」という用語を用いることは、決して望ましいこととは言えません。「科学」と「自然哲学」は同じ概念ではありません。科学革命が革命的であった理由の一つは、この時期を通じて自然哲学が以前とは別のものに変貌し、我々の考えるような科学の姿に近づいたことにあります。
科学革命という言葉
デカルトは、本当の学問(philosophie) を全体として1本の樹にたとえました。その根がメタフィジクス(形而上学)で、幹がフィジクス(物理学)で、その幹から出ている枝たちが、いろいろな科学(sciences)としています。これはデカルトの学問の樹と呼んでいいでしょう。この樹の枝たちにあたる諸科学として、デカルトは、医学と力学と道徳学を挙げています。道徳学とは、他の諸科学の全体の知識を予定してのもので、知恵の究極のものという意味です。デカルトの、この説明の仕方にはヨーロッパの学問思想史の歴史の流れがあらわれています。学問全体をつかんで「科学」といってしまうことは、デカルトの学問の樹でたとえると、物理学や力学や医学などを全部まとめて「科学」と呼ぶことは意図されていなかったと思います。
ここでは、今から300~400年前、すなわち16~17世紀のガリレオ・ガリレイ(Galileo Galilei)(1564~1642)からニュートンの時代までを討論の対象にしています。17世紀を中心として起った近代自然科学の成立という事態を適切に表現するものとして、科学革命という看板をかかげています。今から300~400年も昔のヨーロッパでの事件を、今ここで論じる意義を少し解説しておきましょう。
科学革命の意義
現代が技術革新の時代であることを否定するものは、どこにもありません。20世紀の科学の本質を本当によく理解するためには,その始点にさかのぼらなければなりません。激動する現代の秘密を解く鍵は、16~17世紀の科学史の中にあるといえます。科学や技術の発展の歴史をぬきにした歴史は意味がありません。科学時代の歴史は、科学史が中心になるべきです。その科学史の中で、科学革命の考え方は、全体の骨組みを成すものです。
我々が生活しているこの現代社会において、原子力や人工衛星によって象徴的に示されている現代科学の巨大な力は、まさしく圧倒的というべきものであり、いかなる文化的、社会的、政治的事象もこの現代科学の甚大な影響を離れて語ることはできません。それは文字通り現代文明の中心であり、人間の将来の運命も、この科学の成り行き次第にかかっているといっても決して過言ではないでしょう。今や人類の運命ともなった、この科学の圧倒的な勢力も、実は17世紀を中心として起った一回限りで起きた歴史的事件である、「科学革命」に由来しているのであり、現代の文明というものもこの革命の直接的結果にほかならないでしょう。ここで初めて現代と直接連なるところの「近代的なるもの」の原型が作られたのです。
ケンブリッジ大学の著名な科学史家であったハーバート・バターフィールド(Herbert Butterfield)(1900~1979)は、科学革命の意義を強調していいます。この革命は中世のみならず、古代世界の科学における権威を覆しました。スコラ哲学を崩壊させただけでなく、アリストテレス(Aristotle)(紀元前384~紀元前322)の自然学自体も破壊に導きましたが、それはキリスト教の勃興以来のあらゆるものに抜きんでて輝きます。科学革命は、人間の習慣的な知的営みの性格を変革し、物理的宇宙の全構図と人間生活そのものの構造を変換させながら、近代世界と近代精神との真の起原となりました。彼によれば、ルネサンスや宗教改革を「近代」を始める従来の歴史的区分は適切ではなく、今や「科学革命」こそ、近代を近代らしくさせた決定的な契機として位置づけられねばならないとしています。これこそ古代や中世には存しなかった自然に対する新たな知的態度を形成し、そこに一つの根本的な知的転換を遂行することによって、その後の人間の後戻りを許さぬ無限の進歩の礎を築いたのです。そして、我々は、この進歩の過程の途上に位置しながら、300年前に行われた、この転換のはかり知れない意義を知ろうとしています。科学革命の最終的な意義は、文明そのものを可能にした農業の発見よりさらに重要ではないでしょうか。なぜなら、科学には無限の進歩の可能性を内蔵しているからです。
科学革命の意味
さて、科学革命の歴史的意義は上述の通りであるとして、次に、いかなる意味において科学革命は「革命」と呼ばれるのでしょうか。この科学革命の革命たる科学史的意味はどのようなものなのでしょうか。そもそも近代科学の成立を真に革命的事件として把(とら)えるために、最初に考えなければならないことは、ギリシア科学とか中世科学とか、いわれた場合、その「科学」の意味するものが、今日の意味での科学ではなく、それとは異なった世界観、 自然観、価値観の下に考えられた体系であり、その目的、志向、方法、構造において本質的に異なったものであったということを知らなければなりません。
そして科学革命以後において、はじめて今日の科学と同質の科学の概念ができ上ったのであり、今日の科学の概念や方法がそのまま古代・中世にも存していたとすることは根本的に謬(あやま)りであるということです。
イギリスの科学史家であるA・R・ホール(A. Rupert Hall)(1920~2009)によれば、「科学革命」の進行の過程において、初めて近代的な意味における「科学的態度」というものが形成されました。そこに新たな自然認識の原則的方法、いわゆる科学的方法が確立され、その後の科学は累積的な性格を持った、といいます。その新たな科学的態度、方法とは、単に観察のみならず、構成的実験の厳密な基準を要求しました。さらに自然認識の領域から霊的なもの、隠れた質のようなものを追放し、その対象を経験的現象に限りました。また十分な実験的証拠のある理論と推測による仮説や単なる思弁を厳密に区別することも必要です。また理論の裏付けとなる組織的実験が数字的な量的取り扱いと固く結びついていることが重要でした。初めて形成された、自然認識である「科学的方法」は、その後の科学の内容がいかに発展しようとも少しも変えられることなく、その後の科学的知識の累積的前進を可能にしました。
物質・時間・空間・因果性の観念の更新がいかに大きくとも、それは科学の「内容」の更新であって、科学の「構造」そのものの更新ではありません。1800年以降において科学の進展は、後の発見が前の発見を包み込むようにして行われるようになりました。すなわちニュートンはアルベルト・アインシュタイン(Albert Einstein)(1879~1955)によってその誤りが示されたのではありません。またアントワーヌ・ローラン・ド・ラヴォアジエ(Antoine-Laurent de Lavoisier)(1743~1794)はアーネスト・ラザフォード(Ernest Rutherford)(1871~1937)によってその誤りが示されたのでもありません。科学的命題の定式化は変えられ、その適用の限界が認識されますが、その命題が頭初正しいとして見出された領域内では依然としてその妥当性を保っています。
一般に科学革命以後においては,後の理論は前の理論に何ものかをつけ加えるか、またはそれを包み込むかによって、累積的に進んでいきます。しかし、「科学革命」がまさに起りつつある場面においてはそうではありませんでした。アリストテレスのスコラ哲学の力学が打ち破られて、ガリレオの力学が成立する場合、後者は前者に何ものかを付け加えれば出て来るものではなく、後者は前者を包んでもいません。実験的方法と数学的方法が結びついた、新しい自然認識の方法が登場し、自然の正しい基本的構図が示され、古代から中世を貫いて存していたコスモス的世界像が根抵から覆(くつがえ)されました。
ジョン・デスモンド・バナール(John Desmond Bernal)(1901~1971)の言葉を借りていえば、この科学革命においては、ギリシア人からひき渡され、イスラム教とキリスト教の神学者によって固く守られていた知的仮定の全構造が覆され、根本的に新しい体系がこれにとって代ったのです。アリストテレスの宇宙の位階構造がニュートンの機械論的世界像に道を譲ったのです。
科学革命が再生させたもの
科学革命は、誤った理論や事実を修正しただけではなく、ギリシア以来千数百年にわたって支配し続けた古い概念体系の枠組そのものと、それに密接に結びついた古い世界観や自然観、そして価値観を一挙に粉砕し撤去しました。そこに一つの根本的な知的転回を遂行することによって、全く新しい自然認識の礎石をつくり上げ、今日我々が「科学的方法」と呼んでいる新たな自然探究の方法を確立しました。この転回によって初めて我々の意味するものと同質の科学の概念が成立したのであり、その後の科学の発展は、ここにおかれた礎石の上に、この科学的方法によって開拓されていく認識を、つみ重ねていくことができるようになりました。力学においてはガリレオからニュートン以来、天文学においてはニコラウス・コペルニクス(Nicolaus Copernicus)(1473~1543)からヨハネス・ケプラー(Johannes Kepler)(1571~1630)以来、また化学においてはロバート・ボイル(Sir Robert Boyle)(1627~1691)からラヴォアジェ以来、このような累積的前進が保証されました。ここに科学革命の「革命」といわれる意味があるのです。
科学革命は単に過去の思想的伝統の復活には帰せられず、それは一つの全く新たな知的態度の誕生であり、この「新しさ」を可能にする近代の独得の要因がなくてはなりません。それはすなわちルネサンス以来の技術的実践の蓄積であり、この技術を理論的に理解することが、近代科学の特色なのです。単に技術的実践が高まることで、科学革命が生じたとするならば、正しく事態を把えていないと私は思います。
なぜルネサンスの技術家たちは近代科学を作ることができなかったのでしょうか。ガリレオ、デカルト、フランシス・ベーコン(Francis Bacon)(1561~1626)、ボイルは、大学において十分な教育を受け、また過去の思想的遺産に通じており、かつ近代の技術的問題に関心を持っていました。なぜ彼らによって、初めて近代科学は成立したのでしょうか。それは、科学革命はこのギリシア以来の「理論的遺産」と中世末期以来の「技術的実践」とが独特な形で結びつき、そこに全く新たな自然に対する探究方法がつくられたことによって生起したといえるでしょう。ギリシア時代や中世において、「合理的思考」と「技術的実践」は、互いに分離していました。それが科学の生じることができなかった理由であると私は思います。たとえばギリシアでは、前者は哲学者の専有物、後者は奴隷のものというように分離していたし、また中世においても前者は神学者の思弁に属し、後者は教養のない職人のものでありました。
現在の「科学革命論」の一つの問題は、この学者的伝統に属する理論的遺産と職人的伝統に属する技術的実践の結合、連携、その相互滲透の具体的なあり方を追求し、この二重構造が一元化される場面を明らかにすることです。そうすると、ここに初めて近代科学革命の独自な「構造」が開示されます。「数学的方法」と「実験的方法」の結合という科学革命の方法論的産物もこのことと深く関係します。なぜならば前者はギリシア以来の理論的遺産の中にあり、後者は近代の職人の技術的実践のうちに鍛え上げられたものだからです。
職人的技術は理論的につじつまが合えばよいのではなく、実際に物を作って実験的に試してみなければ一歩も進めません。しかし職人たちは、実験的事実を長年の経験ということに留めるだけで、それらを普遍的な理論にすることができませんでした。それを成したのが合理的理論によって武装され、かつ技術的実践に関心を持った近代の学者たちでした。我々はこの結合、統一の大まかな脈絡をたどってみましょう。
バターフィールドは、近代科学の起源についての著作を書き上げた後、科学革命が近代世界と近代精神の真の生みの親であると記しました。また科学革命の意義は、キリスト教の出現以来、他に例を見ないほど大きなものです。しかし科学革命の原因について知りたいときは、ルネサンスと呼ばれるあのヨーロッパ史上の大きな変化の中にそれを探さなければなりません。科学革命は、ルネサンスを抜きにして語ることはできません。科学革命は宗教改革と同様に、ルネサンスの生み出したひとつの結果として見ることができます。
ルネサンスの役割
ルネサンスは、知識人を歴史への関心を深めさせました。自らを古代ローマ、もしくは古代ギリシアの知的栄光を相続する者として位置づけるという意識が誕生しました。つまり彼らの関心は、かつて人間によって超えられたことがなく、また多くの人にとっては人間が超えることのできないものであった古代人の知恵を、現代に復興することでありました。ヨーロッパ中の修道院の図書室を順々に調べ、修道僧に読まれることなく埋もれていた古代の写本を数多く発見した者もいました。これらの写本は印刷技術のおかげで保存され、比較的簡単にヨーロッパ中の読者へと提供されました。現代に生きる我々が手にしている古代の著作は、ほとんどがルネサンスの人文主義者によって収集保存されたものです。
当時の人文主義者の受けたインパクトを知るには、ヨーロッパの大学で当時教えられていた伝統的アリストテレス主義に対する影響を見てみればよいでしょう。たとえば、人文主義者たちが再発見したディオゲネス・ラエルティオス(Diogenes Laertius)(3世紀ごろ活躍)の『哲学者列伝』や、マルクス・トゥッリウス・キケロ(紀元前106~紀元前43)(Marcus Tullius Cicero)の『神々の本性について』を読めば、中世には哲学の最高権威とされていたアリストテレスが、古代唯一の哲学者ではなかったことが挙げられます。さらにアリストテレスは古代に最も尊ばれた哲学者ではなかったということが一目瞭然でありました。続いて、ほかの哲学者の書物、プラトン(Plato)(紀元前427~紀元前347)や新プラトン主義者、ストア派、エピクロス派の著作の発見は、当時支配的であったアリストテレス主義とは異なった哲学的見解について学ぶ上で格好の著作でありました。このようにして復輿された古代哲学の中には、後期アカデメイアの懐疑主義があります。後期アカデメイアは、プラトンの創立した学校として畏敬の対象でした。数学や魔術思想についての著作も復興されたことで、状況はさらに複雑になりました。アリストテレスは数学を重視しなかったのに対し、プラトンは数学を確実な知識への道筋として考えていました。数学への関心が急激に高まるにはそれだけで十分でした。
古代魔術思想の著作には、イアンプリコス(Iamblichus)(245~325)やテュロスのポルピュリオス(Porphyry of Tyre)(234~305)などによるものがありました。中でも、モーゼ(Moses)(紀元前16世紀または、紀元前13世紀ころに活躍)と同時代の古代の知者と考えられていたヘルメス・トリスメギストゥス(Hermes Trismegistus)によるとされた書物のおかげで、魔術こそが最古の知恵を伝えるものと考える者が増えました。このような事情で、魔術もまた正当な意味における知識として考えられるようになったのです。教会はもとより悪魔学との関係から魔術に反対していましたが、その抗議にもかかわらず、魔術への関心は続いたのです。古代の知識が提供されたことで、知的状況は混迷を深めたましが、それは可能性を秘めた混迷でありました。結果として、ルネサンスにおいて伝統的なアリストテレス主義的自然哲学がその知的権威を失い、新しい自然哲学が台頭しました。また信頼に足るほどの確実性をもった知識は、どのようにして発見され、確証されるべきかという問題についても新しい考え方が登場した時期でした。当時の権威は誤謬に満ちたものであり、頼りにならないものとして見られるようになりました。懐疑主義のような新しい哲学体系が出現したり、数学や魔術のような哲学以外のアプローチも注目されたりすることで、従来からの知識だけを追求するということが危機に瀕しました。その結果、各自が自分自身の経験と努力だけを頼りに真理を発見することに力点がおかれるようにもなったのです。
ギリシア哲学の復活
ルネサンス期において古代の著作が復興されたことは、さまざまな知的影響をもたらしましたが、魔術的伝統への関心の高まりもそのひとつです。その背景には、古代の新プラトン主義的著作が読まれたということがあると思います。
また、ニュートンは錬金術師でもありました。ニュートンの錬金術研究は、長い間その科学的な仕事とは無関係なものとして片づけられてきましたが、近年になりそれが彼の物質理論に影響を及ぼしていることがわかってきました。ベティー・ジョー・ダプズ(Betty Jo Teeter Dobbs)(1930~1994)やR・S・ウェストフォール(Richard S. Westfall)(1924~1996)の強調するところによれば、ニュートンの自然哲学の基礎に粒子間引力および斥力という隠れた力が存在するという事実は、ニュートンが錬金術的な思考様式に親しんでいたからこそ可能でありました。
隠れた力に対するニュートンの確信を説明するために、錬金術の知識だけでは不十分であるにしても、錬金術がニュートンの科学思想の一面を知る上で重要です。1675年に王立協会に送られた初期の論文「光についての仮説」や『光学』(第三版1717年)からは、ニュートンは明らかに錬金術における光の理論に多くの根拠を得たことが伺えます。錬金術では光は物質と相互作用し、それにある種の能動性を与えることができると考えられていました。ニュートンの引力の観念の起源は別のところにあるかもしれませんが、物質には、ある種の能動原理が潜在的に備わっているという考え方は、錬金術の伝統から直接とられているように思われます。そういった能動原理が万有引力の原因と考えられていた可能性もあります。
このプラトン主義の内部で、粒子論的な物質観が発展しはじめます。たとえば、ニュートンが物質の粒子的構造を信じていたことは確かであり、また光に関しても、粒子性と波動性の間で動揺しながら次第に粒子性に傾き、それらの粒子に万有引力が内在するという考えに近づいていました。ニュートン自身は、実験的もしくは理論的に確定しえないような場合には、慎重にも反対の解釈の余地を残していましたが、18世紀の追随者たちはこれを解釈し直して一層厳格な形での原子論の方に推し進めました。しかし、『プリンキピア』が描いた原子からなる自然像には、まだ神による「最初の一押し」を容れる余地が残っていました。
中世思想と科学革命
ガリレオは、1632年に公刊された『二大世界体系についての対話』、いわゆる『天文対話』のなかで、自然落下運動法則を述べるはじめのところで、つぎのような対話を展開しています。ガリレオを代弁するサルヴィアチ(Salviati)が、「自然落下運動が直線であることを知るだけではまだ十分でありません。それが常に同じ速さが保たれるのか、それとも減速するのか、加速するのかを知らなければなりません。」と述べました。彼は、これが加速運動であることを明らかにしたのち、次に「加速運動であることを知るだけではまだ足りません、といいます。さらに彼は、加速運動がどのような比率で成されるかを知らなければなりません、といいます。最後に、この問題がすでに哲学者や数学者の誰かによって明らかにされていたとは思いません。」と述べています。このようにガリレオは、自然落下運動の加速度率というものが、それまで誰によっても研究されたことがなく、解かれたことのない、きわめて重要な問題であることを強調するのです。
これに対して、アリストテレスのスコラ学徒を代弁するもう一人の対話者、シンプリチオ(Simplicius)はつぎのような反論を展開します。「哲学者は主として普遍的なことがらに専念します。彼らは定義と、最も一般的な基準を見いだします。好奇心の対象であるような、ある種の微妙なことや些細なことは数学者に委ねます。続けて彼は、アリストテレスは、運動一般がどういうものであるかについてすぐれた定義を下しました。また彼は、位置運動についてはその主要な属性である、自然的であること、暴力的であること、単純であること、合成であること、均等であること、加速することを示すことで満足しています。さらに彼は、加速運動については、加速を根拠づけることで満足し、そのような加速度率と他のより特殊な出来事の探求は力学の専門家や他の身分の低い職人に委ねます。」このように述べました。彼は、ガリレオが自慢しているような自然落下蓮動の加速度率の研究などは、哲学者が成すべき研究ではないことを主張し、間接的にアリストテレスを弁護しているのです。
科学革命に賛同する人々
科学革命の起源には、人文主義者の改革思想が主要な地位を占めていると言わざるをえません。科学革命の特徴を三つ挙げて見ます。
- 自然的世界の働きを理解するのに数学を用いることです。
- 真理発見のために観察と実験とを行うことです。
- 社会的評価の低い数学的職人や魔術師しかもっていなかったような知識の有用性という考え方を、自然的知識にまで広げるということです。
科学革命を起こすための知識が人々に根づくためには、ルネサンス人文主義が必要でした。
数学は自然的世界を記述するだけでなく、説明するためにも用いられるようになりましたが、それは天文学の領域に限られませんでした。当時、交易の発達や植民支配の拡大を背景に、探検への関心が高まっていました。それは航海術、測量や地図製作といった実用数学が関心を集めることにもつながりました。主導的知識人たちはこれらの分野にも目を向け始め、また職人は社会的にも知的にも上昇することが可能となりました。さらには名門階級の中からも数学に関心をもつようになる者が出現する原因となったと考えられています。
イエズス会もその積極的な教育活動を通じて、自然哲学への数学の導入に貢献しました。彼らが数学教育を重視したことは、数学が自然哲学や形而上学と並んで、学院で教えられたことからわかります。イエズス会の教育活動は歴史上重要です。その学院での数学に対する姿勢は、数学者の地位向上という大きな潮流を反映しています。また多くの生徒たちにも数学の重要性を印象づけました。
少なくとも二人の思想家が、イエズス会の学校で学び、その後世界像の数学化に独自の仕方で貢献しました。それはマラン・メルセンヌ(Marin Mersenne)(1588~1648)とデカルトです。メルセンヌは1611年にミニム修道会の僧となり、修道会の支援のもと信仰を擁護するために生涯を学問に捧げました。
メルセンヌも懐疑主義には反対であったので、数学を最も確実な種類の知識と考え、それを通して人間は神のもつ知識にまで到達することが可能であるとしました。メルセンヌは精力的に執筆し、またほかの数学者にもその研究を出版するよう促した。それ以上に彼が熱心だったのは、ヨーロッパ中の著名な学者と書簡をやりとりすることでした。同じような分野で仕事をしている学者にとって、メルセンヌのネットワークは共通の情報源となりました。彼は最新の研究の結果を必要としている別の人のところへと送ってあげました。同時に、メルセンヌ自身の考えや、哲学にとって数学が非常に重要であるという彼個人の信念も、この個人的情報網を通じて広めました。
科学革命には興味がない人々
さて、我々がここで問題にしようとするのは、どのようにしてガリレオが、アリストテレスのスコラ学徒の保守的な殻を打ち破り、輝かしい近代科学上の業績を成しとげたのかということを歴史的に、また具体的に述べることではありません。我々がここで問題にしたいことは、当時の哲学者や思想家は、どうして独創性や新しさを高く評価すべきガリレオの自然落下運動法則の定式化のような作業を自分ではせず、身方の低い職人に任せようとするようなことをしたのか、ということです。
我々はまた別な例をあげてみましょう。1609年、ガリレオはオランダで、遠くのものを近く見えさせる眼鏡が発明されたということを伝え聞き、自分でもその製作を志ざし、望遠鏡の製作に成功しました。ガリレオは直ちにこれを空に向け、当時としては驚くほど多くの発見をしたのでした。中でも世間の人びとを驚かせたのは、月にも山のあること、また木星が地球と同じように月、衛星を、しかも四つも持っていたことでした。アリストテレスのスコラ学説によると、月も含めての諸天体は、大地とその同辺を形づくっている地、水、空気、火の4元素とは異なった、より高度な第5元素であるエーテルからできているとされ、そしてその形体もまた、この元素にふさわしく最高度な形体、完全な球形をしているとされていたのでした。したがって天体の一つである月に、山や谷があるなどということは全く馬鹿げた話であるとされていたのです。
スコラ哲学の教え
このような、一般の人びとの素朴な驚きや強い好奇心に対して、スコラ学者たちがどのような態度をとったかというと、彼らはこのような新しい発明、発見に対してははなはだしく批判的でした。彼らのある者は、望遠鏡の話を聞くと、自分ではのぞいて見もしないで、そんなものは新しい発明でも何でもなく、すてにアリストテレスはそれについて記録している、といいました。それは、アリストテレスはテキストのある箇所で、深い井戸の底からは昼間でも星の見えることを記録しています。その理由として、井戸の中に溜まった蒸気によって人間の視力が強められることを挙げています。この深い井戸ということから、望遠鏡の筒を思いつき、井戸の中の蒸気ということから、レンズの考えが思いついたと解脱したのでした。これは、今日になってみれば、まったくこっけいな笑いばなしではありますが、しかしこれはガリレオが誇張し、創作したものでなく、当時に実際にあった話だと信じられています。
思惟するだけのスコラ哲学
我々には、アリストテレスのスコラ学徒がガリレオの作った望遠鏡をのぞこうとしなかった理由を、ガリレオの言うように、単に臆病であったからとかいう性格のみに帰することはできないように考えられるのです。これだけでは十分でなく、アリストテレスのスコラ学徒とガリレオの学問に対する態度の違いには、性格的なものよりさらに大きく深い、何かの違いがあったように考えられます。加速度率の研究、あるいは望遠鏡をのぞくことは、それほど大した手数のかかることでもなければ、恐ろしいことでもなかったでしょう。したがってこの研究をやらず、望遠鏡をのぞかなかったのは、スコラ学者がそれらの行為を面倒がってやらなかったとか、あるいは単にやりたくなかったからというよりも、やる必要を感じなかったからにほかなりません。その必要を感じず、関心がなかったからに違いないのです。それではなぜ、チェーザレ・クレモニーニ(Cesare Cremonini)(1550~1631)を代表とするスコラ学者たちは、そのような必要を感ぜず、関心を持たなかったのでしょうか。
スコラ哲学の求めるもの
ガリレオにとって、彼の長年にわたる研究の際の最大の関心事はいうまでもなく、物体の運動諸法則の定式化ということでした。彼自身の言葉から簡潔にいうと、「自然の出来事についての具体的な知識を得る」ことでした。これがガリレオの「科学」の最大、究極の目標だったのです。しかし、スコラ学徒たちの「科学」の最大、究極の目標は決してそうではありませんでした。スコラ学徒たちの最も大きな研究課題は、一言でいうならば、人間と神との関連であり、このつながりを明らかにすることでした。被造物である諸存在物、特に人間と、これらの被造物の創造主としての神とのつながり、この両者の間に成り立つ秩序がその研究の対象であり、この秩序の明快な叙述がその研究課題でした。アリストテレスの諸テキストもまた、この面でもっとも深く研究され、開発され、利用され、またある意味では歪曲されて、カトリック信仰の位階制の枠の中に組込まれたのです。そして「自然」というものも、この創造主としての神の敷いた秩序が、被造物の中での現われ方、つまり本性として捉えられ、この「本性」ということこそ、「自然」のもつ本来の意義だったのです。自然とは、理性を備えた存在物である人間が、自らの本性を自覚し、この自覚を通して最高善、神に向って努力する、この努力の一つの契機なのです。したがって、今日我々が思うような、人間の思惟や意思から独立した唯物論的な意昧での自然は、神の被造物として、それ自身の秩序、本性は備えていても、これを自覚する理性は備えていません。従って、最高善である神に向っての意識的な努力は成しえないものとして、そのようなものは人間のような理性を備えた存在よりは一段低く評価しました。したがって人間に始まり神に終わるカトリック信仰の世界の中では、唯物論的世界のものは研究に値するものではなかったのです。
スコラ哲学は聖なる世界を求めます
自然落下連動の加速度率が明らかにされたところで、人間と神との関連をめぐってのさまざまな重要課題の解決に対して、どれほどの寄与がなされるのでしょうか。また放物体の描く曲線が、円でも直線でも両者の複合でもなく、放物線であることが証明されても、人間の行為の内に見出される悪の起源という、きわめて重大な難問に、どれだけの光が投じられるのでしょうか。人間の魂のどれだけの部分が不滅であるかについて研究を深めることの方が、望遠鏡などという、わけのわからぬ玩具にうつつをぬかすよりも、はるかに緊急に取り組むべきことであり、また身近なことでもありました。このように考えてきた場合、ガリレオと同時代の哲学者たちがガリレオの科学の偉大さを、またその重要性を認めることができなかったのは、彼らがすべてスコラ学徒の末期の二流、三流の学者であったからであるということよりも、彼らもまた、輝かしい光を投じていた全盛期におけるスコラ学の学説と同じものを信奉し、その世界観に閉じこもっていたためであると考えた方がよいのではないでしょうか。
宗教改革の役割
このような新しい態度は、宗教改革においても見られます。マルティン・ルター(Martin Luther)(1483~1546)は、教皇のみならず地域の司祭に従うことすら拒否しました。「全ての信徒が司祭であること」を唱えたルターは、自分で聖書を読み、自分で神の思し召すところを感じ取るようプロテスタントを促しました。これは聖書の権威を再確認しただけに見えるかもしれませんが、実際はそれまでにない新しいことでした。それまでは、ローマ・カトリック教徒は聖書を読むのではなく、司祭に相談して導いてくれるのを待つべきだとされていました。ルターにとってはこのような司祭の権威は誤ったものであり、各自が自ら聖書に戻ってその真理を発見するべきだと訴えました。16世紀には自然的世界は「神のもう一冊の書物」に譬えられることが多かったのですが、ここには宗教改革と科学革命の類似性が見られます。科学革命においては経験と観察が真理発見の方法として強調する態度が見られます。自然の研究に対するこのような新しい経験的あるいは実験的な態度が出現するには、ルネサンスが引き起こした変化を経なければならなかったことは疑いがありません。
ガリレオの世界観
スコラ学徒たちの世界像はガリレオのそれとは異なっていました。それでは、ガリレオのもっていた世界像とはいったいどういうものであったのでしょうか。ガリレオ自身の書いた書簡や著作から、彼の抱いていた世界像を明確な形でとり出すのは非常に困難です。しかし、彼のことばの断片などから推察すると、特にガリレオが自分の地動説が聖書のことばと矛盾するものでないことを主張しています。例えば、1613年12月21日づけの数学者ベネディクト・カステリ(Benedetto Castelli)(1578~1643)あて書簡、および1615年のクリスティーナ・ディ・ロレーナ(Cristina di Lorena)(1565~1637)あての書簡で書かれている文章には、「聖書のことばは、人間の魂の救いと信仰を固めるのに必要ではあっても、自然論とは直接に関係を持たない」と書かれています。この文章から推論すると、ガリレオがすでに人間と自然との世界、かつてはカトリック信仰の中で一体であり、上下の関係を持っていた二つの世界が完全に分たれ、それぞれ独自の存在を主張するようになったと考えていたのではないかと思われます。このような意昧で、我々はガリレオの、自らは明快な哲学体系としては述べなかった世界像を、デカルトの二元論の内に、その代弁者を見出すことができると思います。
科学革命の時代背景
科学革命が成就されたのは、実験的方法が成立するによって成されたものであり、17世紀は実験が近代化された時代といわれています。この実験という方法はニュートンによる経験主義的態度とデカルトによる合理主義的態度の結合によりはじめて成立しました。17世紀の現実とは、その分裂であり、矛盾であり、かぎりない試行と錯誤であり、多くの認識の混乱を生み出していました。いわば、実験における人間の感覚と理性は、協力し合うよりもはげしく否定し合い、おろかな結論を多く出させるものでした。
方法の矛盾は深刻な懐疑へと移行し、試行の錯誤は絶望へと転化します。そしてこの懐疑と絶望こそ17世紀の時代の特質でした。ベーコンは主著『新機関』(Novum Organum)の第一巻のアフォリズム94から115にかけて、人間の知識への絶望を精力的に語ります。この時代の実験的方法の提唱者ベーコンこそ実験の陥るこの悲劇を最もよく体験した最初の人でした。またボイルは17世紀の実験的方法の推進に大きな足跡を残した人ですが、彼の人生観も「人間の本性の必然的不完全さ」(the necessary imperfect of human nature)という悲観的な意識が常につきまとっていました。
この実験方法を完成したのは、いうまでもなくニュートンですが、彼が死の言葉で自分が「海辺であそぶ子供にすぎぬ」(only like a boy playing on the sea shore)と語るとき、17世紀の悲観論はかれの生涯をはなれず、つきまとっていたことは明らかです。ミシェル・ド・モンテーニュ(Michel de Montaigne)(1533~1592)やハインリヒ・コルネリウス・アグリッパ(Heinrich Cornelius Agrippa)(1486~1535)は、16世紀にアリストテレスの古代の権威を否定し破壊した懐疑主義者ですが、17世紀の懐疑の深刻さは、当時の外部にむけられた懐疑主義と異なるものです。17世紀の懐疑は、深く人間の内部に向けられ、当時の科学者にも解くことができない苦悩を形づくっていたのです。歴史家はこれを「危機の時代」(critical years)と語り、かつてない「懐疑の時代」として語るのです。
17世紀の科学革命は、この懐疑の深刻さを貫いて成就されます。一切の絶望をのりこえて進行します。それは方法論的に分裂の時代であるとともに、偉大な実験活動の時代であり、「不合理の時代」(century of absurdities)であるとともに「天才の時代」(century of genius) でありました。また危機の時代であるとともに、科学の驚異(marvels)の時代でした。悲劇と混乱からの転換、または近代的知性の移行の時代として、17世紀の科学の流れは、まさしく「変革」または、「革命」(revolution)の時代であったといわるべきでしょう。我々が17世紀を科学革命の時代と語るとき、新しい体系が古き体系に取って代わったという意味ではなく、新旧思想の交替のかもし出す不安と絶望にもかかわらず、また人間的なものへの一切の懐疑に悩みながらも、その悲劇から立ち上がった点において、「科学革命」名が与えられるべきだと思います。
科学革命の到来
ニュートンの「自然哲学の数学的諸原理」(1687)『プリンキピア』は、世界像の数学化の頂点でしょう。この書物に書かれていることで有名なことは、惑星が太陽の周りを回るのは、リンゴを地上に落下させるのと同じ力によることを確立したからですが、その内容ははるかに豊かです。そこでは最初にケプラーの惑星軌道の法則が数学的に証明され、月や彗星に関する理論が初めて近代化されました。ニュートンの運動法則はデカルトの自然法則に取って代わり、その結果、物体の衝突理論は完成へと一歩近づきました。ニュートンはデカルトが取り扱うことができなかった、斜め方向の衝突も理論化に成功しています。ニュートンは遠心力についても完全に理解しました。また流体中の物体運動の理論に先鞭をつけましたが、この研究をもとに彼は媒体の圧力と密度に応じて変化する音の伝播速度を主題とする音響理論を構想することができました。とりわけニュートン自身を含め多くの同時代人により支持されていた機械論哲学にとって意義深かったことは、彼が可視的でマクロな現象がいかにしてミクロな現象から説明されうるかを数学的に証明したことです。
ニュートンの『プリンキピア』出版によって、16世紀に始まった自然哲学の数学化の流れは完成されます。このように評価されるのは、ニュートンはガリレオやデカルトと異なり、数学的にも自然学的にもおおよその正解に達したからなのかも知れません。
ガリレオの功績
科学革命を引き起こした人物が、ガリレオであり、デカルトなのです。ガリレオの方が年長であり、彼の科学的活動は16世紀末に始まるのですが、彼らの主要な活動時期は重なっています。いずれも、学問的経歴をアリストテレスの体系の影響下で始め、その体系に対する根本的な批判的作業を経て、自らの科学を形成しました。
ガリレオが、彼の時代まで支配的であったアリストテレス自然学の影響から抜け出すことができた第一の事情は、16世紀の後半になってようやく本格的に紹介され吸収されることになった、アルキメデス(Archimedes)(紀元前287頃~紀元前212)の科学の修得にあります。アルキメデスは、「梃(てこ)」や「釣り合い」を扱う「静力学」の創始者であり、その問題について数学的定式化を提示した数学者です。それは、数学が自然現象の法則性を表現し、その現象を統御するという端的な例でした。このアルキメデスの科学は、次に取り上げるデカルトにおいても、その科学的活動を方向づけるものでした。「抽象的数学」は「具体的自然学」を実質的に構成しえないとする、アリストテレスの自然学の立場を揺るがすものでありました。
地動説の正当化
それまでは天体の世界は永遠不変と考えられてきました。ガリレオは、自身の天文観測と理論的根拠から、地動説を積極的に支持しました。その根拠を示します。第一に彼が行った太陽黒点の観測は、黒点の生成消滅を示していました。太陽にも地上の世界の特有の性質と考えられてきた生成消滅があるということは、二つの世界は異質ではないということを意味します。ガリレオにとって、天体に固有な運動と考えられてきた円運動が、地球自体の運動に適用可能であるということになるのです。
第二に、それまで地動説が斥けられてきた大きな理由は、動いている船の高いマストの上から物を落とした場合、物体はマストの真下に落ちるという事実が、説明できないではないか、というものでした。これに対してガリレオは、地上の諸物体は、地球の水平方向の一様運動を共有しており、同じ方向の一様運動を共有しているものは相互に静止している、という議論で説明しました。これはのちに「ガリレオの相対性原理」と呼ばれることになった説です。
地動説は宇宙や地上の世界の実在の構造が、日常の知覚経験に従ってではなく、「地球の回転」という視点から理解し直されることになります。天体の世界と地上の世界は、同質の世界とみなされることになり、「上下」の方向も絶対的なものでなくなり、ただ我々の知覚に相対的なこととして理解されることになります。そこでは、宇宙や自然を構成すると考えられてきたアリストテレスの目的論的・階層的秩序は、根本的に解体されることになるのです。
抽象的数学と具体的自然学の同一化
こうして、我々の感覚知覚によって経験される現象は、自然の実在の構造を示すものではなく、我々の感覚知覚に相対的な現象にほかならないということになります。
ガリレオは、『天文対話(二大世界体系対話)』(1632年)において、アリストテレス主義者を登場人物に立て、アリストテレス自然学の見解を主張させて、それを論駁(ろんばく)する議論を展開しています。
そこでは、アリストテレス主義者は、数学は抽象的な対象を扱うものであり、それに対して自然学は現実の具体的現象を対象とする学問であって、具体的な自然学を抽象的な数学によって構成しようなどというのは見当違いあると言っています。それに対してガリレオは、「自然現象で具体的に生じることは、同じ仕方で抽象的にも生じる」と述べ、厳密な数学に訴えて、抽象的に自然現象の内にある厳密な法則性を追求しうるのだと主張します。
ガリレオは、これらの仕事を通じて、新しい近代科学の原理的な方法論をもたらしました。その第一は、「理想化」の手法です。彼の投射体の運動についての分析は、自然現象の多くの要因を捨象した架空の分析であって、自然現象自体の分析になっていないという、アリストテレス主義者の反論を予想して、ガリレオは次のように主張します。間題を科学的な方法で取り扱うためには、空気抵抗のような困難を一旦切離してみることが必要であるとしました。そのため、その定理を現実世界に適用するときは、経験が教える制約つきでそれを使用する必要がありました。
第二は、自然学の作業における、数学的論証の効力について示しました。ガリレオは、自然現象の分析において、「その数学的な理由を発見することによって得られた一個の事実についての知識は、実験を繰り返すことなしに、ほかの諸事実を理解させ、確かめさせるもの」であり、数学的論証は、演繹的判断により「経験上からは、かつて観察されなかったようなことまでも証明する」というのです。
実際に彼は、その数学的運動論によって、投射体は放物線を描き、その最大射程は45度の角度の場合であるということを論証しました。こうして、自然についての新しい知識を、感覚経験とは独立に、論証によってもたらすという、数学的自然学の「生産性」を明らかにしたのです。
異なる実験の考え方をする大陸とイギリス
数学的諸学にアリストテレス主義的自然哲学に並ぶような権威を付与するには、人工的に作り出される現象も日常的な現象と同じくらい世間一般の人にとって明白なものとなる必要がありました。公共の場所で実験を行うことによりこの課題を解決しようという試みもありました。例えば教会の尖塔の頂上からおもりを落とすなどです。しかし最も好まれた方法とは、出版物の中で実験を詳細に記録することでした。多くの場合、説明は幾何学の教科書の形式に則っていました。著者は実験装置の組み立て方、実験の手順、そして実験結果について、それぞれ具体的に説明するのです。その実験はすでに何度も繰り返し行われており、多くの専門家も見学していると記されました。やがてこうした形式が実験報告のあり方として定着していきました。
コーネル大学教授のピーター・ディア(Peter Dear)(1958~)はこのような実験をめぐる習慣が大陸で広まってゆく様を描き出しています。しかし、イギリスで根づいた実験哲学はこれとはだいぶ異なっています。例えば、フランスのプレーズ・パスカル(Blaise Pascal)(1623~1662)は実験を説明する際、それが事物の真理を表しているかのように一般的な見地をとり、もしこれらを行ったらこのことが起きるに違いないという言い方をしました。イギリス実験哲学の先導者ロバート・ボイルはそうではありませんでした。彼から見れば、パスカルによる説明はパスカル自身の前提している理論の上でしか成り立たちません。ベーコンの言うように、人は自らの先入見を肯定するために実験を行うこともできるのです。
イギリスにおける実験的方法は、ボイルを中心とした王立協会のメンバーのグループが主張するところによれば、事実だけを明らかにするものでした。これは大陸における実験的方法とは異なり、理論的な先入見から自由であるとされました。
自然の研究には、原理的に相反する二つの流れがあります。第一は自然を一定の原理によって統一的に把握しようとする考え方に立つものです。第二は自然をありのままに具体的にかつ総体的に把えようとする考え方に立つものです。科学方法論としていえば、前者は演繹法、後者は帰納法ということになるのですが、そう簡単に言い切ることができません。
前者は、些細な現象などには目もくれずに、自然を動かす統一的原理に肉迫します。ひとたびその原理に達すると、今度は世界のすみずみまでもその原理によって説明しつくしてしまいます。いかなる現象も、そこから導き出された法則も、その原理の補強に役立つだけです。
後者にとっては、その事物や現象から何が導きだされるか、現象の根底に潜む法則は何か、その法則によって自然はいかに説明されるか、といった問題は目もくれずに、事物や現象をひたすら客観的に記述していきます。結論されることを拒むような徹底した記録の精神がそこにはあります。
科学の歴史は、この二つの流れの激しいぶつかりあいの中で発展します。個人の思想も、この二つの思想に引き裂かれます。前者を宇宙論の流れ、後者を百科全書の流れと名づけよう。 17世紀の前半においては、前者の典型がデカルトの宇宙論的構想、後者のそれがベーコンの自然誌の方法でありました。
イギリスの実験方法
普遍的な言明は、多くのイギリスのプロテスタントにとっては意味をもたないものでした。それらは彼らにとっては虚偽の信念、つまり世界のあり方は必然的であるという信念にもとづいているからでした。例えば、真空は存在するはずだ、あるいは、物質の微小部分は不可分であるはずだ、といった言明に表れています。彼らには必然的な言明は、いかなる哲学的な体系をも任意に真理となしうる神の全能性を、不当に制限するように思えたのです。イギリス人は、神は哲学的可能性や不可能性に束縛されることなく、いかなる事柄も真理となしうると考える傾向がありました。自然哲学で彼らの行う方法が確立されれば、それは知識の正当化の一般的な方法が獲得されたことになるのです。イギリスの実験的方法は、専制的な権威を必要とすることなしに、自発的な秩序をつくりだせる共同体にとって不可欠な合意の手段として期待されました。
実験方法の違いは、宗教が起源
三段論法によって自然哲学を行おうというアリストテレス主義的な方法を棄却し、代わりに信頼できる実験を用いようという努力がなされたわけですが、ここで問題となっているのは、単なる抽象的な認識論的転換ではありません。伝統的なアリストテレス主義的自然哲学の信憑性は、用いられている前提が自明であるということから来ていたのですが、この信憑性そのものを別のものに替える必要があったのです。数学的命題同様、実験的知識も自明な知識ではありません。その真理について人を説得するためには、単に個人的に信用してもらうのでないとすれば、手順に至るまで詳しく説明するしかありませんでした。ボイルやパスカルといった実験哲学者にとって、周囲の人すべてに実験哲学や数学の専門家になってもらうことは不可能でした。そこで彼らは自分の主張がいかに信頼できるものであるかを強調する道をとりました。
それでは、ボイルのようなイギリス人とパスカルのような大陸人の間に見られる違いは、いったいどこからきたでしょうか。説明として、ディアは宗教的要因を重視します。大陸のカトリック圏ではまだ奇跡が信じられていたのに対し、イギリスのプロテスタントにとっては奇跡の時代はもはや過去のものでした。カトリック教徒によれば、自然は法則に従っていますが、その規則性はたった一回の出来事(つまり奇跡)によって覆されることもありえたのです。したがって、彼らにとっては一回限りの出来事としての実験は意味がないのです。数回の実験だけでは自然の法則の一つの実例に過ぎません。反対に、例えば気圧についての普遍的言明こそが、自然的世界の秩序について何かを教えてくれるのです。他方のプロテスタント圏イギリスにおいては、奇跡の存在が最初から否定されている以上、自然の秩序の法則性についての確信も必要ありません。そこでは一回限りの実験でも自然のしくみについてより深く理解するうえで有意味なものであるとされます。
反対に普遍的な言明は、多くのイギリスのプロテスタントにとっては意味を持たないものでした。それらは彼らにとっては虚偽の信念、つまり世界のあり方は必然的であるという信念に基づいているからです。それは例えば、真空は存在するはずだ、あるいは物質の微小部分は不可分であるはずだ、といった言明に表れています。彼らには必然的な言明は、いかなる哲学的な体系をも任意に真理となしうる神の全能性を、不当に制限するように思えたのです。イギリス人は、神は哲学的可能性や不可能性に束縛されることなく、いかなる事柄も真理となしうると考える傾向がありました。
実験方法についての考察
ディアとは対照的に、スティーヴン・シェイピン(Steven Shapin)(1943~)とサイモン・シャッファー(Simon Schaffer)(1955~)の二人は、王立協会独特の実験的方法論を、17世紀イギリス社会が陥っていた社会的混乱が背景にあると説明します。彼らは、イギリスの独特の実験哲学を、王政復古期において平和と安定を保障する必要と結びつけます。ありのままの事実を発見することにより、ボイル派は自然哲学における論争の終結が可能になると考えていた、というのです。物質が無限に分割可能であるか否かについて論争する人でも、事実そのものであれば反論しないでしょう。これは自然哲学者にとっては社会秩序の回復に貢献できる道のように見えたのです。自然哲学で彼らの奉じる方法が確立されれば、それは知識の正当化の一般的な方法が獲得されたことにほかならず、政治や宗教など他の分野でも争いの終結につながるであろうというのです。イギリスの実験的方法は、専制的な権威を必要とすることなしに、自発的な秩序を作り出せる共同体にとって不可欠な合意の手段として期待されました。
ディア、シェイピンやシェッファーの主張にはいくらか議論の余地があるにせよ、彼らの研究のおかげで、「実験的方法」がいかにして17世紀イギリスという文脈の中で発達し、またいかにして大陸における考え方と異なった方向を持つに至ったかについて深い理解が得られたと思います。また、彼らの研究は近代科学において実験的方法が大きな力をもっていることの背景についても考えさせてくれます。シェイピン、シェッファーの二人が指摘するように、今日では実験的知識はそれ以外の知的方法に比べて明らかに優れており、そのために大きな成功を収めたのだと考えられがちです。しかし実際には、彼らの研究が示しているように、我々が実験主義に寄せる信頼は、実験的方法そのものと同じく、初期近代社会においてはっきりと歴史や地域を限定された特殊な目的のためにとられた、様々な政治的、社会的、修辞的戦略と結びついて生まれてきたものなのです。
ロンドンの王立協会の役割
実険的方法が興隆したことで、自然哲学者や実験家のグループができていったことがしばしば指摘されます。これらのグループには、正式なものもあればそうでないものもあり、イタリアのアカデミア・デル・チメント(Accademia del Cimento)(1657)、イギリスのロンドンの王立協会(Royal Society)(1660)、あるいはフランスのパリ王立科学アカデミー(Académie royale des Sciences)(1666)に代表されます。このような指摘には、実験的方法が科学者の共同作業を必要とするという考え方が前提されています。この見方は、ベーコンのユートビア的著作『ニュー・アトランティス』(New Atlantis)(未完の著作として1627年出版)に描かれたサロモンの家にはっきり見ることができます。サロモンの家が発想の原型になり、王立協会と王立科学アカデミーが組織されたと言われています。また、これらの学会はどちらも実験的方法に傾倒した科学者たちの小規模な集まりから成長し、新しい学会の中でも最も成功を収めました。
ロンドン王立協会の成功
ロンドン王立協会(The Royal Society of London for Improving Natural Knowledge)は1662年に設立された自然研究者の組織です。その設立は、多かれ少かれ個人の恣意的な産物であった科学が、明確に方向づけられた集団的努力の結晶へと転化したこと、科学が一つの制度として国家と社会の中で不可欠の機能を果たし始めたことを意味しています。科学は王立協会によってはじめて近代的形態を獲得します。だから、それは近代科学成立史上において画期的な事件であったといえます。
協会の人々が集団的組織的に遂行しようと意図したのは、その名が示すように、(自然的知識の改善)でした。彼らはそのために新しい組織を採用し、有効な方法を発見し、共同事業の目標としての体系的なプログラムを設定し、全力をあげてその目的に立ち向かいました。わずか30年の間に英国の科学の水準は大陸の先進諸国を凌駕しました。そして、ニュートンの『自然哲学の数学的原理』(1687)は、王立協会を科学の世界の絶対的権威として君臨させるに至らせたのです。
1645年ごろ,ロンドンにはいくつかの自然研究者のサークルが生まれました。そこに集った人々は大商人や地主や新貴族や彼らと密接につながる知識人たちでした。その多くは議会に同情を示し、中には国王に忠誠な人々もいましたが、いずれの派に立つにしろ、決してその熱狂的な支持者ではありませんでした。宗教的にはピューリタンもいましたが、その多くはむしろ寛容と理性を重んじる英国教会の穏健派つまり、広教会派だったといえるでしょう。
彼らの一人、トマス・スプラット(Thomas Sprat)(1635~1713) が後に書いた『ロンドン王立協会史』(History of the Royal Society of London)(1667)によれば、彼らにとっても時代の争点である宗教や政治問題は深い関心の対象でした。しかし、それはこの穏健で冷静な知識人たちには耐えがたい苦痛でした。彼らはこの「陰欝な時代」の慰めを自然の研究に求めたといいます。彼らはしばしば会合して、新しい発明や発見について語り合いました。始めは一定の方法を持たず、体系的な研究を推し進めたのでもありませんでした。やがて彼らは新しい科学が彼らにとって何を意味するかを理解し始めました。それにふさわしい研究方法を発見すると、自然研究について体系的な構想を抱き始めるようになり、彼らは自分たちが誰よりもベーコンの弟子であることを自覚するようになりました。
科学は人間に新しい発明と力とを与え、人間の生活を豊かにします。ベーコンはそう信じていました。ベーコンによれば、自然の研究の第一歩となる基礎は、「自然誌」(Natural History)の作成でした。つまり、できるだけ多くの現象を「はやまった思索」をまじえずに記述し、それを適当な項目に配列し整理するのです。完全な自然誌が準備されたなら、そこから自然を動かす原理が導き出されるでしょう。その事業の達成には自然研究者の集団的な協働を待たなければなりませんでした。『ニュー・アトランティス』(New Atlantis)をベーコンは夢見ました。
自然と技術についての有用な知識のコレクションは、自然誌あるいは自然の技術誌とよばれます。自然誌の作成こそ、創立期の協会の「主要な、かつ究極的な目的」でした。ここで注意しなければならないのは、17世紀の自然誌は、18世紀のそれのように科学の一分野なのではありません。それは方法や事実認識としての知識を収集するための方法であり、その方法の適用の結果、出来上がった知識のコレクションでもあります。一言でいえば、自然誌とは記録する方法の一つです。
知識を、個人の極限された収集や個人間の偶然的な伝述にゆだねずに、一定の目的意識をもって収集し、その相互交流をはかるということは、17世紀においては革命的な出来事でした。人類として新しい発明や発見が一つもなかったとしても、それだけで、すでに「自然的知識の改善」という目的は、協会の人々の多くを満足させる程度に達成されたでしょう。体系的に収集され、即座に伝逹される知識を前提として思考する、今日の私たちには、協会の努力がもっていた革命的意味はとらえにくいようです。
中世の社会構成体の細胞をなす様々な共同体は、ひとつひとつが完結した、閉鎖的な社会を形成しています。共同体の成員は、生産と生活の全面にわたって、厳格な規則を受けます。この規則は知識の上にもおよびます。知識はそれが共同体の存在理由を与えるものであれば、秘伝として外部にもれるのを防ぎます。知識の相互交換は、共同体間では原則的には行なわれません。
例えば、商人と生産者のギルドでは、商品生産の「技術」の秘密はあくまで保たれます。ギルドが崩壊し,生産の大規模手工業の段階がやってきても,大規模手工業の技術的基礎が手工業的であるかぎり、事情は変わりません。技術の秘密は執拗に守られます。
国内市場の形成や海外市場が拡大するに従って、伝統技術の上に安住することを許さなくなります。新しい技術が要請されます。知識が閉鎖的社会に閉じ込められている状況にあっては、新しい技術への要求は、発明へと向うより、「秘伝」を相互に盗み取ろうとする努力へと向います。
こうした知識の閉鎖性は決して生産部門に限られてはいません。思想や学問の分野においては,印刷術の発明によって事態は変りつつありましたが、それはまだごく限られた効果しか収めていませんでした。王立協会の人々は、こういう状況に挑戦したのです。
17世紀という、知識が閉鎖的社会の中に閉じ込められていた時代にあっては、その閉鎮性を打破し、相互交流をはかり、人類の知的所産を収集し集積することが、科学の進歩の基礎条件でした。それは自然と社会、つまり世界を総体的に把握しようとする資本家階級の知的野心、すなわち、百科全書の構想と、技術の改善による生産の増大、原料と商品の市場の開拓をめざす現実的関心と、そのいずれにも即応できるものでした。政治権力を掌握した大商人や地主層が、その事業に着手します。彼らは自らの組織形態を使って集団的協動の体制をつくり、「自然誌」という記録的方法を採用し、有用な知識の収集に努力しました。
ホィッグ党の色彩の濃い協会は、そのリーダーを歴代の会長に迎えて、一つの社会勢力となりましたが、完全な自然誌の作成という目標には及びませんでした。体系化しようとしても報告は不完全で断片的で、そのまま使うことができませんでした。有能な人はそれほど多くはいませんでした。協会は会員の出資による運営をしていましたが、財政も滞りがちで、うまく行きませんでした。しかし、決定的な要因は、彼らが「原理」を持たなかったことです。収集された雑多な認識資料を整理し分類し体系づけるには、一定の原理を必要とします。彼らはそれを持たなかっただけでなく、意識的にそれを拒否し、「記録的な方法」だけで百科全書的な知識の体系を作ろうとし、作れると信じていました。なんという大きな錯覚でしょうか。その行きづまりは誰の目にも明らかでした。ぼう大な資料を前に、彼らの仮説や原理の探究が始まりました。これまでの協会からみれば異質の人であったニュートンが、舞台の正面に登場することになります。
「大衆は有用な知識の所有者であるどころか、せいぜい真理を妨害するしか能のない連中にすぎない。真理を知るのは常に選ばれた小数者だけだ。」協会への最初の手紙にこのように書いたニュートンは、創立期の協会の真の指導者ロバート・フック(Robert Hooke)(1635~1703)と真っ向から対立しました。ニュートンにとって、協会は最初から住みよい場所ではありませんでした。
しかし、事態は変化しました。協会はニュートンに手を差し延べました。逆二乗法則がフックのアイデアだったとしても、ニュートンの体系的構想力によって理論化される他はなかったのです。名誉革命の前年に出版された『自然哲学の数学的原理』によって、協会の活動は実質的に終わりをつげました。その課題の解決は18世紀に残されました。
原理を獲得した自然研究の体系化が始まりました。自然誌が方法から分野へと転化します。遅きに失したとはいえ、最初の近代的百科全書『技術辞典』(1704)(Lexicon technicum)の編集者という名誉は、王立協会の書記ジョン・ハリス(1666~1719)の上に輝きました。彼を経て、協会のプログラムはフランスの百科全書派(Encyclopédistes)に引き継がれました。協会は徐々に実験科学の伝統から離れて行きました。フックはガリレオ以来の実験科学を受け継ぎましたが、18世紀になってニュートンが台頭すると、理論的な科学の勢力が増して、自然誌は自然哲学に移行して行きました。しかし、ひたすら客観的即物的に対象を記述して行こうとする記録の精神、自然誌の方法まで失われたのではありません。それは近代科学の底辺に脈打っています。
機械論哲学の登場
17世紀は、アリストテレス主義哲学を根こそぎ捨て去ることを可能にするような新しい哲学を求める人々が現れました。新しい哲学はいくつか提唱され、互いに競合しましたが、当時それらはひとくくりに「機械論哲学」と呼ばれました。17世紀末までには、機械論哲学は実質的にアリストテレスのスコラ哲学にかわって支配的になっていました。それは光の伝播から動物の発生まで、気圧理論から呼吸の説明まで、そして化学から天文学にいたるまで、自然的世界のあらゆる側面を理解するための鍵と考えられました。機械論哲学は過去とは根本的に断絶していました。それは実際、科学革命の最高潮における自然哲学です。
機械論哲学では、あらゆる現象は数学化された機械学、つまり力学の基本概念を用いて説明されます。形、大きさ、量、運動といった概念です。原理的には接触作用があらゆる変化の原因とされます。機械論は自然の働きを機械の働きに見立てます。自然的変化の原因は物体の相互作用なのですが、それはあたかも時計の歯車のように考えられました。あるいは物体どうしの衝突と、それに伴う運動の伝播も原因として措定されました。
アリストテレスの目的論は、物体の振舞いをそれに内在する目的から説明します。例えばドングリが生長する理由は、オークの木となって人間に木材を提供するためであるとされます。機械論では生気論や目的論を用いた説明は拒否されます。物体が真にもつ性質である大きさ、形、運動と静止は、物体が単に二次的にもつ性質から厳密に区別されました。後者は真の性質から派生するもので、色、味、におい、熱や冷といったものです。例えばビネガーは「味」という性質を持つのではなく、実際にはビネガーを構成する粒子が鋭く尖っているために舌を刺激し、その結果、酸っぱく感じられるに過ぎない、という説明がされました。アリストテレス主義で言われていた明らかな性質が、機械論では単なる二次性質になっている点が注目されます。二次性質は物体を構成する不可視の微小粒子に原因とされるのです。同時に、それまでの隠れた性質も機械論的原理を用いて説明されます。アリストテレス主義における明らかな性質と隠れた性質の区別は、機械論では意味をもちません。究極的には感覚不能な粒子の運動と相互作用から自然現象が説明されるからです。
機械論哲学の重要な特徴として最後にあげられるのが、あらゆる物体が不可視の原子あるいは粒子から構成されているという仮定です。さまざまな機械論哲学の出現の背景に、古代の原子論的自然哲学の復興があったとしても不思議ではありません。デモクリトス(Democritus)(紀元前460頃~紀元前370頃)、そしてとりわけエピクロス(Epikouros)(紀元前341~紀元前270)の学説が復興されたことが重要でした。実際、機械論の代表的思想家ピエール・ガッサンディ(Pierre Gassendi)(1592~1655)は、エピクロスの思想を再構成する過程で自らの体系を展開して行きました。しかし、すべての機械論者が不可分の原子を考えていたわけではありません。機械論者でありながら、同時に物質が無限に分割可能であり、かつ実際に観察できる変化はすべて物質の最小単位としての粒子によってひきおこされると考えることは、不可能ではなかったのです。原子より小さいものの存在も考えられていました。こうした改革の重要な結果に、不可分でありながら、かつ大きさをもつ粒子という観念が確立されたことがあります。それ以前の原子論が抱えていた大きな困難は、数学的原子論と呼べる説との区別が曖昧であったことです。数学的原子論では、粒子が不可分であるのは、それが延長をもたない幾何学的な点であるからでした。しかし数学的原子論では、延長をもたない原子がどのように延長をもつ物体の自然的変化にある役割を果たしうるのか、不明でした。点というのは大きさがないのだから、いくつ集まっても大きさ、つまり延長を持ちえません。
17世紀の科学研究の内容に少しく立ち入ってみれば分るように、17世紀の科学は力学的、機械論的な自然観をその根底に置き、その限界をほとんど出なかったことが解ります。17世紀の科学の革命的な発展はほとんど、古代~中世のコスモス的な自然観に対する力学的自然観の勝利を表現していました。したがって、我々はこの支配的な自然観の変革を機械論哲学の勝利と呼ぶことができるでしょう。さて、この機械論的自然観の勝利への突破口を切り開いたのは、コペルニクスの地動説であり、ガリレオの力学と地動説の研究です。ギリシア哲学の伝統に古来、「運動の無知は自然の無知」ということわざがあるように、力学の問題は自然哲学の根本問題であり、世界観の問題に関連する問題です。アリストテレスのスコラ学の自然観というのも、その根本はこの力と運動の作用に関する独得な解釈にあり、運動の根本にふれる議論はこの自然観をみとめるか否かに大きく左右されざるを得ないのです。
ところで、17世紀には物理学者、化学者、生物学者などの区分はありませんでした。当時の科学者は皆が自然哲学者であって、その自然哲学者がそのときの関心にしたがって、あるときは生物学的、あるときは力学的、数学的な対象をとりあげて論じたに過ぎません。17世紀にはすべての科学は自然哲学者という人間において統一しており,自然研究のある分野における成功は、直ちに他の分野の自然研究に適用されていました。ガリレオの力学と地動説は、このようにして17世紀の全科学研究の出発点となり得たのです。
科学革命における数学の役割
「科学革命」をどのように規定するか、これについては、おそらくさまざまな見解があると思います。ここでは常識的な見解にしたがって、コペルニクスの地動説(1543)の登場から、ニュートンの力学(1687)の確立に至るまでの、およそ1世紀半にわたる力学、天文学を中心とする科学の飛躍的発展をさしています。
ルネサンス(15~16世紀)は、近代数学の創生から確立に向かう時期です。この時代に、数学はギリシア的形態を次第に脱皮していきます。インド、アラビア、そしてヨーロッパ中世末期に姿をあらわしていた商業算術は、利潤を追求し、計量や計算を高度に要求する近代資本主義社会の出現とともに急速に普及し、計算に便利なインド数字(アラビア数字)と、その計算法は、16世紀には民衆化しました。イタリアのルカ・パチョーリ(Fra Luca Bartolomeo de Pacioli)(1445~1514)の複式簿記の発明(1494)も、そうした動向の一産物です。
ベルギーの数学者・自然科学者で技師でもあるシモン・ステヴィン(Simon Stevin)(1548~1620)が考案した十進法の小数と、その計算法の樹立(1585)は、計算力を飛躍的に発展させました。また16世紀末から次世紀の初めにかけて、スコットランドのジョン・ネイピア(John Napier)(1550~1617)と、スイスの時計師ヨスト・ビュルギ(Jost Bürgi)(1558~1632)がそれぞれ発明した対数は、天文学者たちの複雑な計算を、著しく簡略なものにしました。こうした計算法の発達と関連して、代数学も進歩しました。ルネサンスが中世から受けついだ代数は、記号を用いない不便な、いわゆる「言葉代数」でありましたが、そればインドの代数よりも劣っていました。やがて、その代数の記号化が始まり、四則演算の記号、等号、根号、括弧記号など、代数計算に必要な記号が、15世紀の中ごろから次世紀の中ごろまでの間に導人されました。また代数にとって重要なベキ指数と、それの記号も15世紀から、17世紀の初めにかけて導入され、改良されました。こうしてデカルトの有名な『幾何学』(La Géométrie)に見られる代数学の姿は,ほぼ現代の式となっているのです。
17世紀の数学は、ルネサンスのそれを土台にして、はなばなしい発展をとげました。17世紀は数学の歴史において、もっとも創意に富んだ世紀といえます。先にも述へたように、代数学はデカルトにおいてほぼ近代化を完了しました。この代数を土台として、彼とピエール・ド・フェルマー(Pierre de Fermat)(1601~1665)は、それぞれ解析幾何学を樹立します。ギリシアの「幾何学的代数」は幾何学の狭い枠で、代数の自由な計算力を圧し潰してしまいました。これに反し、その解析幾何学は、代数の計算力を全く傷つけることなく、座標の観念を媒介にして、巧みに幾何学の世界に結びつけます。この結合は、幾何学にも代数学にも幸いしました。その結合のおかげで、幾何学の世界では無数の高次曲線が発見されました。また代数学の世界に変数・関数の観念が持ちこまれました。解析幾何学は量の変化の仕方をつかむことのできる、変量の代数学なのです。
さて、このような輝かしい近代数学の発展は、天文学や力学を中心とする科学革命の進行の中で、どれほどの役割を演じたのでしょうか。われわれの問題は、「科学革命」の立役者である天文学や力学が、どのような数学を利用していたのでしょうか。コペルニクスが用いている数学は、主として、古典的なユークリッド幾何学と三角法です。いうまでもなく,かれの地動説出現のためには、三角法の発展と、精密な三角関数表が必要ではあるのですが、しかし三角法は近代の発明ではなく、古代ギリシアのヒッパルコス(Hipparchus)(紀元前190頃~紀元前120頃)によって初めてまとめられました。精密な三角関数表は、レギオモンタヌス(Regiomontanus)(1436~1476)などの努力によって、すでに算出されていました。
ガリレオではどうでしょうか。彼の「天文対話」や「新科学対話」で使用されている数学は古典ギリシア幾何学です。ケプラーではどうでしょうか。彼の天文学が、惑星軌道の楕円であることを発見したのは周知のところであり、その理論が円錐曲線を必要としたことは、いうまでもありません。しかし、この理論は古代ギリシアのアポロニオス(Apollonius)(紀元前262~紀元前190)がすでに作りあげていました。ケプラーの理論は、惑星の運動の理論であるからには、当然のことながら、それらの内容にふさわしい数学は徴積分法であるべきと思われます。彼の有名な面積速度の法則の正確な把握には積分法が必要です。残念ながら数学は完全に立ち遅れていました。彼は、軌道上の短い単位距離を惑星が進行するのに要する時間が、その惑星と太陽との距離に比例するとし、またそれらの時間の総和は、これらに対応するそれぞれの距離の総和に比例するとして、これらの距離を面倒な手続でもって計算するのですが、これは積分計算を有限個の線分の総和という近似計算で置きかえるものでした。このような迂路(うろ)を通って、ようやくケプラーは面積速度の法則にたどり着くのです。いずれにせよ、彼の天文学は、新しい数学の出現を待望しながらも、その要求が充たされず困り果てていました。
解析幾何学の創始者デカルトではどうでしょうか。この幾何学は、先にも述べたように、変量の数学であるから、自然の本質が延長と運動であるとする当時の力学的自然観にふさわしいものでした。しかしその幾何学は、彼の力学的自然像の描出には、さほど大きな役割を果しているとはいえないようです。彼は『宇宙論』や『哲学原理』において、自己の方法が数学的(幾何学的)であるといっていますが、延長と運動において物質を考察するということであって、必ずしも本格的な数学的処理を施すという意味ではないようです。
彼は「運動の研究が純粋数学の主対象である」と述べてはいるものの、エーテルの充実した空間の中を動く天体の状況を数学式で表すことはできませんでした。現代風にいえば、連続体の力学に属する課題であり、数学的には偏徴分方程式を必要とするのであるから、デカルトの当時の数学の水準では、どうにもできないものでした。彼が数学を巧みに適用しているのは、光学、落下体論、静力学などであり(かれは解析幾何学を光学に応用している)、彼が最も重要視した宇宙論では、数学はほとんど使われてはいません。パスカルでも、新しい数字と力学・物理学との結びつきは密接ではありません。彼の数学上の重要な業積の一つは無限小概念を用いる求積法ですが、彼の大気圧の実験や流体力学の研究と、はとんと結びついてはいません。
我々はこれまで17世紀の代表的な数学者、科学者をとりあげて、彼らにおける力学や天文学と数学との関係を、簡単ながら検討してきました。その結果は、近代の新しい数学は、「科学革命」の中で、さして積極的な役割を演じてはいなかったということです。数学的手段を高度に要求する天文学において、その手段となったのは、アレクサンドリア数学の遺産である三角法であり、また古典的なユークリッド幾何学であり、さらにはケプラーにおいては、アポロニオスの円錐曲線論です。もちろん、ルネサンスにおける計算術の発達が、天文学者の計算能力を高めたことは否定できません。それらも計算の技術に過ぎず、近代の動力学や天文学にふさわしい新しい数学理論とはいえません。数学は「科学革命」の進展のテンポに完全に立ち遅れていたのです。この立ち遅れを克服し、近代科学にふさわしい数学の態勢が整い始めるのは、おそらくニュートンとゴットフリート・ヴィルヘルム・ライプニッツ(Gottfried Wilhelm Leibniz)(1646~1716)による微積分法の樹立のおかげであろうと思われます。ニュートンの『プリンキピア』(1687)は古典幾何学を範にとって叙述されてはいますが、しかしfluxion法(ニュートンの徴積分法)が随所に姿を現わしており、彼の動力学はこの新しい数学的武器なしには、おそらく成立しなかったでしょう。
初めて彼が新しい数学と新しい力学を結びつけ、両者が互いに他を促進させながら、発展を始めるのです。18世紀はこれの継続です。要するに「科学革命」において、積極的に近代数学が効力を発揮し始めるには、微積分法の登場を待たねばなりませんでした。
科学革命の第一幕の終りをニュートン力学の成立とすると、近代数学が自然研究の力強い武器となることのできたのは、その第一幕の終わる直前でした。近代数学が効力を発揮し始めたからこそ、「科学箪命」の第一幕か終わることができたともいえます。
デカルトの世界論という著作
17世紀前半に、ガッサンディのエピクロス主義的自然哲学に対抗したのは、デカルトの新しい自然哲学でした。デカルトの粒子論は、議論の余地はあるのですが、機械論の中でも最も影響力の大きい思想であり、かつ多くの点で最も印象深いのです。デカルトの自然哲学は数学と自然学の合一に加え、新しい形而上学にも基づいていました。デカルトによれば物質とはその延長のみで定義されます。原理的には自然学は延長物体の運動の幾何学的分析に還元されることが可能です。しかし実際のデカルトの自然哲学を見てみると、数学的分析はほとんど行われていません。例えば天体運動の説明でも、デカルトは惑星の密度と太陽からの距離との間に関係があることを指摘するのですが、その関係を計算しようとはしません。デカルトが自らの自然哲学の数学的確実性について疑おうとしないのは、その全体が公理論的構造を持ち、その基礎が不可疑であり、そしてすべての現象がその基礎から注意深く演繹されているからでしょう。
デカルトは『世界論』において、初めて自然哲学について体系的に考察しました。『世界論』は1633年までに書かれていましたが、ガリレオがコペルニクス説を支持したことで有罪とされたことが伝わると、デカルトは出版をとりやめました。デカルトは1644年の『哲学原理』において、機械論哲学を完全な形で発表しました。『哲学原理』では、デカルトは依然としてコペルニクス主義を支持しているのですが、あらゆる運動は相対的なものであることを証明するために巧みな説明が用いられており、それを背景に、デカルトは地球が定義上静止していると結論しています。
デカルトは物質と延長とを同一視し、それを体系全体の出発点としたため、真空の存在は否定され、あらゆる相互作用は接触によって起こるとしています。世界は物質で充満しているため、その一部分が運動すると世界全体に影響が及ぶことになります。しかしこれはいかにも不自然なことなので、デカルトはそのかわりに局地的な円環ができ、それにより物質相互の位置の入れ替えが起きるとしています。つまり何かが前方へ移動するとそれがその前にある物体を押しのけ、それがさらにその前にある物体を押しのけるという具合に進みます。こうして連続して置換が起きると全体は何らかの理由で方向を曲線状に曲げ、系列の先端では最初に動いた物体のあった空間に最後に押された物体が移動することになります。こうして運動する物体はすべて物質の円環運動の一部となり、それらはすべて渦巻きを形成し、周囲にぎっしり詰まった物質粒子を巻き込んで行くことになります。デカルトの惑星系は自己制御的です。
ところで、なぜ大きな粒子が集積して惑星が形成されるのでしょうか。このあたりの説明は曖昧なのですが、いったんそのような惑星ができると、それ自身が小さな渦巻きを自身の周りに形づくるとされます。惑星を取り囲む粒子は惑星から遠ざかろうとする傾向をもつが、これが重力の原因とされています。デカルトの体系にはもう一つ重要な前提があります。世界における運動の総量は一定であるというものです。デカルトの同時代人もこれに疑義を唱える者はいませんでした。彼らは、細部については批判しましたが、それが自然的世界を理解するうえで最も信頼でき、最も実り多い方法であると確信していました。
デカルトの思想は大陸では成功を博し、とくにフランスとオランダではもてはやされましたが、イギリスではそれほどではありませんでした。イギリスで発逹していた実験哲学は、いかなる演繹的体系も簡単に受け容れることはありませんでした。デカルトは自然哲学における実験に一定の役割を認めていましたが、それらは副次的な地位ということでした。それらはデカルトにとって推論の連鎖を補強する以上のものではありませんでした。
結果として、デカルト主義者の行う実験とは、デカルトの推論が正しいと前提したうえで、どのようなことが起きると予想されるかを報告する程度のものとなります。
イギリスのプロテスタントたちは、合理的な思想の体系を人間が自らの限界を神に押しつけることによってその全能を不当に制限する考え方として受け止めました。デカルト主義的な実験も、ボイルなどのイギリスの著名な実験哲学者によって採用されることはありませんでした。デカルトの機械論哲学そのものが、イギリスで不人気であったかというと、そうではありません。王政復古後に活躍した主流の自然哲学者は皆、機械論を奉じていました。
機械論哲学は当時の数学的力学、運動論、動力学の発展と切り離すことはできないものの、それ以外の面でも当時の自然哲学における有力な考え力でした。何人かの機械論者は新しい哲学の有効性を示すため、生物の形や機能や生命過程にまで研究を広げました。代表的な機械論者であったデカルトとトマス・ホッブズ(Thomas Hobbes)(1588~1679)にとっては、実のところ生命現象や人間を含めた動物の振舞いを説明することが主要な関心事であり続けたとっても、あながち不当ではないでしょう。
デカルトの役割について
私たちはここで、ガリレオからニュートンヘの経過において、その介在者としてのデカルトの存在に注目してみます。デカルトが力学史の中に残した業績をガリレオからニュートンのそれと対比、吟味してみるなら、力学革命などという単純な構図は17世紀の歴史的状況に決して適合しないことが明らかにてきるでしょう。ここには外から持ち込む明解な筋書きではなく、時間とともに曲折する歴史的現実の素顔が見られるはずです。
ガリレオよりも30年余り遅く生れたデカルトが、先達のガリレオから何かの影響を受けたということは予想されます。しかしながら、デカルトが力学の理論的内容について、直接ガリレオから学んだ形跡は余り見当たりません。両者の力学的構想はそれぞれ独自のものでした。だからガリレオとデカルトとの間では、お互いに違っている面が重要な問題となります。
その相違点を考えてみる前に、二人が同時代人として生きた17世紀前半の歴史的状況を反映する共通の課題を思い起こしておくことが必要です。それは力学の思想的基礎を与える宇宙像、つまり地動説の問題です。ガリレオもデカルトもこの地動説の信奉者であり、その点とともに近代的思考を開拓する共通の立場に立っていました。興味深いのは、この共通の問題をめぐって、先達と後継者とのそれぞれの位置では、変化が見られることです。ガリレオの生き方が直接デカルトの生き方に強い影響を与えたものであっただけに、その変化の有様を確認しておきます。
地動説を説いたガリレオが受難の晩年を送ったことはよく知られています。1632年『天文対話』を現わした後で、宗教裁判にかけられ、その地動説を捨てるように強制されたことは有名な出来事です。その当時デカルトは、「もしも地動説が虚偽ならば、私の哲学の全根抵もまた虚偽になる」という立場で『世界論』を書き続けていました。だからデカルトはガリレオの事件を知って、大きい衝撃を受けずにはおられませんでした。
教会の権威を傷つけぬように腐心しながら、自己の哲学的確信を論証的に整備しようとしたデカルトの策謀的な学的生涯は、彼の研究内容全体にも影響を残さずにはおきませんでした。同じ地動説の問題をめぐり、ガリレオは公言した上で異端者として生き、それを恐れたデカルトは偽装転向者として疑いぶかく生きてゆく、それぞれは違った道を選ぶことになります。ここには1633年という歴史的時点での、学者の学説とその背景となる社会思想との複雑な関連の仕方が伺い知られるでしょう。
デカルトがその後もう一度ガリレオに注目したのは、1638年に公刊された『新科学対話』を読んだときです。ガリレオのこの著書に対するかなり詳しい批評が、メルセンヌ宛の手紙(1638年10月11日付)の中に書き残されています。これはデカルトの学問的立場と、ガリレオのそれを対比する上で注目すべき文章です。デカルトは最初に「彼は物理学の問題を考えるとき、伝統的なカトリックの学派の誤りをできる限り避け、数学的推論に基づいて結論に達するように努めている」と、ガリレオの立場に同意を示しています。しかしここでデカルトが強調してみせるのは、ガリレオとの共通点ではなく、相違点の方でした。ガリレオの立場を批判して次のようにいっています。「たえず脱線して枝葉に渡り、落着いて一つの問題を十分に説明することをしないことが大きな欠点ではないかと思います。つまりそれは彼が問題を秩序正しく吟味しないことを示すものです。彼は自然の第一原因を考察せずに、単に特殊な結果の原因のみを求めました。このような結果を導いたのは、基礎工事をせずに建築を始めたからです。」
単純にみれば、これは自然研究者ガリレオと、形而上学者デカルトとの違いにすぎないと思われるかも知れません。その点も考慮に入れる必要がありますが、それに留まる問題ではありません。力学の範囲内に話を限っても、デカルトのガリレオ批判は十分意味を持っています。力学の理論的発展について、ガリレオとデカルトを対比、評価する場合、上の言葉はまさに重要な内容に触れています。それは慣性の法則についての問題です。
慣性の法則は後にニュートンの第一法則として定着する力学の基礎づけに欠くべからざる原理です。普通これの先駆的発見者はガリレオということになっており、事実その通りに違いありません。しかしガリレオの述べた慣性への言及は、水平面上の運動のみに成り立つ特殊なことがらに過ぎませんでした。このことから、次のニュートンの一般的表現である、第一法則は、「すべての物体は,それに加えられた力によって状態を変えられない限り、その静止もしくは一様な直線運動の状態を続ける。」に普遍化されるまでには大きい隔たりがあります。ニュートンがその隔たりを克服し、一挙に一般的法則の把握へ達したものと普通は考えられがちですが、事実はそうでありません。ここにデカルトの介在者としての役割が正当に考慮されねばならないでしょう。
「自然の第一原因を考察せずに、単に特殊な結果の原因のみを求めた。」とデカルトから批判されたガリレオは、『新科学対話』の中で次のように述べています。「我々は、どんな速度であっても、一旦運動体に与えられれば、加速あるいは減速の外的原因が取去られている限り、不変に支持される、ただしこういう条件はただ水平面上でしか見出されません。というのは、下向きの斜面の場合には、そこにすでに加速の原因があり、上向きの斜面の場合には、すでに減速の原因があるからです。このことからして,水平面に沿う運動は永久的であることが分かります。もし等速度であれば、それは減ぜず失われず、まして増えることがないからです。」これは確かに慣性の法則の先駆的表現に違いありません。
ガリレオはこれを法則として把握する意図は一切示していないことに注意しておくべきです。単に水平面上の運動という「特殊な結果の原因」として慣性の存在が予測されたに過ぎないのです。「自然の第一原因を考察」して、慣性の法則を普遍的法則として把握したのは、ほかならぬデカルトでした。
私たちはその適確な表現を1644年に公刊された『哲学原理』の中に見ることができます。デカルトはここで自然の運動について原理的な省察を進め、それを三つの基本法則にまとめていますが、そのはじめの二つが慣性の法則の明確な表現となっています。
自然の第一の法則は、「すべて物体は、他から力が加わらない限り、その同じ状態を保つ。」
自然の第二の法則は、「運動する物体はすべて直線運動を続けようとする。」
これを、ニュートンの表現と比べて見るとき、ニュートンは慣性概念の原理的把握を確かにデカルトから継承していることが分かります。むろんニュートンは表現形式や内容ともに、かれ独自の構想にしたがって慣性の法則を統一的に把握し直しており、ここにはデカルトだけではなく、ガリレオからの継承も明らかに見られます。そうであるにしても、デガルトがガリレオとは全く違った力学的構想から、慣性の原理的な把握に達し得たのであり、その力学史的役割はやはり大きい意義をもっています。「自然の第一原理を考察」しようとするデカルトの哲学的省察の態度こそが、ここでは欠くべからざるものであったといえるからです。私たちはこれで、ガリレオ、ニュートンのあいだに介在するデカルトが、力学の発展経過の中でやはり無視できない重要な存在であったことを、ひとます確認することができました。
デカルトの力学的構想
私たちは、三様の慣性法則がどのように違っていたのか、その点を振り返ってみることにしよう。最初にガリレオは、慣性を物体運動の根源的状態として積極的に把握することができませんでした。彼は、速度を変化させる加速、減速の原因が働かないとき、速度が不変に保たれることを指摘し、たまたま水平面上では等速運動体にこの条件が満たされていることを消極的に認めたに過ぎません。ガリレオの運動学的構想が、速度と加速度における関係を、時間と距離との関係と幾何学的に図解すれば、それは当然であったということが理解できます。ここに運動の第一原因を基本的に確認しておこうとする志向が生れるはずもないからです。
これに反しデカルトは、運動物体の速度や加速度とかいったガリレオが常に着目した実測的な概念にほとんど関心を示しませんでした。そのため運動の変化を定量的に適確に表現する手順を見失って、単独物体の運動(質点運動)の数理的考察は正に生彩を欠いています。しかし、運動の第一原因については明析な把握を得ようと執拗な省察を重ねていました。結局、行き当たる所は自然秩序を司祭する神の存在ということであり、運動の本質的内容もこれとの関連において把握されています。
「神は変化しません。神はその働き方はいつも同じで変わらないのです。」このことからすべての物体は根本的には同じ状態を持続しようとするはずだと、デカルトは考えを進めました。彼は「一つの物体が、ひとたび運動を始めると、永遠にこの運動を続け、自ら静止することはない」と考えました。運動の根源的状態としての慣性が、こうして原理的な認識にまで高められることになりました。「運動は自ら止むのが本性で、静止の傾向を持つものだ。」というこれまでの運動観は、これでようやく克服されました。静止にしろ、運動にしろ、それが持続されている限り、いずれも慣性的な状態の現われと考えればよいのです。それならば運動状態の変化はどのようにして生ずることになるのでしょう。その点ガリレオは、等速運動の「変化」には加速あるいは減速の原因があると言っただけで、その原因が何であるかには触れようとしませんでした。
デカルトは、変化のためにその原因が存在すると指摘するだけでは満足しませんでした。彼はその原因が何であるかを原理的に確定しておこうと努めました。「個々の物体はできるだけおなじ状態に留まるもので、他の物体の衝突がなければ、それを変えない。」つまりデカルトによれば、運動状態の変化は「他の物体との衝突」によって起こるというわけです。ここにデカルト独自の力学的構想が姿を見せています。むろんニュートンの構想とも全く違うものでありました。先の慣性の法則におけるデカルトとニュートンとの表現を、詳しく調べてみなしょう。
二人とも運動の持続という慣性的状態が成り立つためには、それなりの条件が必要だとみています。デカルトは、他から変わらせようとするものがなければ、同じ状態が保たれるといい、他方ニュートンは、加えられた力によって状態を変えないかぎり、同一状態を続けるといいます。
デカルトの場合、「他から変わらせようとするもの」というのが、つまり他の物体との衝突であることは、明らかでしょう。ニュートンの考えている運動変化の原因は、力の作用のことなのです。ここで衝突論と力の作用論と、運動変化の原因を考える上で、根本的に違う両者の立場からは、当然相異なる力学的構想か展開されるはずです。二人がそれぞれに述べた三つの基本法則の残こされた部分には、この違いが明瞭に現れてきます。
一般によく知られているニュートンの法則の第二、第三のものは、
第二法則:運動量の変化は加えられた運動力に比例し、この力が作用する直線の方向に起る。
第三法則:作用には常に、これに守しくかつ反対むきの反作用がともなう。言い換えれば、互いに相対する二つの物体の相互作用は、互いに等しく反対の方向に向かう。
ここではいずれにしても力の作用として運動現象を包括的に把握しようとする志向がはっきりしています。ニュートンが、運動の力として定義したものは、運動量の変化に比例する量です。これは結局、加速度と質量との積として表されるのであって、先にガリレオが加速(減速)の原因といっただけで保留していたものが、いま明確に力の概念として把握し直されたことになります。ここにガリレオとニュートンとの間には、緊密な理論的内縁関係をみることができます。ここでいう質量は、慣性の尺度としての意味を持つ量でなければなりません。その慣性を原理的に定着させたデカルトの介在者としての役割は、ガリレオのものと似ているニュートンの力学的構想において、決定的な影響を与えていたのです。
ところでデカルトの基本法則で残っていた、もう一つは何に触れているのでしょうか。自然の第三の法則は、「運動する物体が、力のより大きな物体に衝突するときは、その運動を失わない。力のより小さな物体と衝突してこれを運動させるようなときは、与えただけ失う。」現在の立場から解釈すれば、衝突現象における一つの運動量保存の法則です。
しかしニュートンの力学的構思にはこのような観点が全く見られませんでした。ニュートンは二つの物体の間に、作用と反作用のつりあいを考えたに留まって、運動量の交換が起こる衝突現象の考寮をすすめる意欲はついに示しませんでした。ニュートンは運動の変化を力の作用で解明しようとしましたが、デカルトは、運動の変化を二物体の衝突によって説明しようとしました。運動量の保存則は、まだ萌芽状態ではありますが、デカルトがこれを把握していたことの力学史的な意義は非常に大きいものでした。19世紀になってエネルギー保存則が確立され、力の概念によるよりも、相互作用で交換されるエネルギーの量に視線を集めて、その後の理論的発展が進むことを考えれば、17世紀力学におけるデカルトのこの先駆的な役割は認められるべきでしょう。
これらのことを考えてみれば、特にニュートン力学の限界を知った現代物理学にいたる長い力学史の中で、デカルトの占めている位置は正当に評価されるべきだと思います。これがニュートンの力学的構想とは違い、直接ニュートン力学を支えるものではなかったからといって、見て見ぬふりをすることは適当ではないでしょう。むしろデカルトの力学的構想は、ニュートンの力学を別の視野から補足してゆく役割を持つものでした。そしてまたこのデカルトの存在を考慮してみればこそ、17世紀の力学史についても、その豊富な歴史的内容の一端を知ることになったはずです。
私たちはこれまでガリレオとニュートンとのあいだに介在するデカルトに目を注いできました。これは特にデカルトだけを重視しようという意昧ではありません。17世紀の力学史が、ニュートンヘたどり着く一筋の経過だけに要約してしまえるものでないことを言いたかったのです。
数学的自然学の形而上学的基礎づけ
デカルトは、物質的事物の本質はどのように認識されるか、ということを検討しました。考察の末、彼が得た結論は、物質的事物の本質の認識も、感覚や想像力によってなされるのではなく、人間知性の内に与えられてある数学的対象である、幾何学的延長、つまり空間の観念によってなされるということです。
しかし、人間が自分の知性の内に見出される数学的対象の抽象的観念に従って立てる理論が、なぜ、人間の外なる物理的自然に実在的に対応するといえるのかわかりません。
デカルトは、全能の神の形而上学(けいじじょうがく)に訴えて、全能の神なら、我々人間が自分の知性によって明晰判明(めいせきはんめい)に理解できる数学的対象を、物理的自然の内に、その実在的構造を構成するものとして創造し、設定しえたはずである、という観念の生得説によって答えました。
このような数学的対象の「生得説」の主張によって、デカルトは、アリストテレス自然学の基礎となる経験論的認識論を排除し、人間精神は、感覚や想像力と独立に働き、人間知性の内に与えられてある数学的対象という抽象的観念に従って物理的対象の本質を究明することが可能である、という見地を立てようとしたのです。
デカルトは、全能の神の形而上学に訴えて、神が我々人間の内に数学的対象を創造して刻印するとともに、それによって物理的自然の法則(自然法則)を構成したというテーゼを提示しました。このテーゼによって、我々人間の知性の内に見出される数学的対象と、物理的自然を構成する構造とは、原理的に対応すると考えてよいことになります。我々人間は、我々の内に見出される数学的観念に従って、感覚経験に依拠することなく、物理的自然の構造を理論的に究明していけることになったのです。
ハーベーとデカルトの生理学
ウイリアム・ハーベー(William Harvey)(1578~1657)は実験によって心臓の自発的運動がその収縮にあることをエレガントに証明したのですが、デカルトの説明はこれと反対しました。それにもかかわらず、デカルトは自らの見方は心臓の諸部分の配置から必然的に結論されるものであると強調しました。彼はそれを、時計の運動がその歯車の配置から必然的に生じることになぞらえました。デカルトの考える心臓の火は、非生物にときどき見られるように、光を出さずに燃える火と同等と考えられています。デカルトは発酵を念頭に置いていたようですが、発酵が微生物の活動を原因として起きることは、当時まだ知られていませんでした。この心臓の火こそ、すべての身体運動の起源であるとしました。
デカルトはそのまま思弁的な生理学理論を構築する作業に着手しました。そこでは動物や人間の体が、水圧で働く複雑な自動機械との類比で説明されています。彼はその心臓と血液の運動の理論を『方法序説』(1637年)の中で発表しています。機械論的生理学の見本を示す意図からでした。デカルトの考え方は大きな影響をもたらしました。生命現象を機械論的に説明する試みは、17世紀を通して支持を広げてゆきました。
我々の世界観は動物機械論という機械論的な考え方に規定されている部分が多いようです。それは生物学でも医学でも変わりありません。その点で、デカルトなどに見られる機械論的生理学は、現代の生命科学の起源と考えることができます。
この方面でのデカルトの出発点は、ハーベーによる心臓と血液の研究でした。デカルトはハーベーの説からその生気論的要素を取り去り、彼の心臓運動の説明を無視して機械論的な血液循環論を考えました。ハーベーはクラウディウス・ガレノス(Claudius Galenus)(129頃~200頃)の説に反対していました。ハーベーはガレノスとは逆に、心臓の自発的運動はその収縮期にある、としました。彼は、心臓の運動自体は血液に内在する生気によって、引き起こされ維持されると考えていました。彼にとって血液は、自ら脈動するものでありました。デカルトはこのような説を受け付けませんでした。デカルトは代わりに生物の内在熱という旧来の考え方に従い、心臓の左心室に火に似たようなものが存在すると考えました。冷たい肺から左心室へと入った血液は直ちにそこの内在熱により気化し、そうして心臓を急激に膨張させます。そのとき気化した血液は大動脈を通って動脈系へ入っていきます。心臓は収縮し、同時に肺から新しい血液が供給されて再び同じ過程が始まる、とデカルトは考えました。
デカルトは、認識論や形而上学の領域で心身の二元論を打ち出しました。他方で、彼は身体や身体に関わる心的活動について、歴史上初めて、機械論的自然学、つまり物理学のみに基づく神経生理学や脳科学の構想を提示したとしました。
デカルトが提示した神経生理学や脳科学は、彼の宇宙論的物理学と同様に、全体として、構想の域を出るものではなく、それが提示した具体的な理論は訂正されざるをえないものでした。現代の神経生理学や脳科学を、物理学や化学との連続上で、神経生理の機能や脳の活動を探求しようとする見地の起源は、デカルトです。その点を確かめておきましょう。
デカルトは、血液循環について、機械論的見地から、心臓を、そこで血液が熱せられる一種の熱機関とみなすことで説明しました。しかし、これは誤りで、心臓をポンプのような機能を果たすものとしたハーベーの説が正しかったのです。
ハーベーは、人間だけでなく他の動物にも共通に認められる、筋肉運動や感覚知覚や認知活動全体を、古代の医学者ガレノス以来、血液に加わる生命物質の一種として採用されてきた「動物精気」という概念に訴えて説明しました。しかし、デカルトは当時の医学史上の決定的な変革をもたらしました。この動物精気の概念の意味を本質的に変容し、「動物精気」から生命的意味を剥奪して、純粋の物体であるとしたのです。デカルトによれば、「動物精気」とは、血液が心臓で熱せられて希薄化したきわめて微細な物体であり、それだけが、脳の空室に入ることができ、脳室を満たして多様な運動を行うことができるとしました。
このようにデカルトは、自分自身が切り開いた生理学的分析から、心の状態と身体の状況とのあいだの「偶然性」を解消しました。それを根拠として、精神は心身の関係を統御しうると考え、意志の働きは、精神から発し、その意識は、精神を原因として持つとしました。
デカルトは、一方で、歴史上初めて、物理的自然のみならず、脳を含む人間の身体全休を、機械論的に解明する見解を提示し、「考えるもの」としての「私の心」は、その自然には属さないとしました。
自由意志の存在について
「懐疑的」、あるいは「自明」と思われることに対して、「同意しない」という行為を理解しようとすることは、「能動的な意志」のありかたにほかならず、意識を能動的意志として把握しようとすることです。デカルトは実際に、彼の方法的懐疑(methodical doubt)によって、「私は考える」の「思考意識」のありかたを提示しただけではなく、「何ものにも同意しないことができる」という自由意志の主体的意識をもたらしました。デカルトにとって意志決定とは、さまざまな選択肢をもち、自明と思われる事柄にも同意しない能力を持ち合わせた上で、一つを選択するという、「自由意志による決定」なのです。デカルト的な意識とは、「自由意志」の「主体」の意識と不可分なのです。この自由意志をどう理解し、受けとめるかという問題は、「意識」をどう把握するかという問題に直結しています。
「懐疑」、あるいは、普通に自明と思われることに対して「同意しない」という行為に関して、心の意識を理解しようとすることは、「能動的な意志」のあり方にほかならず、意識を「能動的意志」のもとに把握しようとすることです。このことは、「自明と思われる対象」に対して「同意しないこと」が可能と考えることができます。我々は対象に対して「肯定することも否定することも可能」です。「意志決定」とは、複数の選択肢から一つを能動的に選択することであるとする、「自由意志の存在」を認める立場に立つことです。
我々は普通の、つまり素朴心理学に従えば、「心」の存在を暗黙の内に認め、それが物体のように空間的に広がっているとは思っていません。我々は、心を物体のように空間上に広がっているものと考えない限り、心と物体との根本的異質性を受け入れているのです。そうであるならば、我々は、「私が私の腕を動かす」ということの特異性を実感として認めながら、非空間的な「心」の存在と、空間的広がりをもつ物理的世界との二元論を受け入れていることになるのです。
私は、デカルトの心の哲学をベースにして、「意志」の「選択の自由」を積極的に認めます。第一に、我々は、およそ我々が思考の対象とできるものについては、常に意志的に「疑う」ことができ、それに「同意しない」ことができるということに基づきます。我々は、ある体系をどこまで知的に理解しても、その上でそれに同意せず、場合によってはその理解にそむくことができるのです。我々は、ある事柄を肯定するとき、その事柄を選択して肯定するという「選択決定」の意識を持ちます。その行為の身体的遂行において、「私の精神が私の身体を動かす」という「心的因果の効力」を実感します。
その場合、自由意志を我々の判断や行為決定の「原理」にしているので、自由意志は幻想ではありません。我々は、自分の「選択」において判断し、行為決定を行うときには、自由を現実的なこととして体現しているのです。
我々が、「他者」に対して、我々の「自我」と同等の「他我」を認めるためには、第一に、他者が、自己意識や意図をもつということを理解することが不可欠です。第二に、他者との言語行為を介して、他者が、自分に対して、意図的に何をするかわからないということ、いいかえれば、私を喜ばすことも、欺くこともできる「自由な主体」であるということを理解することが決定的です。
我々は、犬や猫などのペットに対しては、我々と同等の心は認めません。それは、我々は、自分のペットが、我々をなごましてくれる存在であっても、我々と同じ言語を使って、意図的に我々を欺くことなどできないと知っているからです。
我々が、「他者」に、自分と同等の「私」を認めるためには、他者との関係で「受け身」を経験することが必要なのです。こうして、「他者の心の存在」を認めるためには、第三点として、「言語行為」を介する「相互的関係」が不可欠であるということです。そのことによって、我々は、「他者」に対して、私の「自我」と同等の「他我」を認めることができるのです。「他者」に「自我」を認めるには、相互の言語行為を介して、他者の活動の内に、合理的な意図をもつが、何をするか予想しえない、「自由な行為者」を感知することが決定的なのです。
私の意見
アメリカの哲学界では、心の哲学 (philosophy of mind) というものが、大きな領域を占めるに至っています。そこでは、まず「デカルトの心身の二元論」が取り上げられ、「実体としての心」の説が検討されるようです。そして大抵、「心」を「物体から独立な実体」とするというのは、現在大きな影響を行使している「物理主義」や「自然主義」のもとで、悪い意味で「形而上学的」、場合によっては「神秘主義」と裁断されてしまうことがあるようです。
私は、身体である脳から直接発生した心と、心からさらに発生した心の区別が軽視されていると思います。身体的な心は脳から直接発生しますが、その心は自らの身体を存在させるような行動を自らにとらせます。心から発生した心とは、身体である脳から直接的に発生した心よりも、さらに長く自らの身体を存続することを可能にさせるような心を発生させ、身体を、その思いに従うように行動させます。このような高次元である社会的な心を持つことが、自らの存在を安定させ、自分自身が現実世界へ存続する時間をさらに延長するということを自らに悟らせます。
デカルトが考えた、血液に加わる生命物質の一種として採用されてきた「動物精気(animal spirits)」という概念について、これは現代でいう情報伝達物質であるホルモンなどの各臓器の機能を関連づける役割を持つ物質を想定したのではないでしょうか。当時の医学的な技術の限界で発見することはできませんでした。私は医師ではないので、これらのことに関して十分な知識はありません。デカルトの生理機能についての説明が、どの程度正確に説明されているか判断を下すことができません。たとえそれが、現代の医学的な説明から外れている説明であったとしても、人間の意志による生理機能と無意識に自動的に制御されている機能があることをデカルトは分けて考えていたということが伺えます。
意識もしくは精神が人体の機械的な生理機能に及ぼす影響などに考察してみると、人体には、自動機械としての生理機能が意識とは関係なく、自動的に運用されています。しかし、精神もしくは心の在り方によってその制御の仕方が変わり、生体にいろいろな変化が現れます。そのことを、デカルトは当時の時代に合わせた医学知識で詳細に説明しています。デカルトは人体の解剖などに何度か立ち会って研究しています。
また、筋肉には、自分の意識で動かすことができる「随意筋」と意識的には動かすことのできない「不随意筋」があります。例えば、腕を挙げたり、脚を伸ばしたりする動作で使用する骨格筋は、動かそうと思って動かすことができるので、随意筋となります。それに対して、心臓や内臓は自分で動かしたり、止めたりすることができないので、心筋や平滑筋は不随意筋となります。人間の生理機能は、人間の意志に関係なく自動的に制御されているものが多くあります。まさに自動機械と言われる所以です。
科学革命を一言でいうと、従来の知識に、「地球の外からの視点が加えられた」ということであると思います。デカルトの物理学は、いろいろな解説書を読むと、少し間違いがあると指摘されることもあるようです。しかし、デカルトは神から選ばれた人なのだから、彼の説明が正しく表現されている高次元の世界があると思います。デカルトは、実験によって得られたデータで、例えばガリレオのように法則を見出したのではなく、思惟することによって、もっと深い根本的な法則性を表現しました。したがって、彼の表現する世界はもっと深いところにあるのかも知れません。