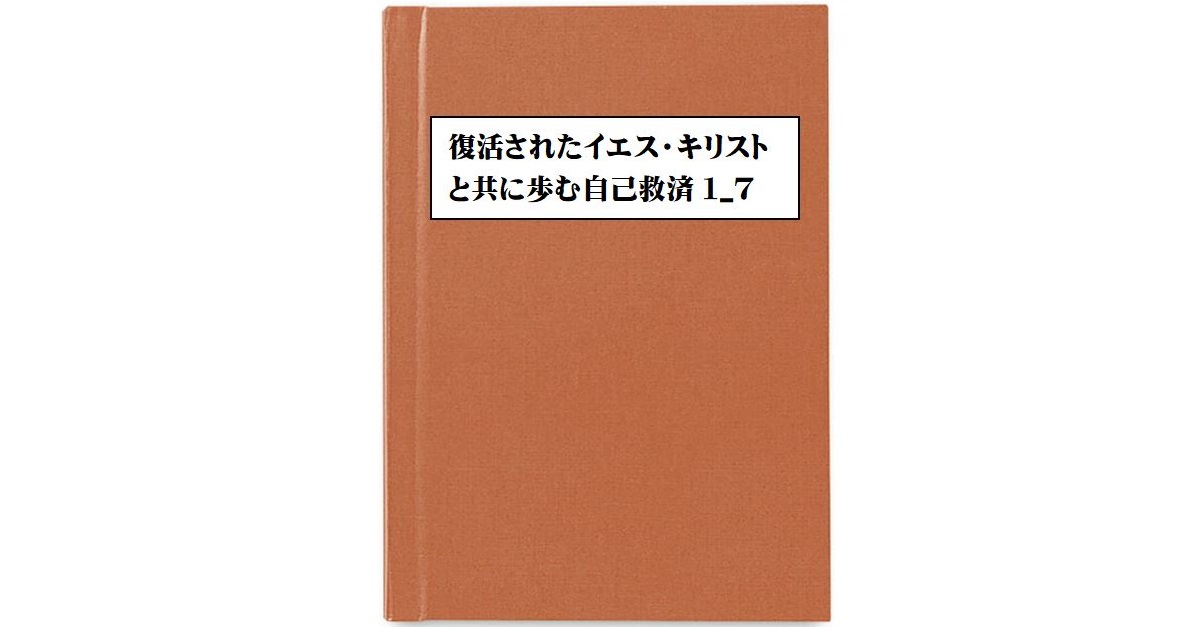科学と宗教
科学で宗教を語るとき、最も注目すべきことは奇跡でしょう。奇跡は宗教のカテゴリーに入ると思います。前の章で示しましたが、新約聖書に記載されている、イエス・キリストの奇跡の技は普通に考えると、日常生活ではまったくありえないことで、いうなれば非科学的で非常識であり、ひいき目に見ても、それは何かのたとえであり、別なことを表現した言い回しである、と思うでしょう。決してそれが真実を描写したものであるとは、非キリスト者の普通の日本人ならば思わないでしょう。
ところが、西洋の方々は、その聖書の記載されていることに、真っ向から取り組みました。その結果、よく知られているように、「近代科学はなぜ西欧のみに興ったのか」と研究されるくらいに注目されて、また、有名にもなりました。
私もそのように考えて、一体どのようにすれば、西洋人のような科学を創造できるのか、考えてみました。言ってみれば、それはやはり、脳の問題でしょう。それは、単純に頭が良いとか、悪いとかということではなく、イエス・キリストを受け入れる脳のような発想を持たなくてはならないだろうと考えました。参考にした文献から引用したものを、下記に記しておきました。
現実世界に生きる人間の脳の機能を科学的に考えるとき、宗教であつかう霊とか魂と、肉体である脳との関係はどのように考えたらよいのでしょうか。
「脳科学とスピリチュアリティ」の著者である、マルコム・ジーブスと、ウォレン・S・ブラウンは、著書の中で発言します。一般に、どの宗教においても、その宗教と関わりのある文化的特徴によって、人間の感情、思考、行為という形式が作られ、方向づけられると考えられています。心理学者はこうした形式を理解して、どのようにしてそれらが成長してきたのか、その主要な効果は何であるのかを示そうとします。万一、心理学者がこれに成功するようであれば、その成功によって、自分は究極の心理や価値についてのより広範でより深い問題について意見を述べる特別な権利を手にしたと思いたくなるのでしょう。こうしたことは、すでに多くの人々が述べているように、宗教の真理と価値は、自然の秩序が人間世界の秩序や被造世界との接触から生じると考えられています。また、その真理や価値そのものを、普遍的な人間の感覚では直接取得できないということを主張しているように思われます。
「科学が宗教と出会うとき」の著作者であり、アメリカの物理学者、神学者でもある、I.G.バーバー(Ian Graeme Barbour)は、次のように発言しています。
仮に人間の本性についての科学的主張と宗教的出張主張とが、互いに独立していて無関係であるならば、両者の間に対立はありえません。古典的な身体・霊魂二元論において、霊魂は非物質的であり、科学的研究は本来的に近づけないと言われます。最近のある著作家は、身体と霊魂とを、思想伝達の個別の二形態を指す用語であると考えているようです。つまり、身体と霊魂とは、対照的な機能を果たし、人間生活に相補的展望を提供するというものです。こういった見方は、聖書に見られる、本来のキリスト教の見方ではありません。(2023_3_6・修正)
後代のキリスト教に見られる身体・霊魂の二元論は、本来聖書自体には見当たりません。ヘブライ人の聖典において、自己は、考え、感じ、望み、そして行動する統一的活動体であるとしています。
イギリスの旧約聖書学者である、H・ウィーラー・ロビンソンは、次のように書いています。「人間の本性の理念は、二元論ではなく、統合体を暗示しています。これらの用語が直感的に示唆するような対照が、身体と霊魂との間にあるのではありません」。
ルター派のスイスの新約聖書学者のオスカー・クルマンは、これに同意し、次のように警告します。「本来、創造に関するユダヤ教やキリスト教の解釈は、身体と霊魂に関するギリシャ的二元論すべてを排除するものでした」。特に身体は、悪の源泉でも、あるいは否認すべきもの、逃れるべきもの、あるいは否定すべき何かのものでもありません。もっとも身体は、誤用されることがあるかもしれないけれども。我々はその代わりに、身体を容認し、物質的秩序を肯定的に受容します。
スリランカの神学者およびメソジスト派牧師のリン・ドゥ・シルヴァは、自著に次のように書いています。聖書には、ギリシャ思想やヒンドゥー教思想に見られるような人間の二元論的概念が存在しないことを、聖書学は極めて決定的に立証しています。聖書の人間観は、二元論的ではなく、全体論的であります。出生時に身体に入り、 死においてそれを残す、不滅の実在としての霊魂の概念は、聖書の人間観とは全く無関係であります。聖書の見解は、人間が統合体であるということであります。つまり人間は、霊魂、身体、肉組織、精神などの統合体であり、すべてが一つになって人間全体を構成するものと考えられています。
『解釈者の聖書辞典』によれば、ヘブライ語の単語「ネフェシュ」、通常、魂あるいは自己と訳されるこの言葉は、決して不滅の霊魂を意味するものではなく、本質的に、食欲と感情の主体、そして主体としての生命原理、あるいは自己という意味です。新約聖書において対応する言葉は、「プシケー」です。その言葉は、生命を意味する古いギリシャ語の語法を継承します。死後の生命への信仰が、新約聖書時代に展開したとき、その信仰は、霊魂の本来的不滅ではなく、神の働きによる全人的復活として表現されました。
ルター派のスイスの新約聖書学者のオスカー・クルマンは、死後の生命は、生得的、つまり、本来備わっている先天的なものとしての人間の特質ではなく、「最後の日における神からの贈り物」と理解されることを示しています。
新約聖書に登場するパウロは、物質的身体として、あるいは身体から離れた霊魂としてではなく、彼が「霊の体」と呼ぶものに身体が復活する裁きの日まで、眠る者としての死者のために表現した一時的な呼称です。(コリントの信徒への手紙一 15・44)このような死後の生命感は、キリスト教においては問題であるかもしれません。しかし、このような生命感は、人間の存在全体が、神の救済の目的の対象であるという信仰を証言するものと考えることができます。しかしながら、主にギリシャ思想の影響のために、初代教会において二元論が発展しました。プラトンは、先在する不滅の霊魂が、人間の身体に入り、肉体の死後に生き残ると考えていました。後期ヘレニズム世界におけるグノーシス主義運動やマニ教運動は、物質が悪であり、死によって霊魂が身体の拘束から解放されると主張しました。教父たちは、グノーシス主義を拒絶しましたが、新プラトン主義における霊魂と身体の二元論を受け入れました。そして全面的ではないとしても、それと結びついた善と悪との道徳的二元論を受け入れました。身体に対する否定的態度を示す記述がアウグスティヌスの著作に見られます。しかしこのような態度は、神の被造物としての物質世界を善とみる、聖書の証言からの逸脱を表しています。
13世紀にトマス・アクイナスは、霊魂が身体の形相であるという、アリストテレスの見解を受け入れました。そしてそのことは、身体のいっそう肯定的な評価を意味しました。アクイナスは、霊魂が身体以前から存在するというよりむしろ、神が着想を得た数週間後に、神によって創造されたと表現しました。動物は、「感覚的霊魂」を持っているものと考えました。しかし、ただ人間だけが、「理性的霊魂」を持っていると考えました。アクイナスは、人間の本性と道徳的行動に、複雑な分析を加えました。道徳的行動は、善を実行する際の感情「熱情」に対して、重要な役割を持たせました。善は、啓示と理性によって人間にもたらされます。中世の神学者は、神の目的に従って設計された、世界の有機的統合体という感覚を人間に表現しました。それにもかかわらず、不滅の霊魂という概念を表現したのは、人間と他の被造物の間に絶対的な線を引くためのものであり、世界における我々人間の地位に関して、人間中心的見解を促進させました。もっとも、全体的な宇宙レベルの組織においては、神中心でありました。ほとんど例外なく、人間以外の世界は、中世や宗教改革時における人間の救済劇において、補助的役割のみを演じるものとして描かれました。
精神と物質というデカルトの二元論は、さらに聖書の見解から離れました。聖書の見解がすでにそうしていたように、霊魂の概念は、少なくとも感情に対してある役割を認めていました。けれども、デカルトの理解における精神は、感情よりもどちらかというと、理性によって特徴づけられる非空間的かつ非物質的な「考える実体」でありました。他方で物質は、空間的で物理的力によってのみ制御されるとしました。しかし、似ても似つかない、精神と物質というデカルトの二元論における二つの実体は、どのようにして相互作用することが可能なのか、想像することは困難でした。デカルトは、動物は理性を欠いており、知能、感情、あるいは意識性を持たない機械であると主張しました。
多くの神学者が、身体と霊魂の二元論を擁護し続けました。カトリック教会の公式的見解は、人間の身体は、霊長類やヒト科原人の身体から進化しましたが、人間の霊魂は、進化論的歴史における特定な時点において、それを受け取る準備ができている身体に導入されたと言うものであります。 1996年の回勅において、教皇ヨハネ・パウロ2世は、進化が「仮説以上のもの」であると述べました。なぜならば、進化は多くの独立した研究路線によって支持されてきたからであります。教皇は同じく、人間の歴史を通じて、それぞれの霊魂は、「神によって直接に創造された」ことを再度確認しました。
教皇以外他の注釈者は、霊魂が非物質的であり、それゆえ古代化石の研究や現代人の脳の科学的研究のいずれによっても、発見することができないと強調しました。彼らは、霊魂についての神学的言明が、科学的研究から得られないこと、そしてすべての科学理論から全く独立していると主張しました。(2023/4/7・修正)
宗教は、人間が作った文化の中でも相当古い部類のものであると思います。社会生物学者エドワード・O・ウィルソンは、宗教的実践が、人類の初期の歴史で有用な生存機構であったと考えられる、と言っています。なぜならば、そのような実践は、集団の結束に貢献したと考えることができるからです。けれども彼は、宗教が人間の進化の産物として説明されるとき、宗教の力は永遠に無くなるであろうし、宗教は、科学的唯物論の哲学によって、置き換えられるであろうと発言されています。
しかし、今回参考にさせていただいた「科学が宗教と出会うとき」の著作者であり、アメリカの物理学者、神学者でもある、I.G.バーバー(Ian Graeme Barbour)は、このことに関して次のように応えています。仮にウィルソンが一貫しているならば、科学の力も、進化の産物として説明されるとき、同じく徐々に衰えるでしょうと、彼に言わなければなりません。なぜならば、進化の力だけではいずれ終わりが来ることは神の決めた定めであるからです、と発言しています。 神学者フィリップ・ヘフナーは、我々人間は、神の継続する創造の進行プロセスの中で創造された、共同創造者であると考えることができると言っています。進化は、自由な被造物を創造し、それによって、さらなる創造的可能性の道を開いて行くということが、神の目的であり、また手段でもあります。我々人間は同時に、遺伝子と過去の歴史に制約される自然と文化の被造物でもあります。