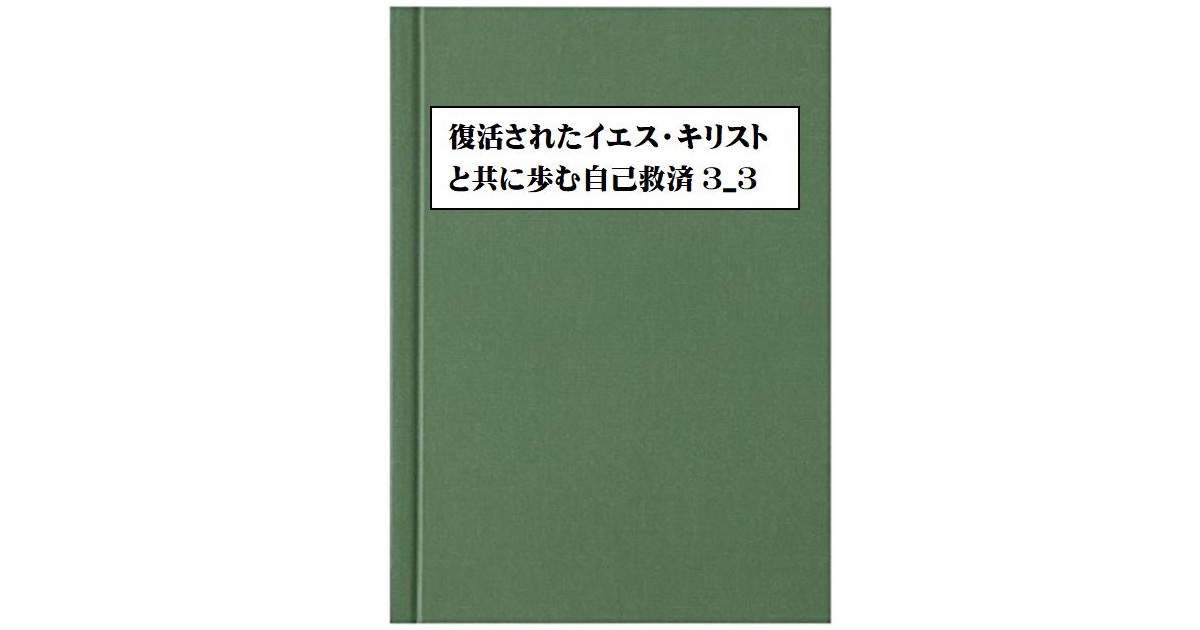ガリレオによる科学革命
イタリアの地にガリレオ・ガリレイが登場します。彼は、大きさ同じだが重さの異なる球を斜面で転がす実験を行い、物体の重さの違いにかかわらず、球が転がる速さを同じであることを突き止めます。それまで広く一般に信じられてきたアリストテレスの運動の法則では、物体は重くなればなるほど早く落下すると考えられていたため、この発見はアリストテレスの権威にひびを入れることになりました。
近代科学が目指したことは自然現象を数式化することであり、そこにはエネルゲイアを構成する重要な要素である事物の存在意義や目的といったものが立ち入る隙はありませんでした。むしろそうしたものを徹底的に排除することで、近代科学は自然の摂理を明らかにしようと試みたのです。こうして科学の世界からアリストテレスのエネルゲイアは消えてなくなり、エネルギーとは何者なのかを希求する新しい旅が始まりました。
ニュートン(力学)からジュールとケルビン卿(熱力学)へ
近代科学では当初、ガリレオの実験に代表されるように力学的な運動エネルギーのみを観察の対象としていました。その最大の成果が、アイザック・ニュートンが打ち立てた運動の3法則、そして古典力学の最高峰といえる万有引力の法則です。これらの物理方程式の左辺はすべてFとなっています。フォース(力)のFです。つまりニュートンが活躍した17世紀には、まだエネルギーという言葉は物理学の用語としては定着していませんでした。エネルギーという言葉が初めて使われたのは、19世紀になってからです。光の干渉実験を行ったことで有名なイギリスの物理学者トーマス・ヤングが用いました。 1807年に出版された彼の王立協会での講義録にその記録が残っています。しかしながら彼の用法は、依然として力学的な現象の説明に限ったものでした。
力学的な現象を越えたものの説明としてエネルギーという言葉が使われるようになるのは、 19世紀半ば以降の話です。ジュールの法則で有名なジェームス・プレスコット・ジュールや、原子や分子が運動を停止する温度(マイナス273度)を基準とする絶対温度K(ケルビン温度)にその名を残しているケルビン卿が活躍した時代です。この時代にようやくエネルギーをめぐる議論が、力学的な世界から熱を含むものへと拡大していきました。この時期に確立した熱力学第1法則、いわゆる「エネルギー保存則」によって、ついにエネルギーという言葉は現代的な意味において歴史の表舞台に姿を現すのです。
ジュールは水に浸した導線に電流を流し、水温の変化を測定する実験を繰り返し行い、電流によって発生する単位時間当たりの熱量Qは、流した電流Iの二乗と導体の電気抵抗Rに比例することを発見します。これが、世にいうジュールの法則です。電流と熱量に関係があることが証明されると、ジュールの関心は次いで、熱がどこからもたらされるのかに及ぶようになります。当時、熱に関する理解は定まっておらず、質量のない流体であるとする熱素説と、運動であるとする熱運動説がありました。歴史的には熱素説の方が主流でしたが、ジュールは熱運動説の方が正しいのではないかと考えておりました。そのことを検証するためにジュールは、おもりの重さで水中の羽根車を回し、その運動による水の温度上昇を精緻に測定するという実験を行っています。
こうしてジュールは熱は物質ではなく運動であると結論し、熱と運動の等価性を主張します。それは、熱と運動エネルギーはそれぞれの一形態であり、互いに変換が可能であるとする考えでした。こうして「エネルギー保存則」の骨格が形づくられるとともに、エネルギーという言葉が力学的な用法を超えて使われる土壌が整うことになりました。こうして成立した熱をエネルギーの一形態とする新しい学問分野は、ジュールの実験結果の価値を真っ先に見抜いたイギリスの物理学者ウィリアム・トムソン、後のケルビン卿によって「熱力学」と名付けられました。
マクスウェル(電磁気力)からアインシュタイン(原子力)へ
同じ時代、マイケル・ファラデーの活躍によって電磁誘導の法則が発見されて、運動エネルギーを電気エネルギーに変換できることが確認されます。こうして電気もまたエネルギーの一形態であることが明らかになりました。数学が得意だったマクスウェルは、ファラデーが実験から積み上げた電磁波に関する基礎理論を数式に組み上げることで、ファラデーの理論に数学的な裏付けを与えました。そして磁場が電場を生み、電場が磁場を生む循環によって空間そのものが振動して電磁波となり、エネルギーが伝達されることを示します。さらには、計算から得た電磁波の速度が光の速度とほぼ一致したことから、光が電磁波の一種であることを予言するに至ります。これはのちに周波数の単位にその名を残すことになるドイツの物理学者ハインリヒ・ヘルツによる実験で検証され、光もまたエネルギーの一形態であることが確認されることになりました。
アインシュタインが活躍した20世紀初頭、物理学における最大の課題は、物体の振る舞いを示したニュートン力学と、電磁波の振る舞いを示したマクスウェルの方程式との折り合いをどのようにつけるかにありました。マクスウェル方程式によれば、光を含む全ての電磁波の速さは、真空中、秒速30万kmで一定となります。しかしニュートン力学に基づけば、物体の速さには限界がありません。この矛盾に解を与えたのが、アインシュタインの頭脳でした。
彼は光速を常に一定に保つために、時間と空間が変化しうると結論します。こうして特殊相対性理論が発表されました。1905年のことです。実はこの理論には大変な副産物がありました。それがE = mc2(E : エネルギー、m : 質量、c : 光速度)の発見です。彼は静止している物体に左右から光が入射する様子を、静止した状態と移動した状態からそれぞれ観察する思考実験を行い、物体がエネルギーを吸収すると質量が増えなければならないことに気がつきます。この大発見により、驚くことに質量までもがエネルギーの一形態であることが分かったのです。
これは直感的には理解し難いことかもしれません。質量とは物の動かしにくさの度合いを表しますが、日常的には「重さ」として語られることの多い概念です。(厳密にはこの二つは異なります)重さはエネルギーである、といわれてもピンとこない人が多いのではないでしょうか。しかし科学的事実として、エネルギーは物体の運動や熱といった動的な形態だけではなく、静的な質量という形態をとることもあるのです。この時点で、エネルギーをめぐる議論は、完全に従来の力学の枠組みを超えました。
エネルギーの特性
科学の世界が解き明かしたこと。それはいってみれば、この世の全てはエネルギーでできているということです。物体も光も熱も、その全てがエネルギーの一形態なのです。私たちの周りにはエネルギーが満ち溢れています。実際、地球に降り注ぐ太陽エネルギーだけでも人類が使うエネルギー総量の1万倍以上に相当すると考えられています。そう考えていくと、エネルギーの確保に困ることなど起こりそうもないように感じます。人間の賢い頭をもってすれば、問題の解決は時間の問題というわけです。しかしながら、こうした技術革新への過度な楽観は人を思考停止に陥らせるだけです。エネルギー問題に正対し真摯に取り組むためには、エネルギーが持つ物理学的な特徴を理解し、その限界を知る必要があります。そのことを教えてくれるのが、熱力学の研究がもたらした成果です。
熱力学の第1法則――エネルギーは減りもしないし増えもしない
熱力学の第1法則はエネルギー保存則とも呼ばれるものです。エネルギーの相換性を示すことで、エネルギーはなくなりはしないが、増えもしないということを表しています。熱力学の第1法則が明らかにしたことは、無から有は作り出せないということです。技術革新を通じて人類がなしうることはただ、エネルギーを保持しているものから人類が使える形でエネルギーを取り出すことだけです。こうして、何もないところからエネルギーを作り出す永久機関は実現不可能であることが、理論的に証明されることになりました。
しかし、ここである疑問が湧きます。エネルギー保存則が働く世界では、確かに新たなエネルギーを何もないところから作り出すことはできないのでしょうが、一方で、一度使ったエネルギーであってもエネルギーそのものは保存され、決して消滅することはないはずです。したがって、再利用することが可能なのではないかという疑問です。このことは、永久に駆動し続ける永久機関の実現を依然として担保しているようにも思われました。
熱力学の第2法則――エネルギーは自然に散逸(さんいつ)する
熱力学の第2法則とは、誰でも経験的に知っている現象を表した法則です。それは、熱いお湯はやがて冷めるが、冷たい水は自然に熱くなることはない、という現象です。当たり前のことでしょう。この当たり前のことの重要性に初めて気がついたのはクラウジウスです。彼が着目したのは、熱エネルギーには一方向のみに進む、不可逆の方向性があるという事実です。
私たちは、摩擦や抵抗が存在する世界に住んでいます。そこでは熱エネルギーへの変換を止めることはできません。つまり私たちの住む世界においては、エネルギーは自然と散逸していくというひとつの方向性があるということになります。熱力学の第2法則は、その普遍的事実を表すものです。熱力学の第2法則の確立によって人類は、自らが有効活用可能なエネルギー源が有限であることを、科学的知見として理解できるようになりました。すべては、やがて熱となって散逸していくのです。投入されたエネルギーは最終的には質の低いエネルギーへとその姿を変え、広く散逸していくことになります。私たちは、熱力学第2法則から逃れ、自由になることはできない運命なのです。
エネルギー問題を考えるにあたって熱力学の第2法則を理解することの重要性がお分かりいただけるでしょう。しかしながら、熱力学の第2法則が私たちに教えているくれることはそれに留まりません。熱力学の第2法則が示唆することの豊穣さは、私たちの生活の隅々にまで及ぶのです。
エントロピーの登場
熱力学の特殊性を説明するために生まれた熱力学の第2法則は、やがて新たな言葉を生むことになります。それがエントロピーです。エントロピーと聞くと、エネルギー以上によく解らない科学の概念という印象もたれるかもしれません。しかし実際には、エントロピーの方がエネルギーよりも、よっぽど私たちにとって身近に感じられるものなのです。
エントロピーとは、熱エネルギーから運動エネルギーへの変換変化にかかるエネルギー損失の発生を説明するために、クラウジウスが1865年に考え出した概念です。熱エネルギーの持つ不可逆性を数値化したことで、エネルギーの質の問題を取り扱う熱力学の第2法則はひとつの完成を見るのです。新しい物理量の名前は、運動エネルギーと熱エネルギーの変換に関わるものであることから、ギリシア語で「変換」を意味する言葉(trope)から着想を得て、エントロピーと名付けられました。(2023/6/2・修正)
覆水盆に返らず――エントロピーが表すもの
エントロピーは、熱エネルギーの持つ不可逆性を表現する手段として、クラウジウスの頭の中で生まれました。エントロピーの発明は不可逆性の説明には役に立ちましたが、そもそも熱エネルギーがなぜ不可逆性の方向性を持つのかは依然として説明ができませんでした。要するに、エントロピーという物理量が何を意味しているのかは、謎のままだったのです。
エントロピーが真に意味するところを解明したのは、1844年生まれのオーストリアの物理学者ルートヴィッヒ・ボルツマンです。気体分子の運動と熱エネルギーの関係を研究していたボルツマンは、熱エネルギーとは微小な粒子である原子や分子によるランダムな運動の集合体だと考えていました。温度が高くなればなるほど、原子や分子が激しく運動し、熱を持つのがだと解釈したのです。やがて彼は、ミクロな現象である気体分子の運動、マクロな現象である熱エネルギーの関係を統合するために、確率や統計の視点を取り入れ、エントロピーとは原子や分子のランダムな運動がもたらす「乱雑さ」の尺度であることを論証する論文を書きます。1877年のことでした。この論文は、すべての原子や分子がランダムに運動していれば、個々運動は細かく複雑すぎて解析できなくとも、全体の状態については、統計的に高い確率で予測できることを示した画期的なものでした。
当時はまだ実在することが確認されていなかった原子や分子の存在を前提としたうえで、 新しい学問である確率や統計の知識を駆使して構築された彼の理論は、あまりにも斬新であったがために徹底的に批判されることになります。ボルツマンはあまりの批判に徐々に精神を病むようになり、最後には自殺してしまいました。しかし、彼の死後ほどなくして原子や分子の実在が証明され、確率と統計を駆使した彼の理論の正しさも証明されることになります。彼が切り開いた学問は、のちに統計力学と呼ばれるようになりました。
エントロピーを学ぶことで得られる最大の気づきとは、資源の有限性を知ることです。熱力学の第1法則によって保存されているはずのエネルギーがなぜ有限とされるのか。それはエネルギーには質の問題があり、私たちが本当に必要としているものは、エネルギー資源のなかでも低エントロピーの資源であるからです。それゆえに、資源は有限なのです。
「時間」は人類が生み出した
近代科学の発展により見出された数多の法則の中で、熱力学第2法則、すなわちエントロピー増大の法則ほど、示唆に富む法則は存在しないといえます。このことは繰り返し強調しても強調し足りません。このことに触れる核心的な事例となるのが、私たちの暮らしに根付いている「時間」とエントロピーの関係です。私たちが考える「時間」とは、過去から現在、未来へと進んでいく一方向の不可逆過程のことです。このことを20世紀前半に活躍したイギリス天文学者アーサー・エディントンは「時間の矢」と呼びました。
私たちがこうした時間の流れを感じ取ることができるのは、実のところ熱力学の第2法則が存在し、事物が散逸していくことで世の中が一方向に流れていくからなのです。しかしながら、こうした不可逆な流れが確実に認識されるのはマクロな世界に限った話で、原子レベルのミクロの世界ではその存在が途端に怪しいものになります。熱エネルギーの実態を掘り下げることで、そのことを考えてみましょう。
エネルギーが散逸し、劣化していくことを決定づけているのは、熱エネルギーの存在です。熱エネルギーとは、原子や分子の大集団が乱雑に動き回ることで生じる運動エネルギーの集合体です。では、この運動が仮に1つの原子だけからなる場合は何が起こるでしょうか。どの方向に動くにしろ、1つの原子は1つの方向にしか進みません。乱雑な動きは生じようがなくなるはずです。1つの原子のみによる運動は、運動エネルギーであって熱エネルギーではありません。つまり、1つの原子や分子だけをとりあげるミクロ世界には、熱エネルギーは存在しないということになるのです。
実は運動エネルギーを記述するニュートン力学や相対性理論の物理公式では、時間が一方向にのみ進むという縛りはありません。なぜなら、時間を反転させても式が成り立つからです。つまりミクロ世界においては、過去、現在、未来へと進む「時間の矢」が存在しているかどうかは、よく分からないのです。現代物理学の最先端の知識をもってしても、時間をめぐる問題には未だに答えが導かれていないのが実態です。
人類は、火の獲得によって進化した類まれなる頭脳の力を使って時の流れを記録し、「時間」というものを創造することができたゆえに、自分自身の存在を信じることができるようになったともいえるのです。デカルトが述べた「我、考える、ゆえに我あり」とは、正しくこのことをいっているのではないでしょうか。さらには、過去、現在、未来という時の流れを認識したことで、人は自らの未来は自らの意思で切り開いていくことを知ることになりました。人類は時間を創造したことで、未来を創造する力をも得たのです。このように考えていくと、「時間」とは身近な存在でありながら、同時に実に奥深いものであることが分かります。その存在を支えているものも、熱力学第2法則、すなわちエントロピー増大の法則なのです。
地球環境と熱エネルギーの関係
確かに人類が大量にエネルギーを使うようになった結果、大気に吐き出される人類起源の排熱エネルギー量は加速度的に増加しています。実際、人口が集中する都市部ではその影響が顕在化しており、人工構造物の影響もあって、一般に「ヒートアイランド現象」という名前で知られる高温化現象が起きています。しかし、地球規模での温暖化ということになると話は違ってきます。地上には人類が使うエネルギーの1万倍を超える規模のエネルギーが太陽から降り注いでいます。 したがって、人類の活動によって放出された排熱エネルギーそのものが地球環境全体に与える影響は、極めて軽微なものであると考えられています。
気候変動、地球温暖化への影響としては、温室効果ガスである二酸化炭素やメタンガスの増加に伴う温室効果の影響の方が圧倒的に大きくなります。それは温室効果ガスの存在が、太陽エネルギーを地球が受け取り、やがて宇宙へ放出するという大きなエネルギーの流れそのものを詰まらせるからです。
熱を運ぶ方法には3つの方法があります。伝導、放射、そして対流です。温室効果は熱の放射に絡んでいます。熱放射とは、ある物体から出た電磁波を別の物体が吸収することによって熱が運ばれることをいいます。電磁波による熱の伝達であることから、真空中でも熱を伝えることができるのが特徴となっており、その恩恵を最大に受けているのが地球に住む私たち生物です。仮に地球に温室効果のある大気が存在しなければ、どうなるでしょうか。 日中に地面や海洋を暖めた熱は、夜になると地球地表からの熱放射によって、あっという間に極寒の宇宙へと出ていってしまうことになるでしょう。大気がほとんど存在しない月において、昼と夜の温度差が200℃を優に超えるのはこれが原因です。
しかし、地球には水蒸気、二酸化炭素、メタンといった温室効果ガスがある気体を含む大気が十分に存在しているおかげで、一定量の熱がそこに留められ、地球環境は生物が生存しやすい温度帯で安定しているのです。 このように温室効果ガスは、私たち生物にとってなくてはならないものですが、降り注ぐ太陽エネルギーの量は莫大なため、そのバランスが少しでも崩れてしまうと地球から宇宙へ放出されるエネルギーの流れが詰まり、温暖化が加速してしまうことになります。温室効果ガスの一つである二酸化炭素が、人為的な活動によって増加していることが心配されているのは、それが理由です。