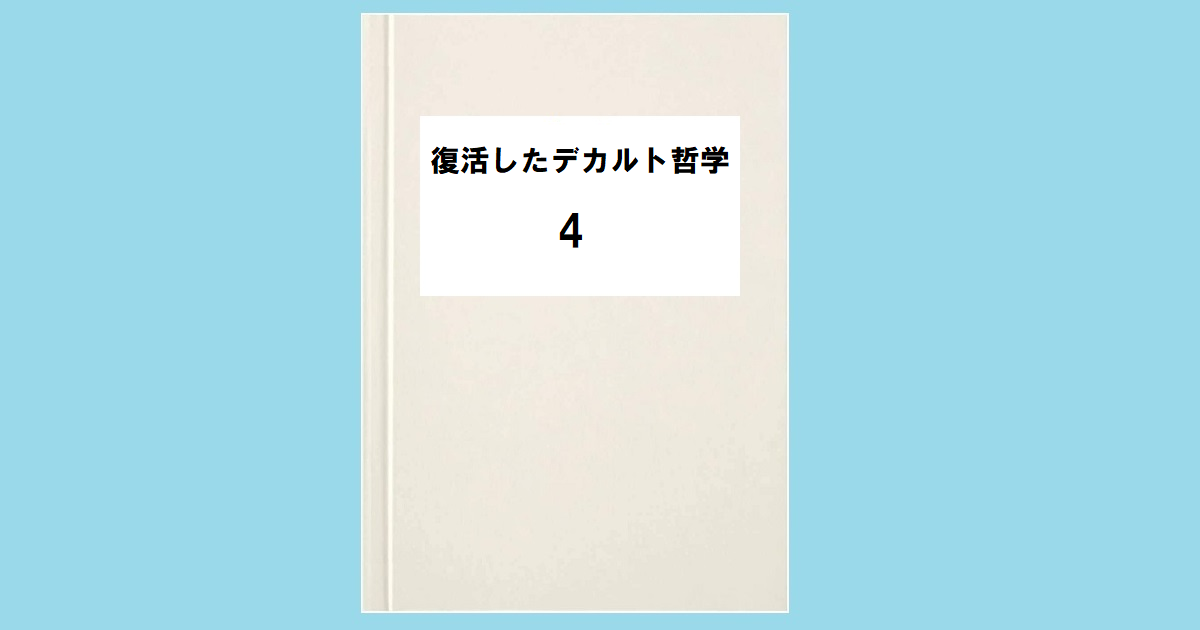(デカルトの哲学を現在の視点で再考して得た真理 4)
第三部
意識の宇宙 物質はいかにしてイマジネーションになるか
| コンティンジェンシー Contingency 「偶然性」「偶有性」「不確実性」 「偶発事件」「不慮の事故」などのこと。 依存する」という意味もあります。 「コンティンジェンシー理論」という言葉がありますが、日本語では「環境適応理論」と訳されます。世の中には、さまざまな環境が存在しますが、唯一で最良なシステムというものは存在しないので、環境が変わればシステムも変わるべきだとする理論です。 | ダブル・コンティンジェンシー Double contingency これは「二重の条件依存性」と同じ意味です。 選択するということは、他でありえた可能性の否定であり、その意味で二重の否定です。自分自身が他者を自らにとっては不透明なもう一人の自分として体験することによって、選択において否定された潜在的な可能性が、自分と他者の双方において相互的に、現実化はされないが含意はされている可能性として保存され安定化される。こうした事態を、ルーマンはダブル・コンティンジェンシーとしました。 | ||
| 1 | 存在論 | 認識論 | |
| 2 | 継続 | 変化 | |
| 3 | 設計 | 最適化 | |
| 4 | 相対性 | 対称性 | |
| 5 | デジタル | アナログ | |
| 6 | 環境 | システム | |
| 7 | 因果 | 循環 | |
| 8 | 有限(時間) | 無限(空間) | |
| 9 | 階層 | ネットワーク | |
| 10 | 多様性 | 唯一性 | |
| 11 | 死 | 復活 | |
| 12 | 統一(調和) | 一致 | |
| 13 | 俗 | 聖 | |
| 14 | 体(物質) | 魂(生命) | |
| 15 | 体験 | 知識 | |
| 16 | 物 | 言葉 | |
| 17 | 価値 | 意味 | |
| 18 | 現象 | 原因 | |
| 19 | 考える | 感じる | |
| 20 | 最後まで | できるところまで | |
| 21 | 相対性理論 | 量子力学 | |
| 22 | 粒子(量子力学) | 波(量子力学) | |
| 23 | 質量 | エネルギー | |
| 24 | マクロ | ミクロ | |
| 25 | 自然科学(自然側からのアプローチ) | 社会科学(人間側からのアプローチ) | |
| 26 | 運 | 技術(確率) | |
| 27 | (記憶力)自己認識 | 想像力 | |
| 28 | 進化 | 創造 | |
| 29 | 形状 | 機能 | |
| 30 | (過去から現在まで)これまで | (現在から未来へ)これから |
※この表についての説明は、過去の投稿記事に記載されています。詳しく知りたい方は、そちらをご覧ください。
第三部で引用させていただいた文献
A Universe Of Consciousness: How Matter Becomes Imagination (English Edition)
Gerald M. Edelman (著), Giulio Tononi (著)
序文
意識は謎であると同時に、謎の源であると考えられてきました。それは哲学的探究の主要な対象の一つですが、最近になって、実験的研究に値する科学的対象の仲間入りを果たしました。すべての科学理論が意識を前提としており、その適用には意識的な感覚や知覚が必要であるにもかかわらず、意識そのものを科学的に調査する手段が利用できるようになったのはごく最近のことだからです。
物理学者が物体を観測するように、意識を直接観測することができません。内観だけでは科学的に満足できるものではないし、人々が自分の意識について報告することは有益ですが、その根底にある脳の働きを明らかにすることはできません。また物理的な脳の研究だけでは、意識がどのようなものであるかを客観的に伝えることができません。このような制約から、意識を科学に取り入れるには特別なアプローチが必要であることがわかります。
私たちの答えは、意識はある種の生物の物質的秩序の中で生じるという仮定に基づいています。というのも、より高度な脳の機能には、世界や他の人々との相互作用が必要だからです。私たちは、この文章を読み終わる頃には、物質がいかにして想像力となるのかについて、新たな見解を持っていることに気づくことを願っています。
世界の結び目
現代において、私たちは意識経験の世界が脳の繊細な働きに密接に依存していることを認識しています。意識は、脳のある部分における、わずかな病変やわずかな化学的不均衡によっても消滅する可能性があります。実際、脳の活動様式が変化し、夢のない眠りに落ちるたびに、私たちの意識は消滅しています。
世界全体といえども、私たち一人ひとりにとっては意識の一部としてしか存在していません。それらは意識が消滅すると同時に消滅します。主観的な体験が客観的に記述可能な事象と、どのように関係しているのかという謎に包まれたこの謎を、アーサー・ショーペンハウアー(Arthur Schopenhauer)(1788~1860)は見事に「世界の結び目」と呼びました。
意識とは、哲学的パラドックスか、それとも科学的対象なのか?
意識というテーマは、かつては哲学者の専売特許でしたが、最近では心理学者と神経科学者の両方が、心と体の問題として、あるいはショーペンハウアーの示唆に富んだ言葉を借りれば 「世界の結び目」として注目し始めています。意識とは何かは誰もが知っていますが、毎晩眠りにつくとあなたを捨て去り、翌朝目覚めると再び現れるものです。
デカルト以来、意識の謎ほど一貫して哲学者の頭を悩ませてきたテーマはありません。デカルトにとっても、意識があるということは「考える」ということと同義でした。デカルトが『第一哲学の省察(Meditations on First Philosophy)』(Meditationes de Prima Philosophia)において哲学の基礎として提起したコギト・エルゴ・スム(cogito, ergo sum)、すなわち「我思う、ゆえに我あり」は、存在論(What is)と認識論(What and how we know)の両方に関して意識の中心性を直接的に認識するものでした。現実的な言い方をすれば、その出発点は、物質よりも心を重視する観念論的な立場につながります。しかし心を出発点とする観念論的な哲学は、物質を説明するために苦労します。
物質を出発点にする理由
デカルトは、精神と物質には絶対的な区別があると主張しました。物質の特徴は、空間を占め、物理的な説明が可能となるように拡張することです。一方、心の特徴は、意識すること、あるいは広い意味では考えることです。デカルトは、このような二元論を提唱しました。これは科学的には納得のいかない考え方ですが、心と身体の関係を説明しようとするためには、直感的に単純で魅力的な考え方のように思えます。
意識の起源を見極めようとする哲学的努力には、根本的な限界があります。それは、意識の源は考えることだけで明らかにできるという、思い込みから生じている部分があります。この仮定は、科学的な観測や実験がない中で、宇宙観や生命の基礎、物質の微細構造を理解しようとする旧時代の努力と同様に、明らかに不十分です。
また、意識が科学的対象として、いかに特殊であるかを考えれば、このような誤りが生じるのも当然かもしれません。これから私たちは、意識は物体ではなくプロセスであり、この観点から見ることによって、「意識は科学的対象に値する」という見解を示します。
意識の特別な問題
科学は常に、世界の記述から主観性を排除しようとしてきました。しかし、主観性そのものがその対象だとしたら、記述から主観性を排除することは可能でしょうか?
私たちは普通の言葉で水を説明することができますが、原理的には、原子や量子の力学の法則の観点から水を説明することもできます。私たちが実際に行っているのは、同じ外的実体について、ありふれた記述と非常に強力で予測可能な科学的記述の2つのレベルを結びつけることです。液体の水、あるいは量子力学の法則に従って行動する原子の特定の配列、どちらのレベルの記述も、そこに存在し、意識的な観察者とは無関係に存在すると仮定されている実体を指しています。
なぜ私たちに意識があるのか、主観的で経験的な特質がどのように生まれるのかを説明したいのです。つまり、デカルトがあらゆる哲学の基礎となるべき最初の明白な証拠とした「我思う、ゆえに我あり」を説明したいのです。どんなに正確な記述であっても、主観的経験を完全に説明することはできないかもしれません。どのように説明しても、一人称の現象体験の発生を説明することは非常に難しいことなのです。
意識的観察者といくつかの方法論的仮定
意識の何が特別なのでしょうか。意識が特別なのは、他の科学的記述の対象とは異なり、意識の神経基盤を研究する際に特徴づけようとする神経プロセスは、私たち自身を指しています。したがって、他の科学的領域を研究するときのように、意識の観察者である私たち自身を暗黙のうちに排除することはできません。
意識を満足に説明するために使用するは、従来の物理的プロセスだけです。特に、意識はある種の脳の構造とダイナミクスの中で生じる特殊な物理的プロセスであると推測されます。物理的プロセスとしての意識経験は、ある種の一般的な、あるいは基本的な二つの性質によって特徴づけられます。一つは、意識体験は統合されており、意識状態は独立した構成要素に細分化できないということです。もう一つは、意識は高度に分化していて、人は何十億もの異なる意識状態を体験できるということです。科学的な課題は、これらの性質を同時に説明できる特定の物理的プロセスを記述することです。
人間の脳の実際の働きには、進化論に似た選択原理が、論理にしたがって動くよりも、ずっと前に適用されているようです。この考え方は現在、選択主義と呼ばれています。私たちの立場を要約すると選択主義は論理に先行します。選択主義的原理と論理的原理はそれぞれ強力な思考様式の根底にあることが予測されます。選択主義の原理は物理的な脳に適用され、論理的な原理は、脳を持つ個人が後から学ぶものであることを把握することが不可欠です。
普通の人の私的劇場:進行する単一性、終わりなき多様性
意識の神経基盤を説明するための私たちの戦略は、一般的な、つまりあらゆる意識状態に共通する意識経験の特性に焦点を当てることです。これらの特性の内で、最も重要なものの一つは、統合または単一性です。統合とは、意識状態がその経験者によって、いつでも独立した構成要素に細分化されることがないということです。この性質は、私たちが意識的に二つ以上のことを同時に行うことができないことと関係しています。例えば、激しい口論を続けながら小切手を合計するようなことです。 意識的現象学の範囲と多様性は、自分の経験と想像力の及ぶ限り、どこまでも広がります。それは我々のプライベートシアターです。こうした意識の領域を分類するための本が書かれ、その構造を読み解く試みに基づいて、哲学体系全体が構築されてきました。意識状態は、知覚、イメージ、思考、内なる言葉、感情、意志、自己、親しみなどの感情として現れます。これらの状態は、考えうる限りあらゆる細分化された組み合わせで起こります。視覚、聴覚、触覚、嗅覚、味覚、固有感覚(自分の身体の感覚)、運動感覚(身体の位置の感覚)、快感、痛みなどです。
意識と脳
主観的な現象学、つまり哲学に傾倒した一個人の意識的経験に基づいて、哲学体系全体が構築されてきたのは、人間の傲慢さの反映であるかもしれません。デカルトが認識し、出発点としたように、このような傲慢さは部分的には正当化されます。なぜなら、私たちの意識的経験こそが、私たちが直接的な証拠を持っている唯一の存在論だからです。
意識をプロセスとして理解するためには、脳がどのように機能するかを理解しなければなりません。脳の最も重要な特徴である解剖学的組織と、脳が生み出す驚くべきダイナミクスに焦点を当て、脳の有用な、しかし決して網羅的ではない全体像を示します。大雑把に書かれてはいますが、この項目は意識がどのように出現するかを理解するために必要なものです。
脳は宇宙で最も複雑な物体の一つであり、進化の過程で出現した最も驚くべき構造の一つであることは間違いありません。現代の神経科学が登場する以前から、脳が知覚、感情、思考に必要であることはよく知られていました。物体として、システムとして、人間の脳は特別です。その連結性、ダイナミクス、機能様式、そして身体や世界との関係は、科学がまだ出会ったことのないものです。私たちはその全体像を把握するには程遠いのですが、部分的な把握でも、ないよりはましです。
脳はコンピュータではない
神経解剖学と神経ダイナミクスを大雑把に見直すと、脳には組織と機能に関する特別な特徴があることがわかります。脳は人工の装置にはない方法で相互につながっています。第一に、脳の結合を構成する何十億、何百億という結合は正確ではありません。同じ大きさの二つの脳で、同じメーカーのコンピュータと同じように接続が同じかどうかを問えば、答えはノーです。最も微細なスケールで見た場合、一卵性双生児であっても、やはり二つとして同じ脳はありません。このような観察結果は、命令や計算に基づく脳のモデルに対する根本的な挑戦です。このデータは、いわゆる選択的脳理論、つまり脳の機能を説明するために、実際のばらつきに依存する理論に強い根拠を与えます。
練習からの教訓:意識的なパフォーマンスと自動的なパフォーマンス
たちの認知生活の多くは、高度に自動化されたルーチンの産物なのかもしれません。話すこと、聞くこと、読むこと、書くこと、記憶することに関して言えば、私たちは皆、熟達したピアニストのようなものです。私たちが文字を読むとき、フォントやサイズに関係なく文字を認識し、単語を解析し、語彙へのアクセスを可能にし、構文構造に配慮するなど、あらゆる神経プロセスが働いています。
私たちは確かに、文字や単語について意識的に手間のかかる方法で学ばなければならなかった時期がありました。私たちの脳がこのような大変な作業をどのように行っているのかは、まだほとんど解明されていません。私たちが意識的に二つの数字を足し合わせるとき、私たちは単に脳に要求を伝え、脳がそれを実行し、答えが返ってくるように思えます。記憶の中の項目を探すとき、私たちは意識の中で質問を組み立てます。私たちが知らないうちに、脳はしばらくの間探索を続け、突然、再び意識に反応が返ってくるようです。
私たちが大人になってからの生活には、このような自動化が蔓延しており、意識的なコントロールは、明確な選択や計画を立てなければならない重要な局面でしか発揮されないことを示しています。無意識のうちにルーチンが継続的に発動され、実行されることで、意識はあらゆる細部から解放され、物事の壮大な計画を立て、理解することができます。行動においても知覚においても、意識が利用できるのは、最後のコントロールや分析のレベルだけで、それ以外はすべて自動的に進行しているように見えます。この特徴から、私たちは脳内で行われる「計算」の結果を意識しているのであって、計算そのものを意識しているのではないと多くの人が結論づけています。
意識のメカニズム:ダーウィンの視点
これから脳の一次的意識に焦点を当てて、言語や真の自己意識を必要としない、現在における統合された精神的な情景を構築する能力について説明します。この統合された精神的な情景の感覚刺激の知覚的分類は、「現在」だけはありません。最も重要なのは、カテゴリー化された記憶、つまり「過去」との相互作用にも依存すると私たちは考えています。言い換えれば、この統合された精神的な情景は「記憶された現在」なのです。
晩年、チャールズ・ロバート・ダーウィン(Charles Robert Darwin)(1809~1882)は自然淘汰を共同発見したアルフレッド・ラッセル・ウォレス(Alfred Russel Wallace)(1823~1913)と激しく対立しました。ウォレスは心霊主義者であり、人間の脳や心は進化論的な自然淘汰によって生じたものではないと主張したのです。ウォレスは、未開人は文明人の脳とほぼ同じ大きさの脳を持ちながら数学を理解しておらず、抽象的な思考を十分にすることができないと主張し、進化論的な自然淘汰によって両者の脳の大きさが同じになったとは考えにくいと論じていました。
ダーウィンの進化論の原則は、脳の機能に関する基本的な理解においても重要です。特に、脊椎動物の脳の構造と機能には非常に大きな違いがあります。二人の人間の脳は、全く同じものはありません。さらに各個人の脳は絶えず変化していて、その変化は脳内の生化学から外形の形態に至るまで、あらゆるレベルに及び、無数のシナプスの強さは経験によって絶えず変化しています。この膨大な多様性の程度は、脳がコンピュータのように固定されたプログラムコードと登録情報で構成されているという概念を強く否定する根拠となっています。
価値観
意識を構成する要素の一つである価値は、人間の体に基本的な仕組みとして備わっているものです。価値が分類とは同一ではないことを強調することは重要です。価値とは、知覚や行動の反応に到達するための前提条件にすぎません。そのような分類的反応は、実際に選択が起こるかどうかに左右されます。知覚的なカテゴリー化は通常、現実世界での実際の行動中に選択の結果として現れます。価値は赤ちゃんの目を光源に向けるためには必要かもしれませんが、異なる物体を認識するためにはそれだけでは十分ではありません。
知覚から記憶へ:思い出される現在
意識の神経メカニズムを解明するためには、一次意識と高次意識との区別を念頭に置くことが有効です。一次意識は、我々と似た脳構造を持つ動物に見られます。これらの動物は心的情景を構築することができるように見えますが、意味能力や象徴能力は限られていて、真の言語は持ちません。人間にだけみられるもので、一次意識の共存を前提とする高次の意識には、自己意識があり覚醒状態において過去と未来の情景を明確に構築する能力があります。これには、最低でも意味論的能力、そして最も発達した形では言語的能力が必要です。
意識体験には、さらに二つの要素が必要です。一つは、価値に反応する類型的記憶の出現で、もう一つは高次脳における基本的な統合メカニズムである再帰性の活動です。我々は、再帰性を媒介する新たな回路の出現によって、知覚の分類化に関与する脳の後半の領域が、価値に基づく記憶を担う前皮質領域と動的に結びついたとき、進化の過程で一次意識が出現すると推論しています。そのような回路が備われば、動物は記憶された現在を構築することができます。すなわち、直前の出来事や思い描いた出来事を、その動物が価値主導で行動した過去の履歴に適応的に結びつけた、ある状況を構築することができるということです。
これらの意識体験のプロセスには、知覚的分類、概念、価値、記憶、そして神経レベルでは、皮質視床組織の特別な動的プロセスなどが含まれます。このような理解がなければ、さまざまな感覚、気分、情景、状況、思考、感情、感情など、一見同時に起こっているように見える複雑な経験が、脳に基づくメカニズムによって説明されるとしても、その複雑さゆえに絶望的に無関係なものとして見えてしまうでしょう。
一次意識のモデルに必要な前提条件
我々は、意識を分析する際、一度に多くの難しい問題に取り組んだり、その豊かな現象論に気を取られたりすることを意図的に避けます。この抑制に従って、私たちは一次意識と高次意識との有用な区別を重視しています。一次意識とは、現在あるいは直近の行動を指示する目的で、大量の多様な情報が統合された心的情景を生成する能力であり、私たちと同様の脳構造を持つ動物において見られます。
このような動物は、心の中で情景を構築できるようですが、私たちとは異なり、意味的または象徴的能力が限られており、真の言語能力はありません。我々人間だけが持つ豊かな高次の意識は、一次意識が提供する基盤の上に築かれ、自己意識と、覚醒状態で過去と未来の情景を明確に構築し、結びつける能力に支えられています。最も発達した形態では、意味的能力と言語的能力を必要とします。
このことから、高次の意識を持つ人間だけが意識状態を報告し、意識について語ることができます。彼らは自分が意識していることを意識的できるのです。以下では、主に一次的意識について考察しますが、実験的洞察が得られる場合は高次の意識についても取り上げます。最後に、高次の意識のより興味深い側面、思考、言語、自己概念、自己言及について取り上げます。
進化の過程で一次的な意識が現れるメカニズムのモデルを考える前に、いくつかの重要な神経プロセスを簡単に確認しておきましょう。それは、すべての動物が共有する特性である「知覚的類型化」です。これは、物理法則に従う環境において、世界を特定の種にとって有用になるように認識して、細分化する能力です。
一次的意識を理解するために必要な次のプロセスは、概念の形成です。ここで言う概念とは、ある場面や物体にまつわる、様々な知覚的分類を結びつけ、様々な知覚に共通する抽象的な特徴を反映した「普遍的な」概念を構築する能力のことを指します。例えば、異なる顔には多くの異なる特徴がありますが、脳はそれらに共通する一般的な特徴を認識することができます。
一次的意識のメカニズム
回帰のメカニズムと知覚的分類、概念形成、価値カテゴリーの記憶の概念を理解することで、進化の過程で一次意識がどのように発生したかをモデル化することができます。
一次意識の基本となる短期記憶は、過去のカテゴリー化された概念的経験を反映します。知覚的に新しいものは、過去のカテゴリー化から生じた記憶に短時間で組み込まれます。意識的な情景を構築する能力とは、数分の1秒という短い時間の中で、記憶された現在を構築する能力のことです。
このようなシステムを持たない動物も、特定の刺激に対して行動し反応することはでき、特定の環境下では生き延びることもできます。しかし、出来事や外部からの信号を結びつけて複雑な場面を構築し、価値に依存した反応の独自の履歴に基づいて関係を構築することはできません。場面を想像することもできず、複雑な危険を回避できないことがよくあります。この能力の出現が意識につながり、意識の進化的選択優位性の基盤となっています。
このようなプロセスが備わっていれば、動物は少なくとも記憶に残る現在において、価値に基づく行動の過去の履歴に基づいて、建設的かつ適応的に偶発的な出来事を計画して結びつけることができるでしょう。
膨大な情報に対処する:ダイナミック・コア仮説
私たちは意識の科学的分析では、意識経験の基本的特性、すなわち、あらゆる意識状態に共通する特性を考慮すべきだと提案しました。このような基本的特性には、次の二つがあります。第一に、意識は高度に統合または統一されており、全ての意識状態は独立した構成要素に効果的に細分化できない統合された全体を構成しています。第二は逆に、高度に分化または情報化されており、膨大な数の異なる意識状態が存在するということです。
意識的経験の基盤となる分散型神経プロセスも、高度に統合され、同時に高度に差別化されているという特性を持っています。私たちは、神経生物学と現象学がこのように一致するのは単なる偶然ではないと考えています。意識的経験の一体性と情報量を説明し、統合と分化という概念に確固とした理論的枠組みを与えることで、意識的経験の神経基盤に関する考えを、さらに発展させていきます。最初に統合と分化が何を意味するのかを明確にしなければなりません。次に、統合と分化が実際に脳内でどのように実現されているのか、より正確に扱わなければなりません。これらの分析結果から、私たちは「ダイナミック・コア仮説」と呼ばれる仮説を提唱します。これは、意識的経験の基盤となるニューロンの集団の活動が持つ特殊性を動作的に簡潔に示すものです。
統合と回帰
私たちが車を運転しているとき、視覚的な光景には、車、歩行者、木々、空など、さまざまな物体が存在し、視野内の特定の位置を占めています。また、物体は動き、特定の音や匂いを放つこともあります。これらの物体は、特定の意味のある方法で互いに関連し合う可能性があります。このように驚くほど豊かで多様な世界であっても、私たちが瞬間毎に経験するのは、統一された一つの意識的な光景であり、全体としてのみ意味を持ち、経験されている間は独立した構成要素に分割できない光景です。その光景は刻一刻と変化し続けています。
意識的経験の一体性や統合を説明する神経過程について、より完全な科学的理解を得ることを目指します。この目的のために、統合とは何を意味するのか、統合はどのように測定できるのか、統合された神経過程はどのように特定できるのか、を明確に定義します。このために、新しい概念である「機能的クラスタ」を導入します。
PETやfMRIなどの神経画像診断技術は、何百万ものシナプスや脳領域の活動を一度に調べることができますが、空間的・時間的解像度が不十分であるため、個々の神経信号の運命を追跡することはできません。このような相互作用する細胞の大集団の行動を調べるには、神経モデリングに頼らざるを得ません。大規模なコンピュータによるシミュレーションにより、複雑に絡み合ったシステムにおける個々の神経細胞の活動を追跡するだけでなく、例えば特定の視覚刺激が提示された後に、何万ものニューロンの発火の空間的・時間的パターンがどのように発達していくかを検証することが可能になりました。
このモデルで得られた結果について、最も重要な点は、物体の適切な属性の結合や統合によって正しい出力が得られるという結果が、特定の皮質領域や特定のニューロン群のどれか1つで得られたわけではないということです。したがって、統合は特定の場所で行われるのではなく、一貫したプロセスによって達成されるのです。このモデルでは、分散したニューロンの活動を統合するという驚くべき能力に加えて、私たちが自分自身の意識的な経験を考察する際に遭遇する特性、すなわち「能力の限界」を想起させる予期せぬ特徴がありました。
視床領域が相互に接続された、皮質領域の異なる、より詳細なモデルにおいて、私たちは視床皮質系内の再帰的相互作用のダイナミクスをさらに詳しく調査しました。これらのシミュレーションから得られた結果は、皮質内および皮質と視床間の再帰的シグナル伝達が、ネットワーク内のシナプス伝達効率と自発活動の急激な変化によって強化され、一過性のグローバルな整合プロセスを迅速に確立できることを示しています。このように、システム内の他の部分とは機能的に区別され、相互作用の強い要素の集合は、「機能的クラスタ」と呼ぶことができます。クラスタは内部の一体感と外部からの孤立という観点から定義されるべきであるという点では一般的に合意が得られています。
機能的クラスタリングの概念により、意識の根底にある神経プロセスを特徴づけるために神経生理学的データに適用できる統合の尺度を得ることができました。神経プロセスが機能的クラスタを構成するということは、ある一定時間において、そのプロセスが機能的に統合されていることを意味します。つまり、完全に独立した、あるいはほぼ独立したコンポーネントに分解できないということです。
意識と複雑性
私たちはいつでも、何十億通りもの可能性のある状態の中から選ばれた特定の意識状態を経験します。もしそうであれば、意識的経験の根底にある神経過程もまた、高度に弁別された情報的なものでなければなりません。このようなシステムの情報量は、「神経の複雑さ」と呼ぶ統計的尺度で表すことができます。この複雑さの尺度により、統合された神経過程の分化度合いを推定することができます。意識と複雑さが密接に関連していることを示すとともに、脳内で複雑さがどのように実現されているかを説明することです。
システムの一部の状態が他の部分に影響を与えるということは、システムが統合されていることを意味します。もしも、システムが統合されていなければ、システム内の異なる部分の状態は独立しているはずです。したがって、複雑性の高さは、システム内の機能的専門化と機能的統合の最適な総合に対応するという重要な結論に達します。これは、脳のようなシステムに当てはまることは明らかです。脳では、異なる領域やニューロンのグループが同時に異なることを行い、相互作用することで、統一された意識的情景と統一された行動を生み出しています。私たちは、視床皮質系の神経過程の複雑さは、その神経解剖学的構造だけでなく、神経生理学的構造によってもダイナミックに影響を受けると結論づけています。このダイナミックな性質により、同じ正常な脳であっても、覚醒レベルに応じて複雑になったり、単純になったりします。
脳の機能の複雑性に関するあらゆる専門家が一致して認める二つの側面があります。一つは、複雑であるためには、異種の方法で相互作用する多くの部分から構成されている必要があります。例えば、オックスフォード英語辞典では、複雑性を「さまざまな部分が結合または接続された全体」と定義しています。もう一つは、完全にランダムなものは複雑ではなく、完全に規則的なものも複雑ではないという見解が現在では一般的に受け入れられています。例えば、理想気体も完全な結晶も複雑ではないと考えられています。秩序と無秩序、規則性と不規則性、多様性と普遍性、不変性と変化、安定性と不安定性の両方を併せ持つものだけが、複雑と呼ばれるにふさわしいのです。細胞から脳、生物、社会に至るまで、生物システムは複雑な組織の典型例です。高い複雑性は、脳と潜在的な複雑性がはるかに大きい外部環境との継続的な相互作用に由来することがわかります。単純な線形系を使ったシミュレーションによると、ランダムな結合性を持つ系の複雑度は低いのです。しかし、外部環境の統計的規則性との適合性を高めるような選択手順によって、これらの系の結合性を変化させると、その複雑性は大幅に増大します。さらに、他のすべてが同じであれば、環境が複雑であればあるほど、一致度が高いシステムの複雑さも大きくなります。また徐波睡眠や全般てんかん発作のように、神経活動が全体的に均一、または過度に同期している場合に意識が消失することからも明らかです。
ダイナミック・コア仮説
私たちは、数分の1秒という時間スケールで、互いに強く相互作用し、脳内の他の部分とは明確に機能的な境界を持つ神経細胞群の集合体を「ダイナミック・コア」と呼び、その統合性と絶えず変化する構成性を強調しています。 ダイナミック・コアは神経の相互作用の観点から定義されるプロセスです。したがってダイナミック・コアは物でも場所でもなく、特定の神経の位置や接続性、活動でもありません。ダイナミック・コアは空間的に広がってはいるものの、分散しており、また構成も変化するため、脳内の特定の場所に限定することはできません。さらに、このような性質を持つ機能的クラスタが特定されたとしても、再帰的相互作用が十分に分化されている場合にのみ、意識的経験と関連付けられるものと予測されます。ダイナミック・コアの特性を視覚的に表現することは大変難しいことです。一瞬のうちに大量の情報を統合するには、高度に統合されながらも差別化された組織が必要ですが、我々の知る限り、そのような組織は人間の脳の中にしか存在しません。
高次の意識
意識と言語、思考、知識の限界との関係にはまだ明確に向き合っていません。私たちが示したように、この関係は高次の意識に基づいており、自己、過去、未来の概念の発達を可能にします。世界の結び目を解く、または少なくともより絡まりの少ない形で結び直すには、これらの大きな問題についての考察で終わるのが適切であると考えています。高次の意識は、意識のプロセスの特性を科学的に探究するために明らかに必要です。人間が意識を持つ以上、高次の意識を完全に排除することはできず、第一次意識という継続的な情動によってのみ人間が突き動かされ行動するものだと考えることはまことに奇妙な話です。
言語、自己、思考、情報の起源、認識の起源と範囲など、高次の意識に関連するいくつかの主題を簡単に探究することに私たちの焦点を当てましょう。意識のプロセスを理解し、それを自分自身と他の人に報告しようとする科学的観察者に何を期待できるかを問う時が来ました。
言語と自己
人間にとって中心的な意味を持ついくつかの問題を新たな視点から考察します。高次意識の出現の背景には、言語につながる神経の変化があると考えられるため、言語の進化の側面について考察します。高次意識が出現し始めると、自己は社会的および感情的な関係から構築されます。自己意識を持つ主体としての自己は、一次的意識を持つ動物の生物学的な個性をはるかに超えるものになります。自己の出現は現象学的経験を洗練させ、感情と思考、文化、信念を結びつけます。それは想像力を解放し、わたしたちを比喩の広大な領域へと思考を開きます。意識を保ちながら、記憶された現在という時間的束縛から、わたしたちを一時的に逃れることさえできるのです。三つの謎、「現在進行形の意識の謎」、「自分の意識の謎」、「物語、計画、空想の構築の謎」は、一次意識と高次意識を合わせて考えることで、すべてを明らかにすることはできないまでも、ある程度解明することができます。
高次の意識につながる脳の構造の変化について考えてみましょう。一次的意識しか持たない動物でも、「心的イメージ」、つまりダイナミック・コアの再帰的統合活動に基づく情景を生成することができます。この情景は、環境における実際の出来事の連続によって大きく決定され、ある程度は、無意識の皮質下活動によっても決定されます。このような動物は生物学的な個性を持っていますが、自分自身を自覚する真の自己は持っていないのです。ダイナミック・コアのリアルタイムの活動によって維持される「記憶された現在」はあっても、過去や未来についての概念はありません。
これらの概念は、ヒト科動物の進化の中で、象徴的な手段によって感情を表現し、物や出来事を参照する能力、すなわち意味論的能力が出現して初めて生まれました。必然的に、高次の意識には社会的相互作用が伴います。構文と意味のシステムは、象徴的な構築のための新たな手段となり、高次の意識を媒介する新たなタイプの記憶を提供しました。意識を意識することが可能になったのです。
ヒト科動物の進化と言語の出現において、一次意識の場合と同様に、新たな再帰ループが出現しました。意味論的能力、ひいては言語を介した新しい種類の記憶の獲得は、概念の爆発的拡大につながりました。その結果、自己、過去、未来の概念が一次意識に結びつき、自覚的な意識が可能になりました。
そのような時点で、個人はある程度、記憶された現在への束縛から解放されます。一次意識が個人を現実の時間と結びつけるとすれば、高次意識は少なくとも一時的な切り離しを可能にします。意図性、分類、識別といった全く新しい世界を経験し、記憶することができようになりました。その結果、概念と思考が促進されます。情景は象徴によって豊かになります。価値は意味と意図性につながります。個人の学習を価値システムそのものの変更に結びつける神経システムを進化させることによって、それ自体をより豊かな適応的方法で変更することができます。言語とともに高次の意識が芽生えると、社会的・感情的な関係から自己が構築されるようになります。
一次意識だけを持つ動物は、象徴的能力を持たないので、自己や過去、未来という概念を発達させる可能性はありません。しかし、言語能力を持つ赤ちゃんには、早い時期から、外部からの合図が母親との感情的なやりとりによって影響を受け、動きや概念的な意味を帯び始めます。音韻論的および意味論的発達のための基盤は早い段階で整い、母親とのやりとりの意味も理解できるようになります。
思考
ここでは、「思考が浮かんだとき、あなたの頭の中では何が起こっているのか?」という問いを投げかけます。ウィリアム・ジェームズ(William James)(1842~1910)は、おそらくこの試みを真剣に試みた最初の人物でしょう。意識の神経基盤に関する現在の理解を踏まえてこのエクササイズを繰り返すと、思考が生まれるたびに脳内では非常に多くのことが起こっており、そのほとんどは並行して起こっており、驚くほど複雑で豊かな連想に基づいているという結論が裏付けられます。そのかなりの部分は、現在のコンピュータの能力をはるかに超える複雑さを持つ情報です。
哲学的思考は単独では不十分であり、脳の機能に関する分析によって補完されなければなりません。自然の中で情報や意識がどのように生まれたかを考えると、認識論は生物学、特に神経科学をその根拠とすべきだと、私たちは考えます。この見解から、三つの重要な哲学的帰結が導き出されます。すなわち、「存在は記述よりも先にある」、「選択は論理よりも先にある」、「思考の発達において、理解よりも行動が先にある」ということです。
人間には一次意識があり、それは高次意識を発達させるために不可欠なものであるという意味で一次的です。そのため、私たちはこれほどまでに一次意識に注目してきたのです。しかし、中心となるのは高次意識です。
私たちの立場は、意識していることに意識的である能力を含む高次の意識は、意味能力、ひいては言語の出現に依存するというものです。これらの特質と同時に、社会的相互作用から生まれる真の自己、そして過去と未来という概念も生まれます。一次的な意識と記憶された現在によって、私たちは象徴的なやりとりや高次の意識を通じて、物語やフィクション、歴史を作り出すことができます。私たちは、どのようにして知ることが可能なのかという問いを投げかけ、それによって哲学の入り口に自分自身を導くことができます。
意識を物理的プロセスとして捉える
意識は脳内の物質的秩序の特定の配置から生じるものであると主張してきました。 何かを物質的と呼ぶことは、崇高なもの、すなわち心、精神、純粋な思考の領域へのそのものの参入を拒否することである、という偏見が一般的です。 物質という言葉は、多くの物や状態を指すために使用されます。それは私たちが一般的に現実世界と呼ぶ、感覚的または測定可能なものの世界、科学者が研究する世界に当てはまります。その世界は、一見した印象よりもはるかに繊細です。星も物質であり、原子や素粒子も物質です。それらは物質とエネルギーからできています。
心は、自分自身や他の心の中で起こる物理的プロセス、コミュニケーションに関わる出来事などに完全に依存し、それらに根ざしています。物質と心の領域が完全に別々であるということはなく、二元論の根拠もありません。しかし、明らかに、脳、身体、社会世界の物理的秩序によって生み出される領域があり、そこでは意味が意識的に作り出されます。その意味は、私たちが世界を記述し、科学的に理解する上で不可欠です。神経系と身体の驚くほど複雑な物質的構造が、ダイナミックな精神プロセスと意味を生み出しています。
私の意見
「デカルト自身が心身二元論という言葉を命名したのですか」と、Microsoft Copilotに聞くと、その答えは、「デカルト自身が「心身二元論」という用語を使ったわけではありませんが、彼の哲学がこの概念の基礎を築きました。デカルトは、精神(心)と物質(身体)を独立した実体として捉え、これを「思惟実体(res cogitans)」と「延長実体(res extensa)」と呼びました。」という、答えが返ってきました。今回、私はデカルトの著作物やデカルトの解説書を何冊か読みました。「心身二元論という言葉」は、やはりデカルト自身が作った言葉ではなく、当時の、または後の時代の哲学者がデカルトを評してその名称を考案したのだと思います。私の意見としては、デカルトの哲学は心と体の二元論ではなく、「肉の心」と「肉の心から生まれた心」による意識の二元論ではないかと思いました。別の言い方をすると、「創発的二元論」とも呼ばれています。
ジェラルド・エデルマンとジュリオ・トノーニの書いた、『意識の宇宙』では、一次意識が「肉の心」に相当し、高次の意識が「肉の心から生まれた心」相当します。肉の心は、原始的な存在です。肉の心は、自身の存在を擁護、維持させるような心です。肉の心から生まれた心は創発作用によって生じますが、その心は、さらに長く、その個体を現実世界に社会的に適合するように維持するための方策を表現しています。本章の最初に掲げた表がそれを表しています。
物理世界において、ある個体が、自ら何かしようとすれば、物質によって作られた機能的な構造が必要です。構造がないと自ら動いたり、何かの機能をしたりすることができません。ただ物質を並べるだけでは、その物質が自ら動くことはありません。ものではなく、理論においても同様で、構造が必要であると思います。
私は、脳の創発現象によって、霊のようなものが人間に宿るのではなく、人間の脳が霊のようなものを想像することができるようになると思います。これは、まだ仮説にすぎませんが、創発作用によって生ずる高次元の存在は、超ひも理論に由来するのかもしれません。物質には、そういった世界を人間に想像させる機能、もしくはそのような世界にアクセスできる機能が暗黙的に備わっているのかも知れません。ただしこれは素粒子レベル以下のサイズでの話です。こういった高次元の世界にアクセスするためには、人間の脳のような複雑性が必要です。創発作用による高次元へのアクセスは、脳の正常な機能がそうさせるのであって、まぼろしや幻覚を作り出しているのではないと思います。
しかし聖なる世界というのは、脳の存在する俗なる世界が併設されてこそ、意味や価値を考えることができると思います。聖なる世界は、俗なる世界のゴールです。現実世界から見ると、俗の世界があってこそ、聖の世界が存在するのです。俗の世界がなくなれば聖の世界の意味も価値もわからなくなってしまいます。つまり我々の生きている俗世界が永遠に続いてこそ、聖の世界の役割があるのです。聖の世界の役割は、人間に俗の世界を続けさせることです。俗の世界の消滅とともに聖の世界も消え去るでしょう。人は誰も聖なる世界のみが存在する世界について、顧みることはないと思います。人間の存在する俗なる世界が無くなってしまうと、聖なる世界だけというのは人間にとって何の意味も価値もないものです。つまり、地上世界の終わりが来てこの世が荒廃して人間が居なくなってしまうと、聖なる世界があったとしても人間にとってはもはや無関係な存在です。
終わり