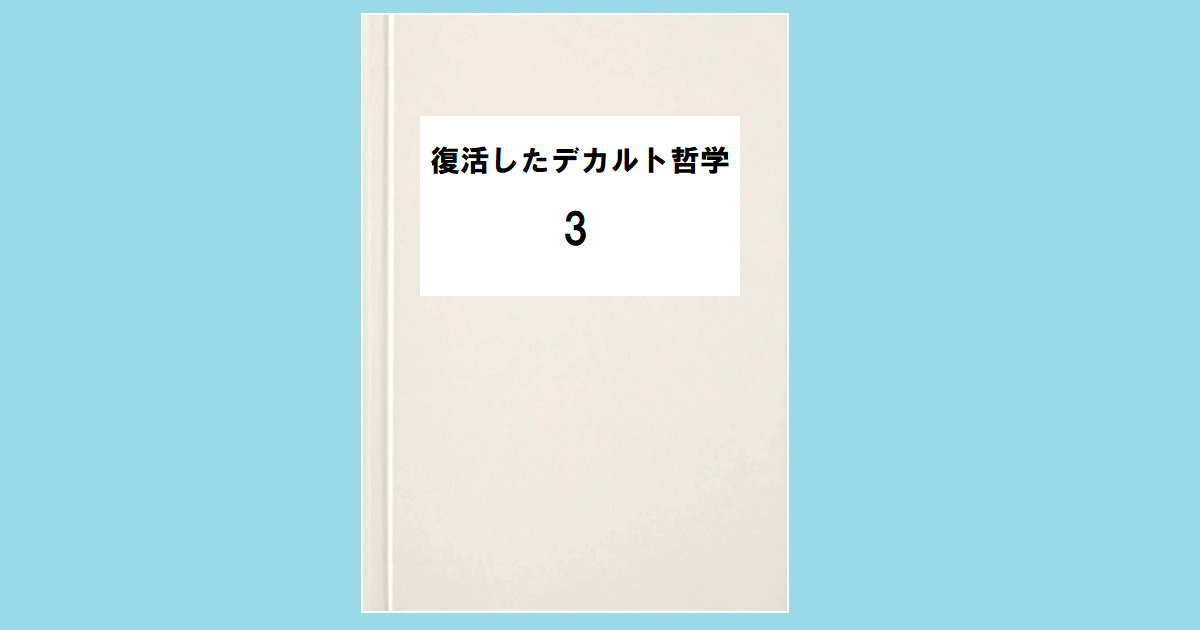(デカルトの哲学を現在の視点で再考して得た真理 3)
第二部
懐疑主義の解決策として多様性と唯一性は生まれた
第二部で引用させていただいた文献
・懐疑 近世哲学の源流 (紀伊國屋書店)
リチャード・H.ポプキン
野田又夫、岩坪紹夫(翻訳)
・デカルト 清水書院(出版社)
伊藤 勝彦
懐疑主義について
この研究対象は、伝承的な宗教信仰に向けられる一連の疑念ではなく、古代ギリシア思想の中にその起源をもつ哲学的見解としての懐疑主義です。ギリシアの初期思想家たちの多彩な懐疑的考察と懐疑的態度とは、ヘレニズム時代に入ると、大きく二つに分かれました。一つは、アカデメイア派懐疑主義の見解で、いかなる認識も可能でないということです。もう一つは、ピュロン派懐疑主義の見解で、何かの認識が可能かどうかを決定するには不適当な証拠しかないので、認識についての一切の問題には判断を差し控えねばならない、との見解を立証する一組の議論に発展しました。
アカデメイア派懐疑主義は、プラトン派のアカデメイア(学園)で紀元前3世紀に定式化されたからそう呼ばれるのです。「私が知っていることは、私は何も知らないということである」というソクラテス(Socrates)(紀元前470頃 – 紀元前399)的考察から発展しました。彼らは、なによりもストア派哲学者の認識可能の主張に反対して、何ものも認識されえないことを示す一連の議論を造りあげました。疑うことは議論を進める知恵の一つであると思います。
定言主義の哲学者というのは、事物の実在的本性について何かの真理を認議していると定言する哲学者のことです。アカデメイア派の懐疑主義哲学者の目的は、定言主義の哲学者が認識しているという命題を、絶対的確実性をもっては認識しえていないことを、一群の議論と問答法によって示すことでした。我々の感覚によって得た情報は当てにならないであろうし、また我々の推論が信頻できるとは確信しえないし、また我々の判断のどれが真でどれが偽かを決定するための、保証つきの標識や基準を我々が持たないことを示す一連の難点を、アカデメイア派は定式化しました。
ビュロン派運動の始まりは、伝説的人物で古代ギリシア・エリス出身の哲学者ピュロン(Pyrrho)(紀元前360~紀元前275頃)と弟子・プリウスのティモン(Timon of Phlius)(紀元前315~紀元前225頃)です。ピュロンについて伝えられる話は、彼が理論家ではなく、徹底的に懐疑する人間の生きた見本であり、そのときどきに現われるものを越えるいかなる判断にも決して係わらなかった人間であったことを教えています。彼の関心は主として倫理・道徳的なものであったようです。この領域において彼は、価値理諭の受容とそれによる判断とから当然生じる不幸を避けようとしたのでした。もしこのような価値理論がたとえ僅かであれ疑わしければ、それを受容し使用することは精神的苦痛を起こすだけです。ピュロン主義は、理論的に定式化された懐疑主義としてはアエネシデモス(Aenesidemus)(紀元前100~紀元前40頃)によって創設されました。定言主義者が「何かは認識されうる」と言い、アカデメイア派が「何ものも認識されえない」と言うとき、「両者はともに定言しすぎている」とピュロン主義者は考えました。
紀元2世紀ごろ、ほぼセクストス・エンペイリコス(Sextus Empiricus)(2世紀から3世紀ころ)の時代まで、ピュロン派運動は主としてアレクサンドリア周辺の医学者団において、他の医学者団の肯定的または否定的な定言主義に対する解毒剤として隆盛をきわめたようです。
その立場は、主としてセクストス・エンペイリコスの著者『ピュロン主義哲学の概要』と、論理学と数学から天文学と文法学に至る、あらゆる種の法則を懐疑主義により踏みにじり壊滅させる大著『学者たちへの論駁』において、いまに伝えられています。
この二つの懐疑主義の立場は、ヘレニズム時代以後は殆ど目立った影響を与えませんでした。ピュロン派の見解は16世紀の再発見まで西洋では殆ど知られなかったようです。アカデメイア派の見解は主として聖アウレリウス・アウグスティヌス(Aurelius Augustinus)(354~430)の論述によって知られ考察されました。これから取り扱う時代の前にも、懐疑主義的発想の兆は、ユダヤ教徒であれ、イスラム教徒であれ、キリスト教徒であれ、主として反理性的な神学者たちの間で行われたようです。この神学運動は西洋では15世紀にニコラウス・クザーヌス(Nicolaus Cusanus)(1401~1464)の著書において絶頂に達し、多くの懐疑主義的議論が宗教的認識と宗教的真理とへの理性的アプローチの確信を覆すために使用されました。
これから論じる時代、西暦1500年~1650年だけが、古代懐疑主義が近代思想に衝撃を与えた唯一の時代なのではありません。それ以前にも以後にも古代懐疑主義思想家たちの大きな影響が見られます。
宗教改革からデカルト哲学の定式化に至るまでの時代には、懐疑主義は特異な役割を果たしていると思われます。この特異な役割は、宗教改革が引き起こした知的危機が古代ギリシア懐疑主義者の議論の再発見と復興との時期に一致したという事実に基づきます。16世紀に、セクストスの著作の写本の発見とともに、古代懐疑主義とその見解を当時の問題へ適用することへの関心と興味が当時の時代へ復興させました。
古代懐疑主義の見解を16~17世紀の思想家たちに注目させるのに果たした別の役割を軽視するつもりはありません。しかしながらセクストスの著作は、ここで考察する多くの哲学者や神学者や科学者に対して特殊で強力な役割を果たしたと思われます。またセクストスが、彼らの多くの議論や概念や理論の直接、間接の典拠であったと思われるのです。ピュロン派懐疑主義者たちの立場の完全な紹介と、彼らがあれほど多くの哲学的理諭に反対するのに用いた問答(弁証)法の武器のすべてが見出されるのはセクストスの書だけです。
それゆえに、モンテーニュやメルセンヌやガッサンディのような思想家は、当時の係争問題を処理するために用いる材料をセクストスに求めました。また、この危機は「アカデメイア派的危機」よりも「ピュロン主義的危機」としての方が、適切に表現されていると思います。
17世紀末に、偉大な懐疑主義者ピエール・ベール(Pierre Bayle)(1647~1706)はセクストスの議論の再導入が近代哲学の発端であると考えました。この時代の多くの著述家は「懐疑主義者」という術語を「ピュロン主義者」と同じものとして用いているし、またアカデメイア派の懐疑主義者は本当は懐疑主義者ではなく否定的な定言主義者であるというセクストスの見解にしばしば従っています。
ここで考察する懐疑主義の歴史はデカルトの死までです。このように限定する理由は、懐疑主義がこの時期までは一つの役割を主として果たし、それ以後は別の役割を果たした、と私には思えるからです。
懐疑主義の正反対は「定言主義」ですが、一つの非経験的命題が、どのようにしても偽でありえないことを立証する証拠が提示されうるという見解です。ここで考察する懐疑主義者と同様に私も、定言主義の主張には疑いを投げかけるし、またこの主張は究極的には、証拠よりも何か信仰的な要素に基づいていると考えられます。もしそうなら、どんな定言主義による見解でも多かれ少なかれ信仰主義的になります。もしもこのことが論証されたなら、そのとき懐疑主義者は何かを確信しているのであり、定言主義者になるのでしょう。
多様性の源流は、ハーバート・オブ・チャーベリの著書『真理について』である
ハーバート・オブ・チャーベリ(Edward Herbert, 1st Baron Herbert of Cherbury)(1583~1648)もジャン・ド・シロン(Jean de Silhon)(1596~1667)も、「新しいピュロン主義」が人間の認熾の基礎を覆したその深さを十分には認識してはいませんでした。しかし、この問題を新しい方法で取り扱わねばならないことを、二人とも知っていました。前者は、真理を発見する精巧な方法を提議したし、後者は、疑われえない若干の基礎的真理を提示しようとした。しかし、懐疑主義への反対者の中で最も偉大なルネ・デカルトは、この二人がそれぞれに基本的係争点を理解していないために、致命的な失敗を犯していることに気づいていました。シロンは、著書『二つの真理』や『魂の不死について』を著しました。
ハーバートは1618年から1624年まで駐仏大使であり、その地で懐疑主義思想の潮流と、それを妨げるための企てに触れました。彼の書をフランス訳したと思われるメルセンヌと、また彼の書のコピーを贈ったことでガッサンディと知り合いになったのもこのときです。
この大作に幾年も費やしたあとで、(これはパリ大使になる前の1617年に始められた)、この書が世に受けいれられるかどうかについて満身の恐れと、おののきに襲われましたが、ハーバートは高きからのお告げと思ったものを受けいれ、ついに1624年、『真理について』を公刊しました。
この書は、当時の学問の惨めな状態、信条の混乱、多種多様な諭争の描写で始まります。世の中には、何でも認識できるという人々がいるし、何も認識できないという人々もいます。ハーバートは、自分はこれら学派のどちらにも属していないと主張しました。
もっと正確にいえば、何かは認識されうると考えていたのです。我々がもつ認識を認知し評価するために必要なものは、真理の定義と真理の標識と真理発見の方法です。これらすべてを発見したとき、我々は懐疑主義には留まれなくなります、なぜなら、我々の能力によって客体を認識することができるようになる一定の条件があることが理解されるからです。
『真理について』の第一命題は、「真理は存在する」と露骨に公表しました。ハーバートは、「この命題の唯一の目的は、痴愚者と懐疑主義者とに対して真理の存在を定言することである」というのです。ハーバートは、「新しいピュロン派」の思想への反対の態度を示すために、真理とは何であり、いかにして真理に到達できるかを示すことに着手しました。真理には四つの型があるといいます。
(1)事物が、それ自身において本当にそのままの事物の真理、(2)事物が我々に現われるように示す仮象の真理、(3)我々が事物について形成する概念の真理、(4)我々の主観的真理である仮象や概念によって判断する共通慨念、すなわち知性的真理です。これらは、真の知覚を獲得する手段についてのアリストテレスの分析に主として従っています。この宝物である共通概念とは何でしょうか。それは、知性の真理とは、すべての正常な人間の中にある一定の共通慨念で、これらの概念は万物の構成要素であり、普遍的知恵に由来し、自然そのものの指令により魂に押印されるものです。
(1)の真理は絶対的です。それは「あるがままの事物」であり、これこそ我々が、他の三項の条件的真理を用いて認識しようと探究しているものです。これら他の三つの項の真理は対象の事物自身よりも、むしろ認識者に関係しています。我々の課題は、真理がいかに現われるかということを、我々がもつ情報から出発して、我々の主観的情報が対象となるそれ自体の真理と一致していることを決定する基準または標識を発見することです。
ここで、真理の判定がどのように行われるか手順を示します。われわれが仮象から認識するものは、実在的客体が何であるかの手引きとしては、我々を欺いたり、誤り導いたりすることがありえます。しかし、仮象は、仮象として常に真正あり、それが現われるように現われます。ただし、必ずしも、事物それ自体の真理であるものの表示ではない可能性があります。我々がもつ経験に基づいて形成される概念は全く我々自身のものであり、これらの概念がそれについての概念であるとされている事物と一致するかもしれないし、しないかもしれません。もしも感覚器官が不完全なら、もしも劣等なものなら、もしも精神が欺瞞的な偏見に満ちておれば、概念はすっかり損なわれているでしょう。そこで、最後の真理、知性の真理が、その生得の能力やその共通概念によって、我々の主観的諸能力がそれらの認識作用を十分に行使したかどうかを決定します。この基準または標識によって、仮象および概念の個人的な主観的真理と事物の真理との間に一致があるかどうかということなのです。したがって、我々が客観的認識をもっているかどうかを、われわれは判断できるのです。
そこでハーバートは、それぞれの項の主観的または条件的真理へ達するための方法と、主観的真理が事物の真理に一致しているかどうかを評定するための共通概念または標織を知るための方法と、最後に、この機構すべてを真理の探究に応用するための方法を、このような厄介な仕方で、一歩一歩精述しました。それぞれの段階に懐疑主義者が提起した難問があるから、それぞれの項の真理を確認するための条件について注意深く述べねばなりません。
こうして、ハーバートは「私の見解では、普遍的同意が神学と哲学との始めであり終りであると考えられねばならない」と宜言しました。神は摂理によってこれらの真理すべてを我々に与えました。それゆえに、それらは実在世界の認識を得るために我々が所有する唯一の基底であるとともに、信頼に値するものなのです。
懐疑主義に対するためのハーバートの提案は、解毒剤として当時は確かに広く承認されましたが、ガッサンディとデカルトから手ひどい批判を受けました。ガッサンディは、ハーバートの提案は、懐疑主義者を征服し損なった擁護の余地ない定言主義であると攻撃しました。またデカルトは、ハーバートの提案は基礎的な係争点を把握していないので、ピュロン主義を諭破し損なった不完全な定言主義であると攻撃しました。
ガッサンディの批判
ガッサンディの反論については資料が二つ残されています。一つは、ハーバートヘ送られなかった丁寧な手紙で、幾つかの基本的問題を提起したものです。もう一つは、共通の友ディオダティ(Diodati)に書かれた手紙で、荒々しい非難を含んでいました。後者は、懐疑主義の挑戦に応えるハーバートの新哲学体系についてのガッサンディの本当の意見でした。それはハーバートの図式は、何処にも到達しない混乱した迷路であるという意見を示していました。
ハーバートが発見したと主張する真理は認識されていないし認識不可能である、とガッサンディは宜言しました。真理がいったい何であるかを知らなくても、ハーバートが真理を見出せなかったこと、また懐疑主義者に応えなかったことは解ります。ハーバートの図式に替えるべき別の定言主義を持たないとしても、ハーバートの図式には何か間違いがあることが理解できます。彼の新体系は一種の問答法にすぎません。しかし、そのような長所は持っていると思います。
この注解をしてから、ガッサンディは、ハーバートの全努力を水泡にしようとして、彼が思った懐疑主義の難点を簡単に定式化した。ハーバートの図式に従えば、真理の標識または基準は自然的本能と我々の共通概念です。それによって我々一人ひとりが事物の真の本性を判断できるとしています。もしもこれが真実なら、殆どすべての問題について生じる判断のひどい不一致をどのように説明できるのでしょうか。
どの人も皆、自分自身の自然的本能と内的能力を確信しています。もし各人がこの不一致を説明するハーバートの手段を用いれば、各人が他の人は「健全で完全ではない」と宜言するでしょう。そして各人が自身の知性の真理に基づいてそれを信じ、そして彼らは袋小路に入り込んでしまうでしょう。なぜなら各人は自分が正しいと当然考えるであろうし、同じ内的基準に訴えるからです。彼らは誰の見解が真であるかを決定する標識を持ちません。そもそも、誰がその判定者になれるのでしょうか、また誰が自分は立場を決定しない権利をもつと証明できるのでしょうか。 実際上あらゆる事に不一致があるかぎり、宗教改革のときに提起されたのと同じ懐疑主義の難問題が、ハーバートの哲学をも同じく悩ませることでしょう。各個人は、自分自身の内にある基準に従って、主観的に事物の真理を見出すことができるでしょう。しかし、さまざまな人々の意見が一致せず、しかもそれぞれ主観的に確信しているとき、誰が真理を判断できるのでしょうか。白痴や幼児を除けば、一定の基礎的な事については普遍的一致があるとハーバートは主張しました。しかしそのとき、もし相争う党派がそれぞれ健全さ、精神的健康、精神的成熟さを所有すると主張すれば、誰がまたは何がこれらの性質の判者となりうるのでしょうか。それゆえハーバートの図式は実在的本性の真理を決定する能力を持ちません。なぜならそれは自然的本能とか内的確信のような、変りやすく弱い基準に基づいているからです、とガッサンディは結論しました。
デカルトの批判
『真理について』の別種の、おそらくもっと痛烈な批判はデカルトが下しました。彼はガッサンディと異なり、懐疑主義を論破するというこの書の目的に深く共感したので、それだけに、この書の基礎的誤謬に一層強く気づきました。1639年にメルセンヌはデカルトにハーバートの書のコピーを送り、そしてこの書について詳細に論じた論文を受けとりました。「この書は、私が生涯をかけて、論究してきた主題を取り扱っていますが、それは私が辿ったのとは非常に異なる道をとっている」と、デカルトは意見を述べました。デカルトの仕事とハーバートの仕事との基本的相違点は、前者は、「真理」は知らないでいることが不可能なほどに、すぐれて明晰な概念である。したがって自分は真理に対していかなる懐疑も異議も断じてもたない、と主張しました。後者は「真理とは何か」ということを発見しようと試みたということです。
デカルトが見抜いたように、ハーバートの研究方法の基本的な問題点は、もしも真理とは何かということがあらかじめ認識されていないのなら、真理を学ぶ道は全くないということになります。彼の結論が『真理について』の図式が、真理を測定または発見するための方法であることを認めるためには、真理とは何かを、あらかじめ認識している必要があります。真理の概念は、形、大きさ、運動、位置、時間のような他の幾つかの基礎的観念と同様に、直観的に認識されるものです。それらを定義しようとすると、反対に曖味になってしまいます。
ハーバートは真理を知るための多くの測定装置を持ちましたが、それが測定するものを知ることができませんでした。デカルトは一つの真理の直観的認識から出発し、彼の真理測定規準を構成しました。デカルトは、その「真理」を検定するための一つの認識方法、コギトを見つけました。ハーバートは一つの「真理」を持ったのかも知れませんが、それが本当の真理であるかどうかを知ることができませんでした。
ハーバートの新哲学は、多様性という真理についての提案でした
ガッサンディは、この新図式では事物の真理を発見できないし、また事実上いかなることにも普遍的に一致することはないのだから、新図式は実際上一種の懐疑主義になると見ました。デカルトは、ハーバートは間違った場所から出発し、真理を見つけるための十分な標識を提案できなかったと見ました。懐疑主義を克服するには、何が真理であるかを認識しなければなりません。また真理探索への関係が確定されない無数の手続きで真理を探求してはいけません。そして、真と偽または疑わしいものとを混同することない真理を認識するための標識を持たねばなりません。ハーバートはピュロン主義的危機に対応するための十分な解答を与えることができませんでした。
私の意見
現代に生きる私たちからみると、懐疑主義は多様性を勧めるような考え方を秘めていると思います。真理について議論をする場合、最初に定言主義があって、次に対立的思想を内包した懐疑主義が出現します。懐疑とは一つに決まらないということを表しています。議論が広がってよいと思いますが、なかなか結論が発散して収束せず、困ることもあります。そこで、懐疑主義的危機を回避するために、いろいろな考え方が考案されましたが、これといった決め手は登場しませんでした。「ピュロン主義的危機」とは、神によって人間に求められていたことが、なかなか実現しなかったということです。誰かが何らかの返事を神に対して、結果を表明しなくてはなりませんでした。そこで、ハーバートの提案が登場しました。彼の新哲学は、現代でいう「多様性」の原型のような気がします。当時はガッサンディやデカルトに否定されたようですが、科学革命の時代に懐疑主義は死に、そして復活することで、多様性という門を開いたともいえるのではないでしょうか。現代では、そういった問題を解決する方法の一つとして、多様性という考え方があります。ハーバートは多様性という真理の一つを発見した、新たな哲学的な源流を発見したのだと思います。
懐疑主義の王者はデカルトである
ブルダン神父(Pierre Burdin)(1595~1653)との書簡の中でデカルトは、自分が懐疑主義者の懐疑を打ち倒した最初の人間であると言明しました。それから100年以上も後の彼の崇拝者の一人は、「デカルト以前にも懐疑的な者たちはいましたが、彼らは普通の懐疑的に過ぎませんでした。しかしデカルトは、懐疑主義から哲学的確実性を生じさせる方法を習得した」といいました。当時は、デカルトの知的改革運動を懐疑主義的危機の側から注目することは、殆ど行なわれませんでした。デカルトは当時の懐疑主義への深い関心を表明しました。また古代および当時のピュロン派の著作に十二分に精通していることも示しました。また彼は自分の哲学を、1628年から1629年の深刻な「ピュロン主義的危機」との対決を通じて展開させました。そしてデカルトは自分の哲学の体系は懐疑主義者の攻撃によく耐えうる、唯一の知的要塞であると宜言しました。
彼はピュロン主義の古典のみならず、当時の懐疑主義的潮流や、学問、宗教にとって増大する一方の、その危険性についても十分に知っていたらしいのです。彼はブルダン神父との書簡の中に、「古代の懐疑主義者の学派はずっと以前に消滅した、と考えては断じてなりません。それは常に変わらず今も栄えています。そして、自分は他の人間たちがもつ能力を越える、何かの能力をもっていると思うほとんどの人々は、普通の哲学の中には満足できるものを何も見出せないし、またその他いかなる真理も見出せないので、懐疑主義に避難するのである」と書きました。
デカルトは懐疑主義の文献の幾つかに精通していただけではなく、時事問題としてのピュロン主義的危機にも深い認識を持っていました。上述のように、彼はハーバートの著作を吟味しています。また、『方法序説』の自伝的部分と彼の書簡には、デカルトは1628年か1629年ごろに懐疑主義の全勢力を傾けた攻撃を受けて、それへの新しい強力な対応策の必要性を痛感したことを示す証拠が書簡に見出されます。懐疑主義の脅威へのこの覚醒によって、デカルトはパリにいるときに、懐疑主義者たちのどのような法外な想定によっても揺り動かしえぬほど堅固で確実な何かを発見しようとして、彼の哲学革命を始動させたのです。
デカルトはパリを去りました。ピュロン主義的危機への解答を出すために、新しい真理を求めて、オランダの隠れ家で省察しました。人間的認識の不動の基礎を発見するために科学と数学から神学的形而上学へ興味の対象が転じたのです。 宗教改革と科学革命と懐疑主義の猛攻撃が、今まで支持してきた人間の知的業績に関するすべての古い基礎を崩壊させました。新時代は、それらが発見したものを正当化し保証する新基底を要求しました。デカルトは最も偉大な中世的精神の伝統に立ち、全能の神という基礎に、人間の自然的認識という上部構造を結びつけることによってこの基底を与えようとしました。ここに神に選ばれたデカルトの使命感が現れています。
炉部屋における神秘的体験
デカルトの伝記作者、バイエ(A. Baillet)(1649~1706)の伝えるところによれば、今は失われたデカルトの手記の中に、「1619年11月10日、霊感に満たされて、私は驚くべき学問の基礎を発見しつつあった……」とあります。これが「炉部屋の思索の一日」を記念する一句であったことは疑えません。この夜、デカルトは三つの夢をみました。デカルトはこれらの夢で、真理の霊が神によって送られてきたと感じ、哲学全体を彼一人の力で新たにする仕事を神から天職としてあたえられたと信じました。彼はこれを自分の生涯におけるもっとも重要な事件と考え、神によって自分の将来における仕事が祝福されたという感激の思いから、やがてイタリアへ行く計画をしていた旅行の途中で、ロレットの聖母寺院に巡礼しようという誓いを立てたというのである。これらは、バイエ(A. Baillet)の『デカルトの生涯』(1691)に記されていることですが、彼の証言を信ずる限り、これはそれ以後のデカルトの思想的生涯を決定づけるような事件であったと考えられます。
「われ」の自覚
『方法序説』(A DISCOURSE OF A METHOD)の第二部の初めのところには、ウルムの炉部屋で思索したことが冷静な調子で報告されています。夢のことなどには一言も触れられていません。そこで述べられていることは、第一に、「たくさんの部分によって構成され、さまざまの工匠の手によって作られた作品においては、ただ一人が仕上げた作品におけるほどの完全性はない」ということでした。ただ一人の建築家が設計し、完成した建物は、他の目的で建てられていた古壁を利用して多くの人の手で修理されたものよりも、はるかに美しく、秩序だっているのが普通です。はじめは小部落にすぎなかったものが、時が経つにつれて大きな町となったところの古い都市は、ただ一人の技師が、平野の中で思いのまま設計し、建築した規則正しい町にくらべると大抵は釣合がとれていません。さらに、一国の法律にしても同様で、ただ一人の立法者、たとえば、昔のスパルタのリュクルゴス(Lycurgus)(紀元前11世紀から紀元前8世紀の間頃)のような人が一人で方針を定めて立法すると、一つの目的に貫かれた整然としたものができます。学問も同様であって、その根拠が不明で、何らの論証を持たない学問であり、つまりスコラ的な学問は多くの異なった人々によって少しずつ組みたてられ、拡げられてきたものであるから、良識ある一人の人が目の前に現われる事がらに関して、生まれつきの持前で成しうる単純な推理ほどには、真理に近いことはありえません。言い換えると、ただ一人の人間が、正しい方法に従って導き出した認識の体系のみが、本当の学問といえるのだと主張しているのです。
哲学者へのめざめ
ウルム(Ulm)近郊の一小村の炉部屋を出たとき、デカルトは一人の哲学者になりました。それ以前は、彼は自然哲学者でした。個々の応用技術的な研究に関心をよせる自然探究者にすぎませんでした。
さて、デカルトは、イザーク・ベークマン(Isaac Beeckman)(1588~1677)との出会いによって理論的な研究へと目覚めさせられてからは、しだいに物理学を数学的に取り扱う研究に専念し始めました。さらに注目すべきことは、1619年3月4日にベークマンにあてた手紙の中で方法の問題に言及し、これらの方法の一般化の理念を述べています。このように数学を普遍化すると、全く新しい学問が生まれるはずであり、それによれば、人はいかなる種類の連続量においても非連続量においても、提出されたすべての問題を解くことができるはずであるとのことでした。
デカルトはここで、単なる数学以上のものをねらっています。彼は新しい方法の理念へと歩みよっているのです。それは単に代数的解法を幾何学に適用することだけに留まりません。デカルトの著作、『精神指導の諸規則(Rules for the Direction of the Mind)』には、「数学(mathesis)という名称は、もともとは、ただ学問というのと同じ意味にすぎないから、その点ではすべての学問が、幾何学自身と同じ権利をもって数学と呼ばれることになるであろう」とあります。つまり、天文学、音楽、光学、力学、その他多くのものが数学によって記述できると考えました。デカルトは一歩、一歩、普遍数学(Mathesis Universalis)の構想に近づいて行きます。もっとも、そのような普遍的学問は、ただ一人の人によって完成されることはありません。やはり同じ手紙(ベークマンあての3月26日付の手紙)の中で、「これは無限の仕事であって、到底一人の人の成しうるところではありません。それはまた信じることができないほどの、野心に満ちた仕事なのです。」と記述されています。
ここでは、まだ彼は自然科学者として語っています。自然科学という学問の性質からいって、それはただ一人の人が一挙に完成できるはずのものではないのです。その時代から次の時代へと、前代の成果が引き継がれ、受け継がれてゆき、ほとんど無限に多くの人々の協力によって研究が継続されることによってのみ、自然の謎は解明されてゆきます。ところが、あの1619年11月10日の神からの啓示の日から、デカルトは自然科学の共同性の道から決然と離れて行きました。そして自分ただ一人の力で、学問を全く新しい基礎の上に打ち立てようと決意します。この突然の変貌はどうして起こったのでしょうか。デカルトは、なぜ科学者の道を見捨てて哲学者となったのでしょうか。これは誠に興味ある課題です。
闇の中を一人ゆく
1619年11月10日、それは運命の日でした。ウルム(Ulm)近郊の一小村の炉部屋の中での深い思索をしていました。そこを出たとき、彼は哲学者でした。いや、正確にいえば、哲学者への道を歩み始めていました。「ただ一人、闇の中を歩むように進んで行こう。すべてのことがらに細心の注意を払おうと、決心した。……」(『方法序説(Discourse on the Method)』第二部)しかし、それは一歩、一歩踏みしめてゆく、間違いのない足どりでした。細心に、慎重に、闇の中を歩きながら、少しずつ、その闇を押しのけ、はるか彼方から光を現れ出させようとします。彼は何を探し求めているのでしょうか。それは世界(宇宙)の謎です。混沌とした世界の輪郭が次第にはっきりとしてきます。定かな形も持たない雑多なるものの内に、はっきりとした形が、秩序が見えてきます。彼はその秩序を探しもとめているのです。世界の秩序を、その整然とした仕組みを探しもとめているのです。世界の合理的に秩序づけられた姿を、方法に従って、少しずつ明るみに出してこようとしているのです。それは、一言でいえば、「カオスからコスモスへ」の道です。炉部屋の思索から諸国遍歴を経て「コギト・エルゴ・スム(Cogito, ergo sum)」に至るのです。
普遍的な知恵
哲学者デカルトが探し求めているのは、全体としての世界像です。世界の整然と秩序づけられた体系、つまり「世界(宇宙)論」です。しかし、それはたくさんの自然科学者の協同作業によっては捉えることはできません。自然科学者はある特定の角度から、世界の部分について精密に解明することはできるけれども、その部分を全体との関連において捉えることはできません。それぞれの科学者の部分的世界認識をどれほど巧みに組み合わせ、組織づけてみたところで、本当の意味での統一をもった全体的世界像は捉えることができません。各部分の算術的総和は、決して生きた全体とはいえないのです。この意味で、一人の技師が建物一つない原野で、思いのままに理想的な秩序をもった都市を設計し、建築するのと同じようなことが、一人の選ばれた哲学者に要求されるのです。良識ある哲学者、つまり、デカルトが、最も普遍的な方法に従って、順序正しく理性を導き、認識の領域を可能な限り拡げて行くことによって、新しい学問の体系、つまり、普遍的知恵を実現するのです。それが彼の目指したことでした。
「人間の認識の範囲に入る可能性がある全てのことがらは、同一の仕方ですべて繋がっています。我々が真でないものを真として受け容れることがないように慎まなければなりません。そうすることで、一つのことがらを他のことがらから推論するとき、必要な順序を守れば、いかに遠く隔たっているものでも最後には到達できるのです。また巧みに隠されているものも最後には発見することができるのです。」
(『方法序説(Discourse on the Method)』第二部より)
ここには、デカルト的な方法の理念がはっきりと示されています。彼はいわば、人間に認識可能なすべての対象を同一の仕方で導きだすような、もっとも普遍的な方法を考えているのです。スコラの学者たちは、「さまざまの学問を対象の相違によって互いに区別し、一つ一つ別々に、他のすべてと切り離して研究すべきだ」と思い込んでいる点において根本的に誤っていました。「なぜなら、あらゆる学問は人間的知恵なのです。いかに異なった主題に適用されても、常に同一性を保つようにしなければなりません。ちょうど太陽の光が万物を万遍なく照らすのと同じように、あらゆる問題を差別することなく取り扱わなくてはなりません」というのです。
(『規則論(Rules for the Direction of the Mind)』第一より)
近代科学の分化・専門化という考え方は、デカルトとは全く無縁なものでした。彼はあらゆる可能的対象を、同質的・連続的な認識の秩序の中に投げいれようとしたのです。
『方法序説(Discourse on the Method)』の自伝的箇所には、デカルトがその哲学革命を始めたのは1628年か1629年であることが示されています。この革命は、人間が認識しているものの確実な基礎を発見するために、人間的認識の全機構に、彼の体系的な懐疑の方法を適用することで始められました。『方法序説(Discourse on the Method)』、『省察(Meditations on First Philosophy)』、『真理の探究(The Search for Truth by Natural Light)』において、古代または当時の、どのピュロン主義者が展開したものよりも、もっと強力な懐疑を進めるような手続きが示されました。それは次のような規則から出発しました。
「私が明証的に真と認めた上でなくては、いかなるものをも真として受け入れないこと。いいかえれば、注意深く速断と偏見とを避けること、そして私がそれを疑ういかなる理由も持たないほどに明証にかつ判明に、私の精神に現われるもの以外の何ものをも、私の判断の内に取り入れないこと。」
デカルトは、懐疑への誘因が生じえない限界を明示しようとしました。この規則そのものは、ピエール・シャロン(Pierre Charron)(1541~1603)の著書『知恵(La Sagesse)』で以前に提案されたものにきわめてよく似ています。それらを応用しながらデカルトは、彼の懐疑性の深さの程度が、これまでの懐疑主義者の導入した単純で温和な段階をはるかに越えた深さの懐疑であることを示しました。
最初の二段階は、懐疑の標準的理由を提起するにすぎません。懐疑の第一段階目の感覚的錯覚は、我々の日常の感覚経験の信頼可能性、または誠実性に疑問を向ける根拠が幾つかあることを示しています。懐疑の第二段階目では、我々の経験全部が夢の一部であるという可能性があるということで、認識している世界の実在性を疑う誘因を自身の中に造り出します。これら両段階に基づいて懐疑主義の標準的論題は、我々が日常経験について持っている通常の信念は疑わしいか、偽であるという事態を十分に描き出します。
さらに次の段階の悪霊仮説は、我々が認識していると思っている、そのことの不確実性を表すことに非常に有効です。この可能性は、懐疑主義の全力量を最も顕箸な仕方で露呈するし、今まで誰も触れたことがない懐疑の基底を暴露します。もしも、我々が持っている情報そのもの、または我々が所有している情報を評価、検定する能力を歪曲できる悪い霊がいるとしたら、そのとき我々はいったいどのようにしたらよいのでしょうか。
認識するための基準、またはラベルが、悪霊によって汚染されている可能性がある場合、我々が認識しているものの信頼可能性は、どのように検査しても、まだ疑間の余地が残ります。
デカルトは最も根源的で最も徹底的な荒廃に導く懐疑主義の可能性を徹底的に考察しました。というのは、我々の持つ情報は欺きやすく、幻想的で誤らせやすいのみならず、我々の検定する能力は、最良の状況の下でさえ、誤っているかもしれないとの可能性があるからです。デカルトは次のことを見抜きました。すなわち、この最高段階まで懐疑の熱を高めて、しかもそれからそれを克服できるのでなければ、何ものも確実ではありえないのです。なぜなら我々が認識するものをすべて汚染し、それらすべてを何かの手段で不確実にするような、執拗にとりつき、つきまとう懐疑が常にあるからです。
この悪霊信仰、すなわち我々の検定する能力そのものについての懐疑主義の圧倒的な重要さを、デカルトははっきり知っていました。我々の感覚はときには誤るという事実、また我々の理性は、ときには背理を生みだすという事実があります。またデカルトは、他の誰でも同様な誤りに陥りやすいという事実、それだけの事実を論証的に真として、以前には受けいれたすべてをデカルトは拒否したのです。
省察(Meditations on First Philosophy)でデカルトは、私が2に3を加えるたびごとに(数学)、四角形の辺を数えるたびごとに(幾何学)、あるいは、何かもっと容易なことが想像できるなら、それを判断するたびごとに、私が間違うことは可能であると指摘しました。何か邪悪な力によって我々が絶えず欺かれているとの可能性が、最も明証な事がらや、明証基準についてさえ、懐疑を呼び起こすのです。
デカルトは、懐疑主義の最高点に到着したのです。我々の最も理性的な能力の信頼可能性にも疑問が向けられうるということが提議されると、そのとき人間は、真理の宝庫から不確実性と誤謬との巣窟へと変形されられてしまうのです。
懐疑主義が最終的な状況まで推し進められることによって、かつて「新しいピュロン派」が夢みたものよりも、さらに深いピュロン主義的危機を生じさせたときにのみ、我々は懐疑主義の力を克服することができるのです。懐疑の提起の可能性を終局まで追求するのでなければ、懐疑や不確実性に汚されない真理を発見する希望をもつことは到底できません。デカルトは、平凡な懐疑主義的懐疑を徹底的否定に変化させることによって、コギトの比類ない圧倒的な力の下地を造りました。したがってコギトの確実性を認知することによって、それに逆らうことは、いかなる意志作用によってもできなくなるのです。
懐疑主義者は、我々人間が何かの真理を所有していることを信じませんでした。一方デカルトは、我々人間は真理を所有しているですが、ただ見ることができないだけである、と確信していました。我々を盲目にしているこれらの臆見と信念とは、疑うことと否定することによって除去され、そして真理が輝き出すであろう、と彼はいいました。完全に確実な真理の認知の基準を造りだすことが、デカルトにとって最終的な目標でした。またこの目標を探し出す懐疑主義的方法とは、認識するものに対して徹底的に懐疑が適用されることなのです。この懐疑という「不確実性の泥沼」にあえて飛びこんだがゆえに、デカルトは「コギト」の中に解決が見出され、そして懐疑主義は徹底的に打ち倒されるのです。『方法序説(Discourse on the Method)』の中でデカルトはいいました。
「私がすべてが偽であると、考えようとしている間も、そう考えている私は、必然的に何ものかでなければならないと、私は気づきました。そして『私は考える、ゆえに私はある』(Latin : Cogito, ergo sum・English : I think, therefore I am)というこの真理は、懐疑主義者のどのような法外な想定によってもゆり動かしえぬほど、堅固な確実なものであることを、私は認めました。私は、この真理を私が求めていた「哲学の第一原理」とすることができると判断しました。」
コギトは、懐疑の結末として機能します。懐疑主義を極限まで推し進めることにより、ありとあらゆる仕方によっても疑われえない真理に真面します。つまり考えることの本質がコギトなのです。疑うという過程は、人が自分自身が気づいていることを無理にもその人に認知させ、また人が疑いつつあり、考えつつあるということや、人がここに存在していることを、無理にでも本人に知らしめます。真の認識の発見は奇跡的ではなく、また神の恩寵の特別な作用でもありません。絶対的に確実な一個の真理である「コギト」の発見は、すべてが不確実であるという懐疑主義的態度を打ち倒すかもしれません。しかし、この一個の真理が実在についての認識体系を構成するのではありません。コギトに直面しているという経験が、堅固でしっかりした出発点を与えられていることが前提であり、事物の本性についての認識を発見または正当化するために、コギトとの間に一連の橋が架けられなければなりません。このことの第一歩は、我々の知的真理から実在についての真理へと我々に推論させる明晰判明な原理を設定することです。それは、我々の観念についての一個の真理の主観的な認知から実在の認識への最初の橋を与えることなのです。
デカルトの形而上学
我々の存在と認識のためには、全面的に依存する神が存在しなければなりません。しかし、このことが正当化されるかどうかは、神の責任なのです。神についての明晰判明な観念に基づけられた、この神の概念をもって、デカルトはいまや彼の約束の国、すなわち真理と実在との認識が完璧に保証される定言主義の新世界へ意気揚々と行進しようとしていました。
神は私の創造者であり、神が欺くことはありえません。心に明晰判明にいだくものは何であれ真であると判断する能力を与えられて私は創造されているので、私の判断能力は神によって保証されています。私が明晰判明に認知するものは何であれ真であると私が信じなければならないだけでなく、神の恩寵によりそれは実際に真なのです。この途方もない保証によってデカルトは、理性的認識についての省察の懐疑を消散させることができました。
悪霊が天国と地上とから追い払われてしまったので、数学の真理について、いかなる疑問もなく、数学的真理は明晰判明なのです。我々はそれを無理にも信じさせられます。そして神は欺瞞者ではありません。したがって我々はこの強制の中で安心しておれるのです。自然の真理との接続も、神への我々の信頼によって発見されるのです。観念から生ずる純粋延長の物体の真埋が適合する自然世界が、実際にあることを我々は確信できます。なぜなら我々の観念の範囲を越えるこのような世界が事実上存在するのでなければ、神は我々にそのように考えさせなかったでしょう。
無神論者について
無神論者は明晰判明な観念の客観的真理性についてのこの保証を持つことができません。なぜなら彼らは自分が認識していると思うものを保証する神を持たないからです。無神諭者も数学的真理を明晰判明に認識できるとのメルセンヌの主張に答えて、デカルトは以下のように宜言しました。
「私はそれを否定はしません、しかし私は、無神論者はそれを真の確実な知識によって認めているのではないと主張するだけです。なぜなら疑わしくなりうるすべての認識は、知識と呼ばれるべきではないからです。おそらくそのような疑いは彼の考えに浮ばないでしょう。しかし彼がそれを検討すれば、また他の人より指摘されれば、やはり彼は疑いに気づくでしょう。したがって、彼が最初に神を認知しなければ、あの疑いをいだく危険からは決して免れはしないでしょう。」
それゆえ無神諭者は、どんな真理を知っているにしろ、それらが真であると徹底的に確信することは決してできません。なぜなら、どんなに確信しているにしろ欺かれているとの可能性を決して一掃できないからです。確実性について、世俗的な保証または基底は一切ありません。世俗的世界では、最も明証な事がらにおいてさえ悪霊の欺瞞、または自己欺瞞の可能性が常につきまとっているのです。こうして、神と離れた世界では、どんな真理も疑わしいと考えられうるのです。そして、いかなる真で確実な知識も発見されえないでしょう。神が欺瞞者でないと我々が認めるとき、神のみがすべての懐疑を消滅させることがでます。それゆえ、我々が数学や自然に関する学問において、認識する真理は我々の精神内の真理との単なる類似以上のものであることを神のみが保証できるのです。
私の意見
デカルトは、ピュロン主義的危機からの解放を目指しました。それは、全能の神による依頼でした。誰かがそれを成し遂げなければならないのですが、神はすべての人に対して平等に機会を与えて待っているわけではないと思います。人を指定するのです。デカルトは選ばれました。そのことは彼の著作の中や、書簡の中で表明しています。
神が人間に対して何か願うことがあるのでしょうか。おそらくそれは被造世界の管理者として永遠に存在することだと思います。それでは、なぜそうといえるのでしょうか。神が世界をどのように創造したのかということを考えれば、そういう結論になるのです。懐疑主義的危機からの解放も人間世界が永遠に続くための重要な要素であったと思います。
さて、懐疑とはどのような意味なのでしょうか。それは真理について、話の筋は通っていておおよその趣旨はわかるのですが、示された定言が現実世界や形而上学との関連性に問題があるように思えることで、信頼性がない状態のことであると思います。また、別の言い方をすると、疑うことは真理に磨きをかけることともいえるかも知れません。
デカルトは、ピュロン主義的危機を克服するために神に選ばれました。デカルトは「コギト」を発見しました。「コギト」は現在でいう「唯一性」のことであると思います。「コギト」とは、神の承認であると思います。これは神に選ばれたデカルトならではの発想であって、他人には分かりづらいことであるかも知れません。当時はデカルト自身にしか、わからなかったことかも知れません。しかしデカルトには、それの重要性を他人に説明してわからせる必要がありました。コギトは「唯一性」を表しており、「多様性」とは対立しません。「唯一性」は人間の意識の選択性であり、「多様性」と「唯一性」は対立することなく、共存することができるのです。選択する権限は、神が人間に与えました。デカルトは、「唯一性」の発見過程を詳細に哲学的に記述することに成功しました。
調和や統一という概念は、内部の要素間の関係は相互に緩いのですが、一致は理想であり、ジグソーパズルのように一切の妥協がありません。調和や統一という概念は、規律を厳格にすると内部の要素の関係が崩壊してしまう可能性があります。一致は、調和や統一という概念の上位概念です。隙間がなく、完全に一致することが現実世界においては難しいことであっても、究極の理想ということができます。したがって多様性と共存することができるのです。人間の意識には、「多様性」のように多くの意見をそれぞれ認める考え方と、一つを選ばなければなければならない考え方が存在するのです。二つの概念が複雑に複合している場合もあるかもしれません。
17世紀以後、徐々に定言主義に対する懐疑主義という対立した関係から、「多様性」と「唯一性」という共存できるパートナーの関係に変化して行きました。「多様性」と「唯一性」の共存関係は、17世紀以後の科学革命に貢献しました。デカルトの発見した「唯一性」は、その一翼を担う考え方であると思います。「コギト」は神に選ばれたデカルトそのものです。おそらく他の人では発見できなかったでしょう。デカルトは神の選択により、人間代表としてそれを発見しました。世界を記述する方法が、対立から共存へ変わらなければなりません。
人間は、脳内に宇宙を構築しなければならなりません。学問はそのために必要なのです。科学革命は従来の学問を進化させるための大きなきっかけでした。世界に関する人間の構想と全能の神の世界に関する構想と一致させなくてはなりません。現実世界は目に見えるもの、触れるもの、感じるものだけではないようです。人間が本来持っている感覚の世界観を超えて、簡単には取り扱えないものを探し、見つけて、人間が利用できるようにしなくてはなりません。
誤解されるデカルト
デカルトは、懐疑主義の悪龍退治を得意げに披露したとき、たちまち自分自身が危険なピュロン主義者として、またその理論が空想と幻想にすぎない不出来な定言主義者として告発されているのに気づきました。正統的で伝統的な思想家たちはデカルトを悪意の懐疑主義者と見たのです。なぜなら彼の懐疑の方法は伝統的体系の基礎そのものを否認するからです。それゆえ、たとえデカルト自身が何と説明しようと、彼はエリスのピュロンから続くピュロン主義者の2000年の歴史の頂点とみなされたのでした。一方、懐疑主義的傾向をもつ人々は、不本意で嫌々ではあったのですが、デカルトを自分たちの派の者と認めて、彼は何も成しとげなかったし、彼の主張することはすべて臆見にすぎず確実性のないことであるのを示そうとしました。また定言主義者たちは省察を強く攻撃しました。
デカルト以後も、近代哲学はピュロン主義的危機を考慮に入れねばならなりませんでした。もし誰かがそれを無視しようとすれば、その人のすべての基本的仮説と全結論とは疑間の余地あるものとされ、新しいピュロン主義者の誰かに攻撃されることになるかも知れません。
私の意見
デカルトは自らの哲学を発表しましたが、誤解を受けて攻撃されたようです。デカルトは発表にあたって、何かが説明不足であったのかもしれません。コギトを発見するために、多様性という考えを前提としていたと思います。そのことが説明不足であったように思います。そのために誤解されたのかもしれません。現代に生きる我々からすれば、すぐにわかることなのですが、当時の人々からすると、その前提としていた話がよくわからなかったのかも知れません。